 ビジネスパーソンインタビュー
ビジネスパーソンインタビュー
メンタリストDaiGo著『究極のマインドフルネス』より
DaiGo「人間はもともと、幸せなときに“わざと”不幸を感じるようにできています」
新R25編集部
「マインドフルネス」という言葉を聞いたことがありますか?
「聞いたことはあるけれど、あまりピンとこない」という人も多いかもしれません。
メンタリストDaiGoさんは、自身の新著『自分を操り、不安をなくす 究極のマインドフルネス』(PHP研究所)のなかで、「他人の評価や意見、感情といったものにとらわれずに、自分の本質をありのままに見つめ、迷うことなく人生を全とうするというのが、マインドフルネスなのです」と語っています。
「マインドフルネス」の本質を理解し実践することで、自分の「心」を自由にでき、日々の幸せを一層実感できるそう。
「心」の自由を手に入れるにはどうすればいいのか。
DaiGoさんと、その答えを見つけにいきましょう。

マインドフルネスとは「気づき」
マインドフルネスというのは、直訳すると「気づき」のことです。
では、気づきとは何でしょうか。
たとえば、私たちの脳はつねに、オートパイロット状態、つまり自動運転状態にあります。
次の日に記憶がなくなるほど酔っぱらっても、なんとか家まで帰ってこられるのは、脳が自動運転をしているからです。
現代では、こうした“自動化”が私たちのまわりのいたるところで起こっていて、便利でいいこともある反面、自分が何をしているかがわからなくなったり、物事に喜びを感じられなくなったりするという弊害も引き起こしています。
そこで、もっと細かいところや、ふだん見逃しているところを、先入観をもたず、ありのままに見ることによってさまざまな気づきを得ましょう、というのがマインドフルネスです。
つまり、大事なこと、本質に気づくことが、心の平穏につながるということです。
マインドフルネスによって共感能力が自然に高まり、人のために行動できるようになるだけでなく、自分自身も幸せになり、ストレスから解放されていきます。

マインドフルネスは日常生活の中でできる
でも、何か特別なことをしなければならないというわけではありません。
基本的には、マインドフルネスは、人の話を聞くときや物を食べるとき、作業をしているときなど、実際の生活のなかでできるのです。
まず、「マインドフルネスのABC」と呼ばれているものを紹介しましょう。
●A=アウェアネス(Awareness)
「自分が何をしているのか」に気づくということです。
私たちはふだん、なんとなく行動していることがあります。
たとえば、ご飯を食べながらテレビを見たりしている場合、ご飯を食べるということに対して、マインドフルネスとは逆のブラインドネスになっています。
つまり、「食べる」ということに意識を集中していないのです。
そのため、食べることに対する喜びも感じられないし、自分がどれくらい食べているかも認識していないので、無駄にたくさん食べるようになったりします。
「自分が、いま、何をしているか」に気づくようになれば、楽しいことは楽しいと思えるようになり、得体の知れない怒りや不安が解消されます。
●B=ビーイング(Being)
ご飯を食べている、テレビを見ているなど、自分がしていることに気づきはするけれども、やっていることがいいことなのか悪いことなのかといった価値判断や評価をせず、ただただそういう行為をしている自分がそこに存在している、と客観的にとらえることです。
●C=クラリティ(Clarity)
物事をあるがままに、明確にとらえるということです。
たとえば、いま自分はなんとなく不安だと考えるのではなく、何が不安なんだろうかと問いかけて、「自分はこうなるのが不安なのだ」と明確にとらえるということです。
つまり、自分がしていることに気づきましょう、そして、気づいたことに対して判断を下すのではなく、あるがままに、明確に、その物事をとらえましょう、というのがマインドフルネスなのです。
判断を下さないというのが、とても大事なことです。
たとえば、自分が不安になっているときに、それがいいか悪いかを考えて、悪いと判断したら、自分はすごく悪い状態なんだと、どんどん凹(へこ)んでいってしまいます。
そうではなくて、あるがままに、「ああ自分は不安な状態にあるな」ととらえ、何に対して不安を感じているかを明確にしていくことが、マインドフルネスなのです。
マインドフルネスの感覚を磨くには、まず、「あるがままにとらえる」ことの大切さを理解することが重要です。

人間はつねに「いま」がいちばん不幸に感じる
人は幸せでうまくいっているときでも、不幸や不安を感じることがわかっています。
私自身、いま、仕事はとても順調ですが、それでも不安は感じます。
どんどん新しいことをやっていかないと仕事に飽きてしまうかもしれないとか、成長できずに立ちどまったらおしまいだとか、やはり考えるものです。
これはなぜかというと、そう考えるシステムが人間の脳に刻み込まれているからです。
私たちは、不安を感じ、危ないと思うからこそ、次を考えて準備をし、分析することで前に進んでいけるのです。つまり、人間は不幸や不安を感じやすくできているのです。
とても幸せで充実しており、仕事もうまくいっていて不満もなく、いい家族にも恵まれ、友達もたくさんいるという状況にもかかわらず、なんだか悶々として不安を感じたり、幸せの絶頂といえるほど充実しているのに、突然、不幸を感じてみずから幸せを手放すような行動に出たりする人がいます。
不思議に思えますが、じつは、普通のことなのです。
私はこんなに幸せであってはいけない、分不相応だと感じて不安になる…これが普通なのです。
つまり、人間というのは、「いま」がいちばん不幸や不安を感じるように適応してきたのではないか、とアメリカのノックス大学の心理学者フランク・マクアンドリュー博士は述べています。
たとえば、産業革命以前の時代は、今日を生きるために一生懸命働かなくてはなりませんでした。
その後、機械化や自動化が進むと、これからは人間が働く時間を減らすことができるだろうと、みんなバラ色の未来を想像しました。
でも、人間はいっこうに幸せにはなっていないし、いまでもみんな変わらず働いています。
AI(人工知能)やIT、自動化などが進んでいるにもかかわらず、ほとんどの人の労働時間は変わっていないし、自由な時間も増えていません。
なぜでしょうか。
マクアンドリュー博士は、人間がいっこうに幸せにならない理由について調べた結果、さまざまな科学的根拠をもとに、人間には、そもそも幸せを感じにくくさせるような、幸せになりそうだとそれをとめるような心理的なプログラムがあるのではないかという説を唱えています。
自分はいま幸せで、このままずっとやっていけるとなったら、私たちは努力も注意もしなくなります。
だから、幸せを感じると、それに水を差す心理が働くのではないかということです。
そうした心理作用によって、このままの状態が続くことはないとか、うまくいくわけがないといった悪魔のささやきが起こるわけですが、そのおかげで私たちは生き残ってきたのです。
不安を感じにくい人たちは、失敗したり裏切られたりして子孫を残すことができず、調子がいいときでも不安を感じやすい人たちが生き残ってきたのだといえます。
つまり、私たちはもともと、幸せなときにわざと不幸を感じるようにできているということです。
ですから、不幸や不安を感じるのは悪いことではなく、そういう性質があることを理解したうえで、いま自分が感じている目の前の幸せを楽しむことが重要なのです。
自分の「ありのまま」を受け止める
『自分を操り、不安をなくす究極のマインドフルネス』では、今回紹介した内容以外にも、脳科学、運動、呼吸法、そして瞑想など、あらゆる角度から「心」の自由を与える方法を教えています。
「心」といっても観念的な概念に留まるものではありません。
DaiGoさんが同書で語っている通り、心と体はつながっています。
自分らしさを最大限に引き出せるマインドフルネス。ぜひ日常生活の中で実践してみてください。

ビジネスパーソンインタビュー
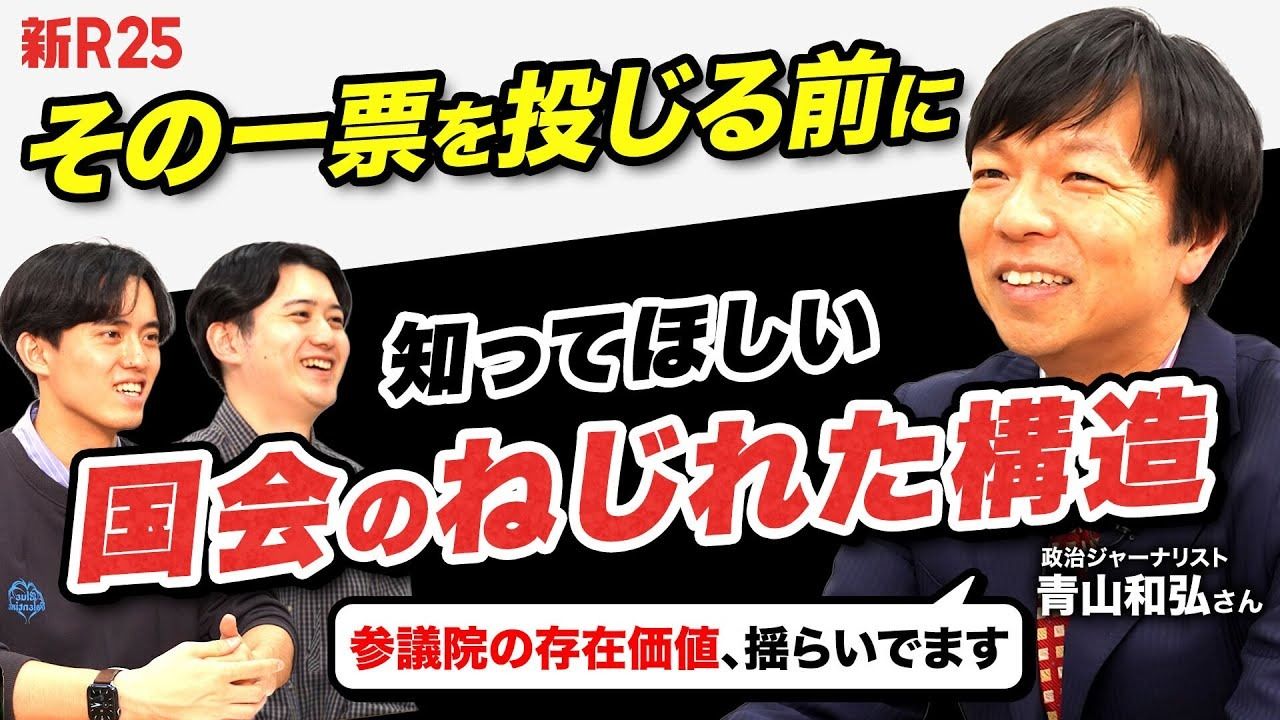
【参議院はAIに?】ダラダラ決められない国会なら、参議院を「革新の議会」に変える逆転の発想【Judge25 参議院必要?不要?】
新R25編集部
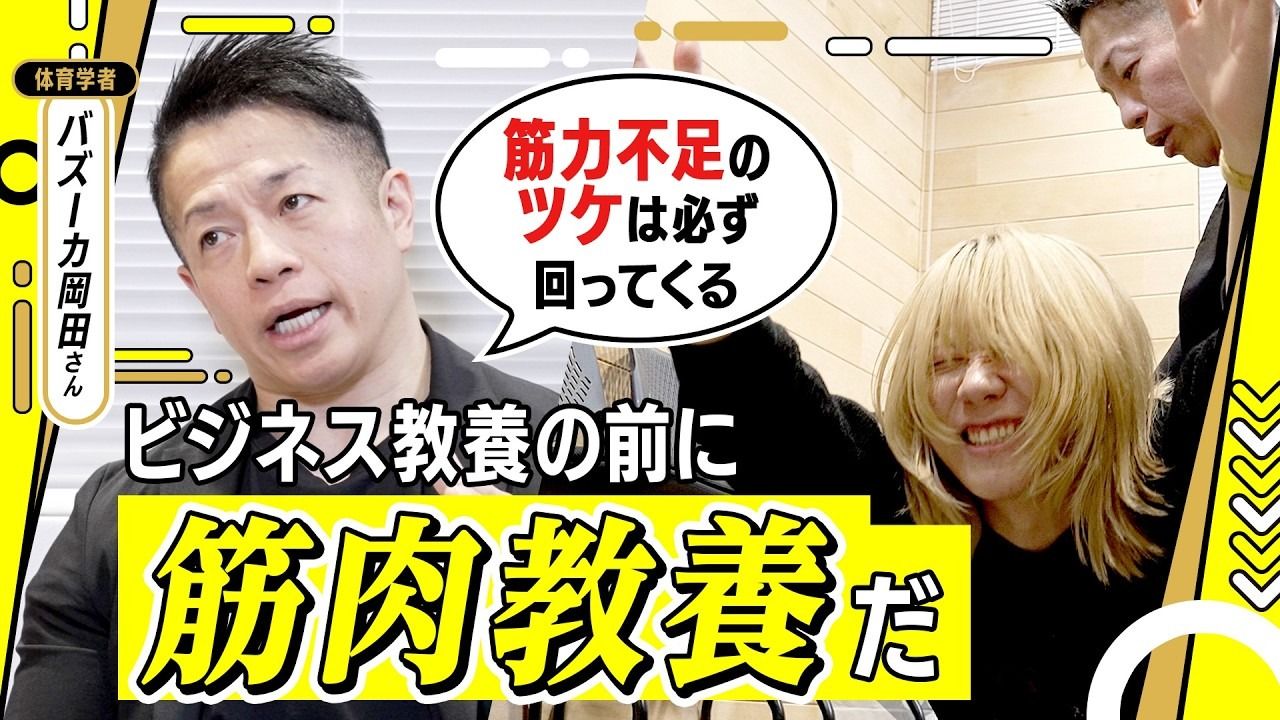
「ツケは必ず回ってくる」バズーカ岡田さんが岸谷蘭丸に説いた、「忙しいから」を理由に筋トレを一切しないことのリスク
新R25編集部
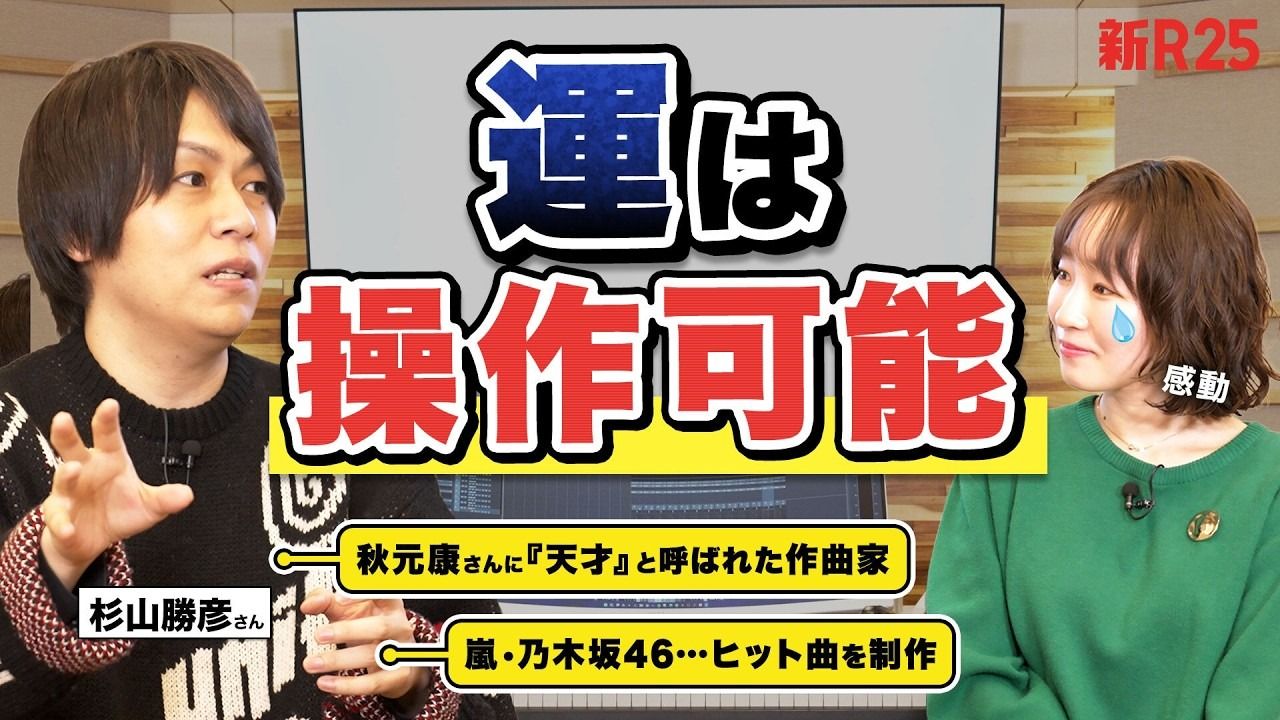
「実力はあるのに選ばれない人」の特徴は?秋元康さんに"天才"と呼ばれる作曲家の納得回答
新R25編集部
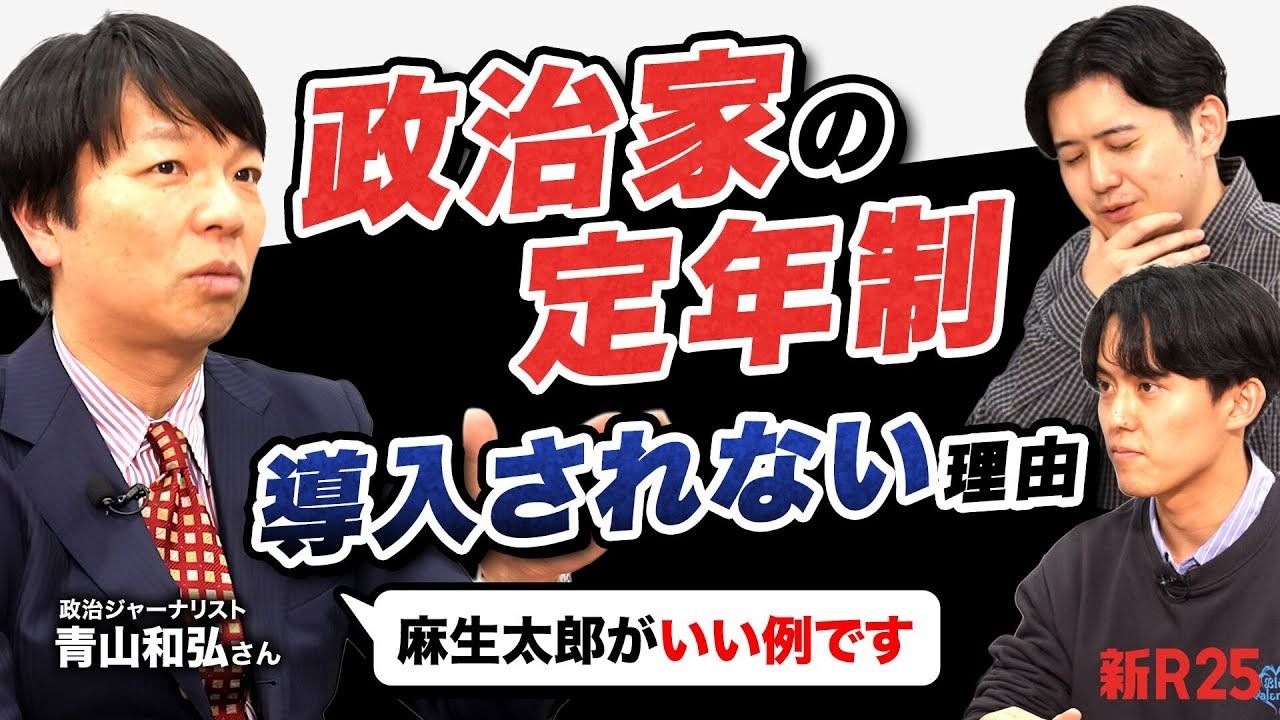
なぜ政治家だけ定年がない? "若手"52歳で社長を降りたCA藤田社長との「辞め時」の決定的違い【Judge25 政治家に定年は必要?】
新R25編集部
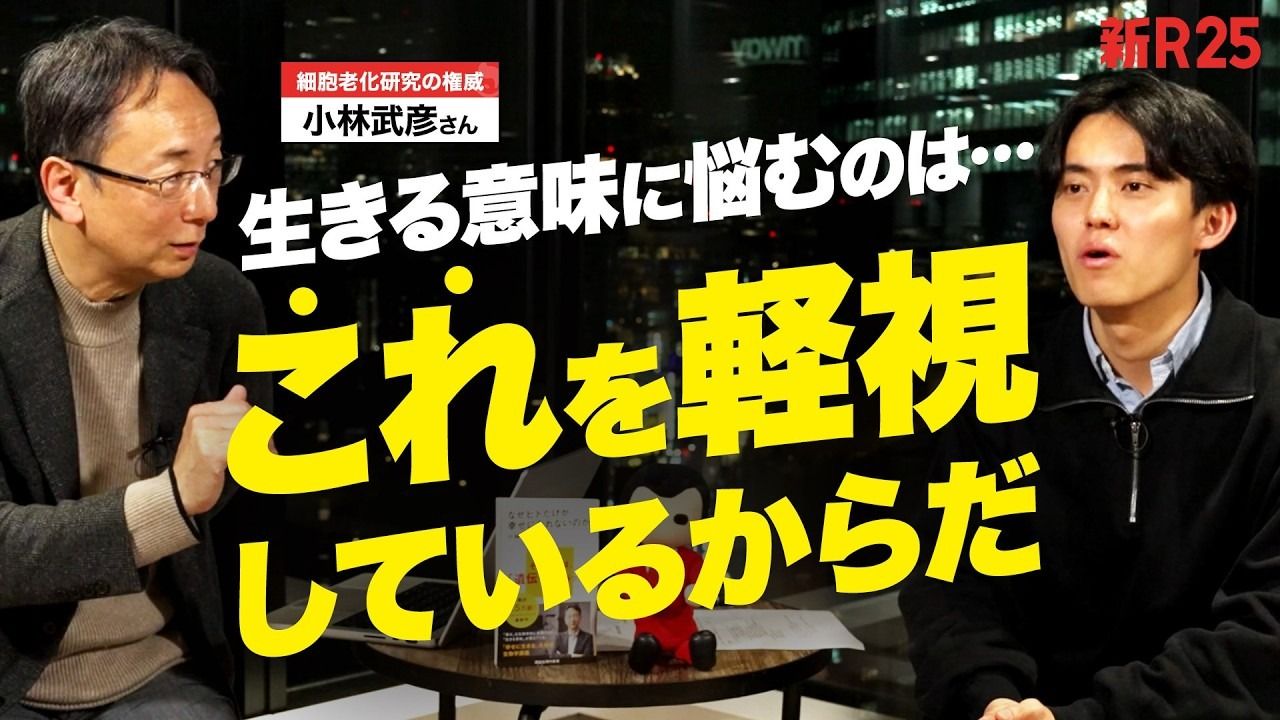
「意外と軽視されてるのが...」生物学者・小林武彦先生が教えてくれた、ヒトが生きる意味に悩む理由
新R25編集部
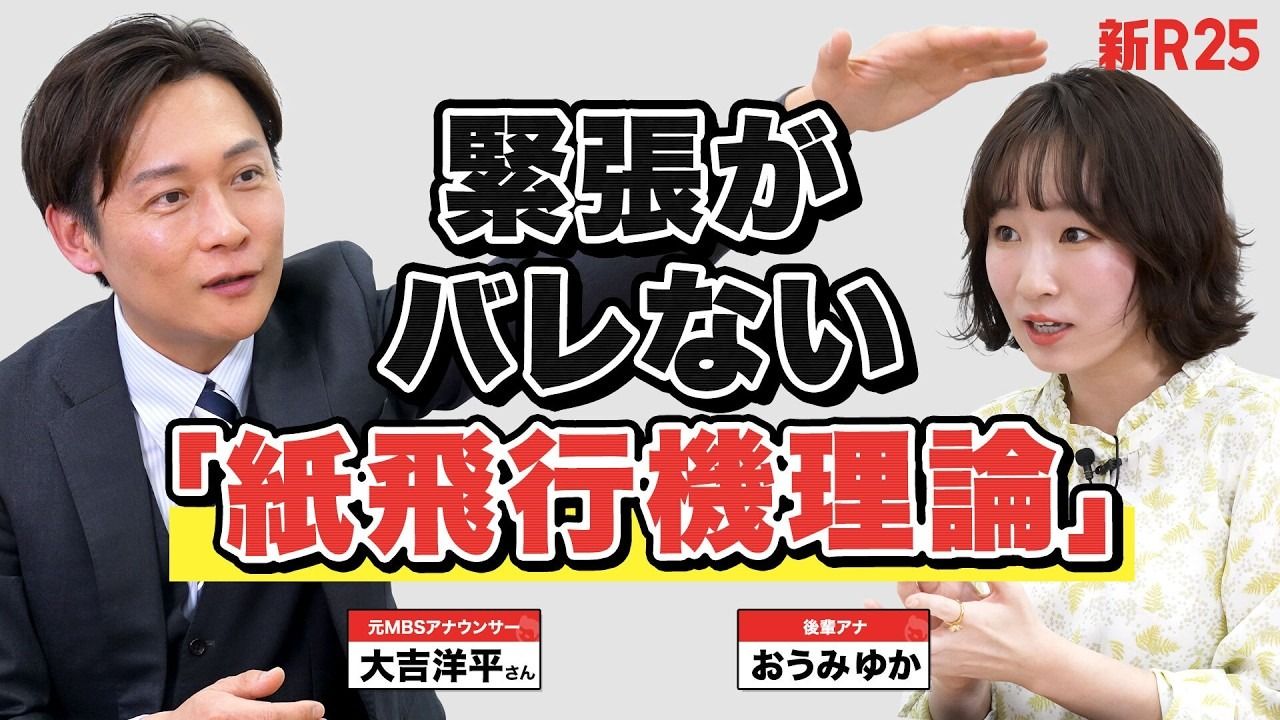
「緊張していい。堂々とビビれ」実況のプロが実践する、緊張がバレない"紙飛行機理論"
新R25編集部




