 ビジネスパーソンインタビュー
ビジネスパーソンインタビュー
佐藤 純著『ビジネスパーソンのための低気圧不調に打ち勝つ12の習慣』より
天気痛は“低気圧”が原因ではない。雨の日に体調不良になる理由を専門家が徹底解説
新R25編集部
「頭が痛くなる」「憂うつになる」「耳鳴りがする」「めまいがする」…
雨の日になると決まって、このような辛い症状に悩まされる人も多いのではないでしょうか?
天気痛ドクター・医学博士の佐藤純さんは、「国民の4人に1人は天気痛の可能性があるのではないかと感じていますが、天気痛は適切な予防と対処法によって、ずいぶん軽減されることもわかってきました」と言います。
佐藤さんの著書『ビジネスパーソンのための低気圧不調に打ち勝つ12の習慣』から、天気痛が起こる原因や、どのように体調管理するのがベストなのかを抜粋してお届けします。

「天気痛」の症状は千差万別
ビジネスパーソンのための低気圧不調に打ち勝つ12の習慣
雨が降ると頭が痛くなる、台風が近づくと肩こりがひどくなるなどといった天気の変化に起因する症状を「天気痛」と名付け、研究や治療にあたってきました。
天気痛によって引き起こされる代表的な症状は以下です。
ビジネスパーソンのための低気圧不調に打ち勝つ12の習慣・頭痛
・めまい
・首痛・肩こり
・耳のトラブル
・気管支ぜんそく
・古傷
・心の不調
天気痛と一口に言っても、その症状はさまざまです。
そもそも天気痛は、「病気」ではなく、「病態」です。
天気の影響を受けやすい病気がもともとあって、天気によってその症状が引き起こされたり悪化をしたりするため、人によって症状は千差万別なのです。
例えば、片頭痛持ちの人であれば、頭痛やめまいの症状を引き起こしますし、肩こりになりやすい人は、肩こりの症状がひどくなります。

不調を引き起こす原因は気圧の「低さ」より「変化」
誤解されることも多いのですが、天気痛は「低気圧だから」不調になるのではなく、「気圧の変化」によって症状が出やすくなります。
そもそも低気圧というのは「まわりの空気よりも気圧が低いところ」、高気圧は「まわりよりも気圧が高いところ」を指します。
ですから、具体的に何ヘクトパスカル以下が低気圧というような定義があるわけではありません。
私が天気痛を長年研究していくなかで、天気痛に影響する3つのキーワードが見つかってきました。
まず1つめは、「内耳」(耳の奥にある気圧を感じ取っている部分)。
2つめは、「脳の過敏性」(内耳が刺激を受けたときに、その刺激をどのように捉えるかというもの)。
そして3つめが、「自律神経」です。
ビジネスパーソンのための低気圧不調に打ち勝つ12の習慣
私は、内耳にある気圧を感じるセンサー自体の感受性が人によって差がある可能性だけでなく、この脳の過敏性についても個人差があるのではないかと考えています。
実際、天気痛の症状がある人は一般の人に比べて、3倍ぐらい内耳の感覚が敏感だというデータもあります。
このように敏感な体質の人は、気圧が変化すると、脳が疲れるほどの痛みが繰り返し出てきたり、めまいがしたり、さまざまな体調不良が起こったりします。
そして気圧が変化するたびに、脳に刺激がいくようになると、だんだん脳が過敏性を帯びてきます。
今までは痛くなかったものが痛いと感じるようになったり、気にならなかったものが気になるようになったりします。
これを、脳過敏症候群(のうかびんしょうこうぐん)ともいいます。
脳の過敏性により必要以上にストレスを感じると、脳は自律神経に指令を送り、交感神経が優位になります。
その結果、頭痛をはじめとするさまざまな症状を引き起こすわけです。
ビジネスパーソンのための低気圧不調に打ち勝つ12の習慣

「天気痛」に悩む人が増えている理由① 気候変動
私が天気痛・気象痛外来を開設して15年以上が経ちますが、天気痛の患者さんは増え続けています。
理由はいろいろと考えられますが、その1つが気候変動です。
近年の地球温暖化の影響で、日本でも夏は40度を超える猛暑日が稀ではなくなり、熱帯地方のようなゲリラ豪雨も発生しています。
また、台風も非常に強い勢力を保ったまま日本に上陸することも増えています。
以前は、春や秋など、暑さと寒さの過渡期となる気候のよい時期がありましたが、近年では9月の終わりまで真夏日が続くことも例外ではなく、その後、急に寒くなり冬が終わったと思ったら、いきなり暑くなるような気候が続いています。
急激な気温変化は、当然、私たちの体にも大きな負担をかけています。
季節の変わり目に体調を崩したり、風邪をひきやすくなったりするのはそのせいです。

「天気痛」に悩む人が増えている理由② 自律神経がサボり出している
また、天気痛の患者さんが増えた理由としてもう1つ考えられるのが、私たちが冷暖房完備の環境で過ごすようになり、体に本来備わっていた体温調節の能力が落ちてきているということです。
この体温調節機能には、自律神経が深くかかわっています。
私たちは夏の暑いときは、汗をかくことで体の中の熱を発散し、体温を下げます。
そして冬には、体の熱を体内にとどめる機能があります。
これらは自律神経がコントロールをしています。
しかし、人間の体は、甘やかしてしまうと、快適なほうへと状態を合わせていきます。
エアコンの効いた快適な部屋で同じ環境にいるというのは、体にとって楽なことです。
コロナ禍で、ますます外出する回数が減り、環境が変わらない生活をしている人が増えました。
そういった生活は、自律神経にとってはストレスが減っていることになりますが、逆にストレスが減ることによって、自律神経が少しサボり出しているとも言えます。
つまり、これは自律神経のトータルパワーが落ちて、交感神経と副交感神経の切り替える能力が弱くなってきているということです。
そのような状態の中で大きな気圧変化や温度変化が容赦なく襲ってきても、自律神経の切り替えがうまくいかず、防御機能が働かなくなってしまっているために、天気の影響を受けて体調を崩す人が増えているのです。

雨の日の不調、「天気のせいかもしれない...」と考えてみよう
日本人の中で、片頭痛の方は8%ぐらいいると言われています。
そして、そのうちの半分は天気の影響を受けていると考えられています。
一方でストレスとの関係が深いと考えられている緊張型の頭痛の方は、片頭痛よりも人数が多く、この頭痛も半分ぐらいの人が、天気が崩れるときに調子が悪くなると言われています。
近年、体調不良が原因で会社を休んだり、遅刻をしたりする「アブセンティズム」や、出社をしても体調が万全でないため、パフォーマンスが落ちてしまう「プレゼンティズム」が、企業の労務管理において、生産性の低下を引き起こす要因として問題視されています。
これは、ビジネスパーソンの多くが、生産性が下がってしまうほどの体調不良に悩んでいるということです。
実際、私の外来にも、不調で仕事を辞めた方や長期休職に入っているという方が多くなっています。
さらに近年、そういった重度の患者さんは、男性のほうが多くなってきています。
これは、女性よりも男性のほうが、我慢できる限界ギリギリまで通院する機会をつくらないという傾向があるからと考えられます。
特に、大きな組織で仕事をしている方に天気痛やうつ症状で悩まれる方が多いようです。
パソコンに向き合っている時間が長いというのもあるでしょうが、組織が大きく、自分の思うように身動きがとれずにストレスを溜めこんでしまうという特性があるからかもしれません。
いずれにせよ、イライラしたり、落ち込んだり、頭が重く感じたり、仕事に行くのがつらいといった症状は、「天気のせいかもしれない...」と考えてみることから始めてみてください。
気圧による体調不良をなんとかしたい方の必読書
『ビジネスパーソンのための低気圧不調に打ち勝つ12の習慣』では、痛みの傾向を知る方法から痛みの元となる慢性痛への対応まで、12のカテゴリに分けて紹介されています。
気圧による体調不良が辛い人や、どんな天気でもいつもの調子で仕事をしたい人は、ぜひ読んでみてください!

ビジネスパーソンインタビュー
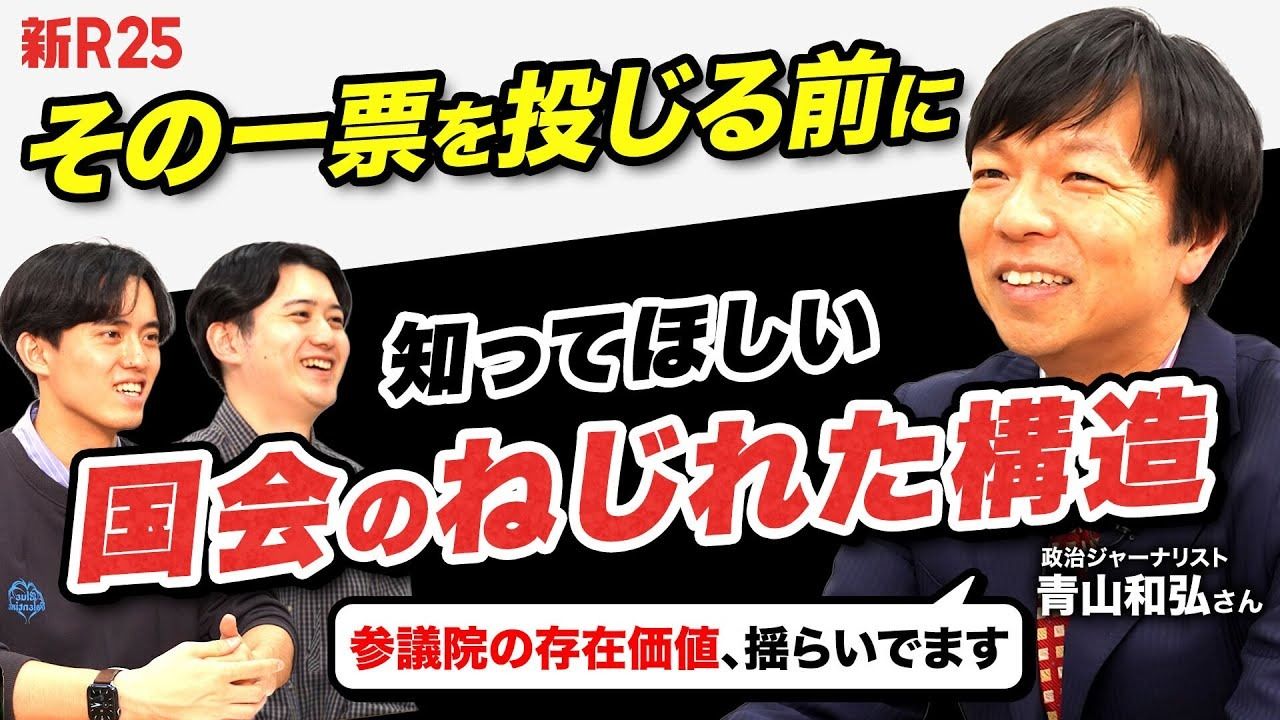
【参議院はAIに?】ダラダラ決められない国会なら、参議院を「革新の議会」に変える逆転の発想【Judge25 参議院必要?不要?】
新R25編集部
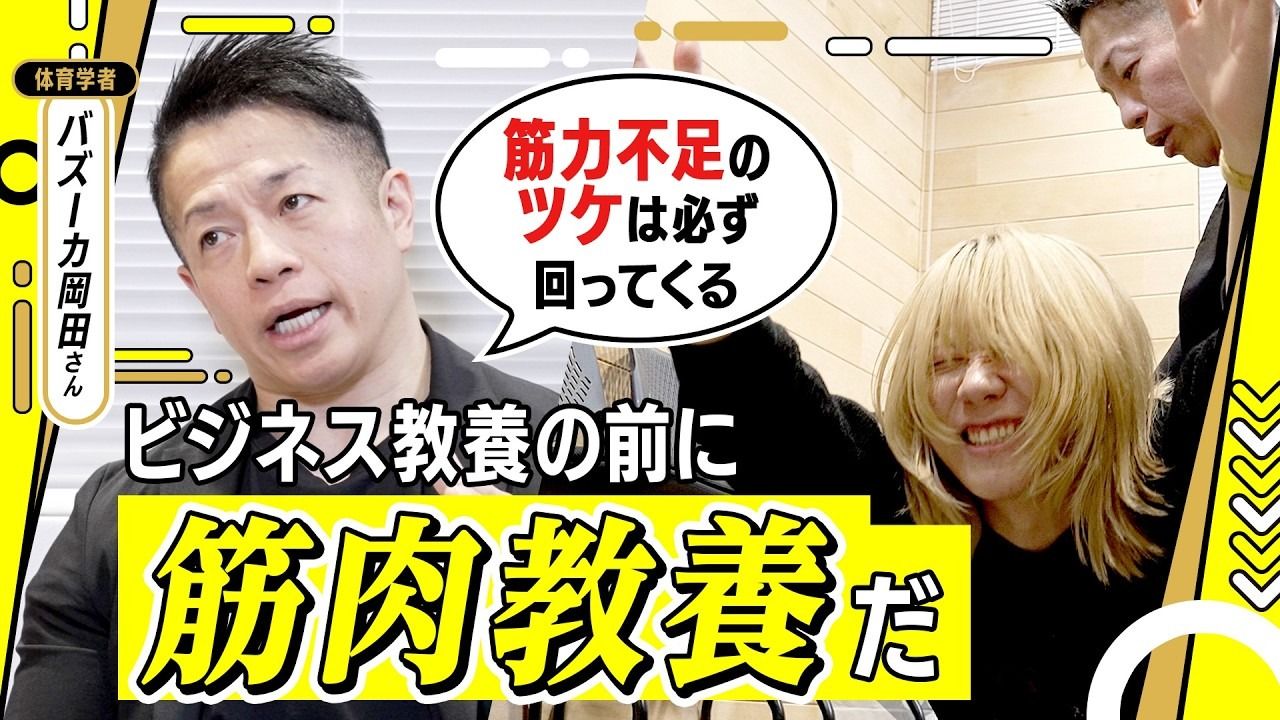
「ツケは必ず回ってくる」バズーカ岡田さんが岸谷蘭丸に説いた、「忙しいから」を理由に筋トレを一切しないことのリスク
新R25編集部
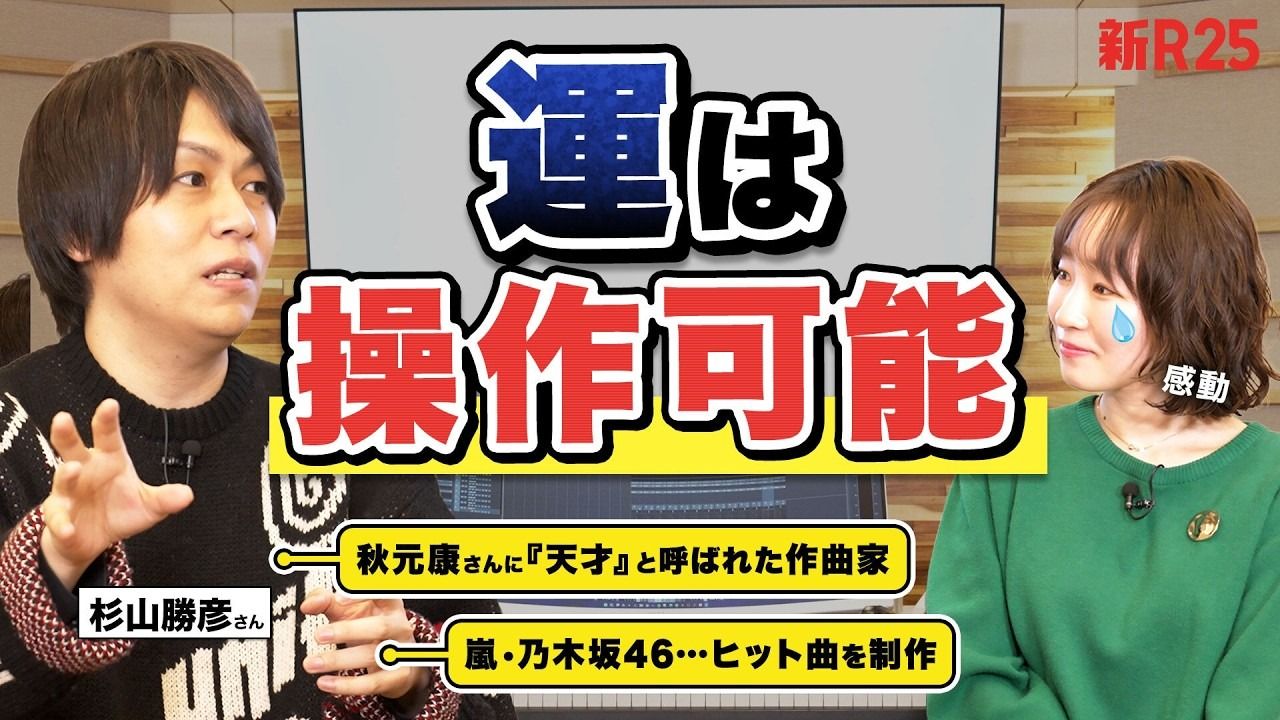
「実力はあるのに選ばれない人」の特徴は?秋元康さんに"天才"と呼ばれる作曲家の納得回答
新R25編集部
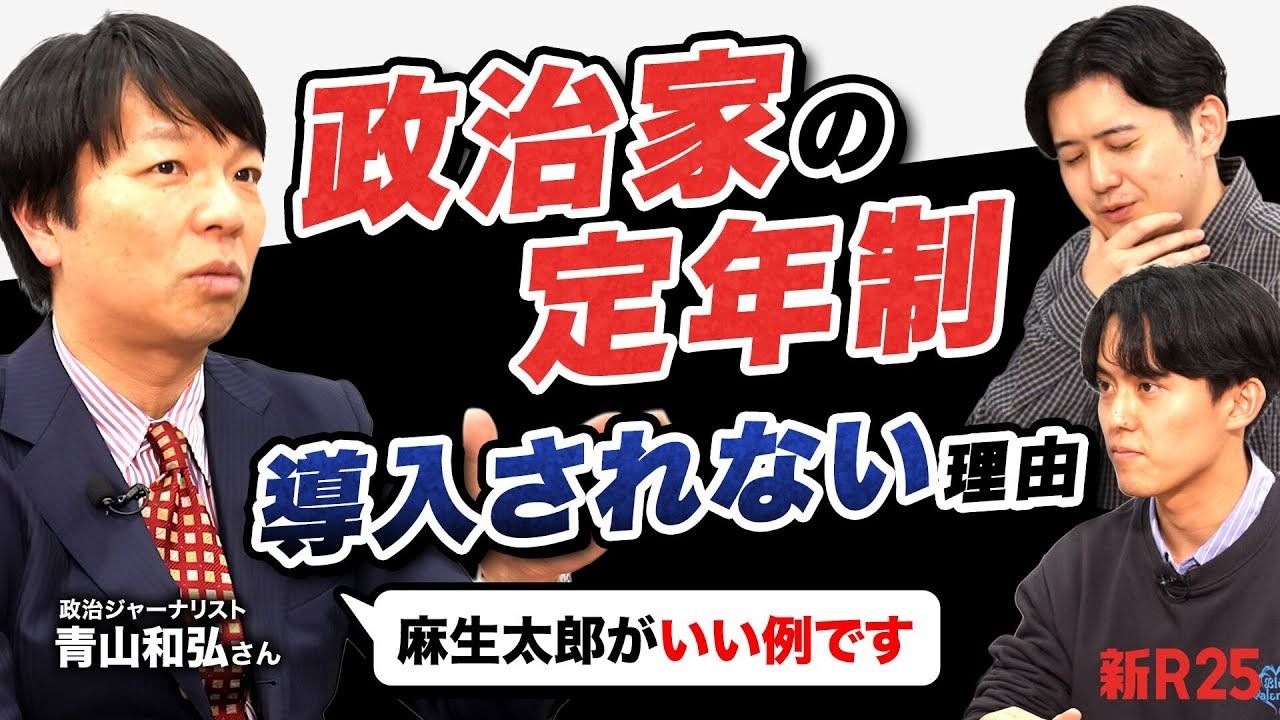
なぜ政治家だけ定年がない? "若手"52歳で社長を降りたCA藤田社長との「辞め時」の決定的違い【Judge25 政治家に定年は必要?】
新R25編集部
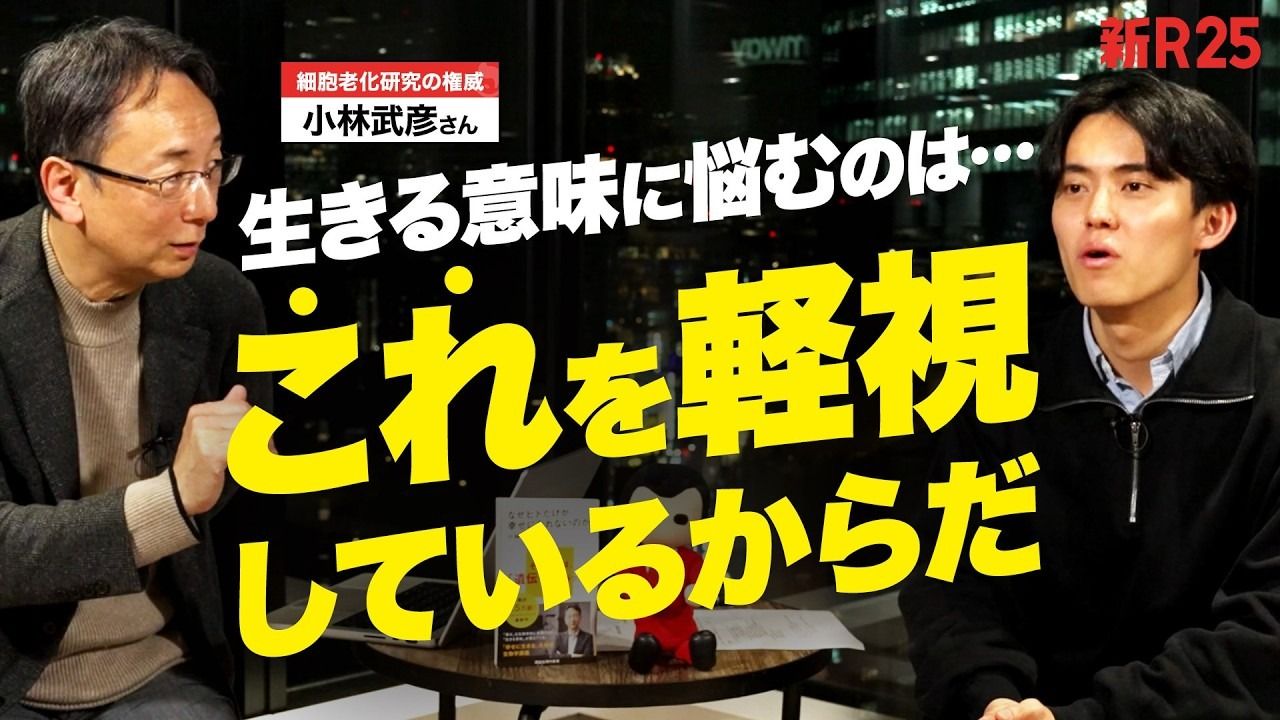
「意外と軽視されてるのが...」生物学者・小林武彦先生が教えてくれた、ヒトが生きる意味に悩む理由
新R25編集部
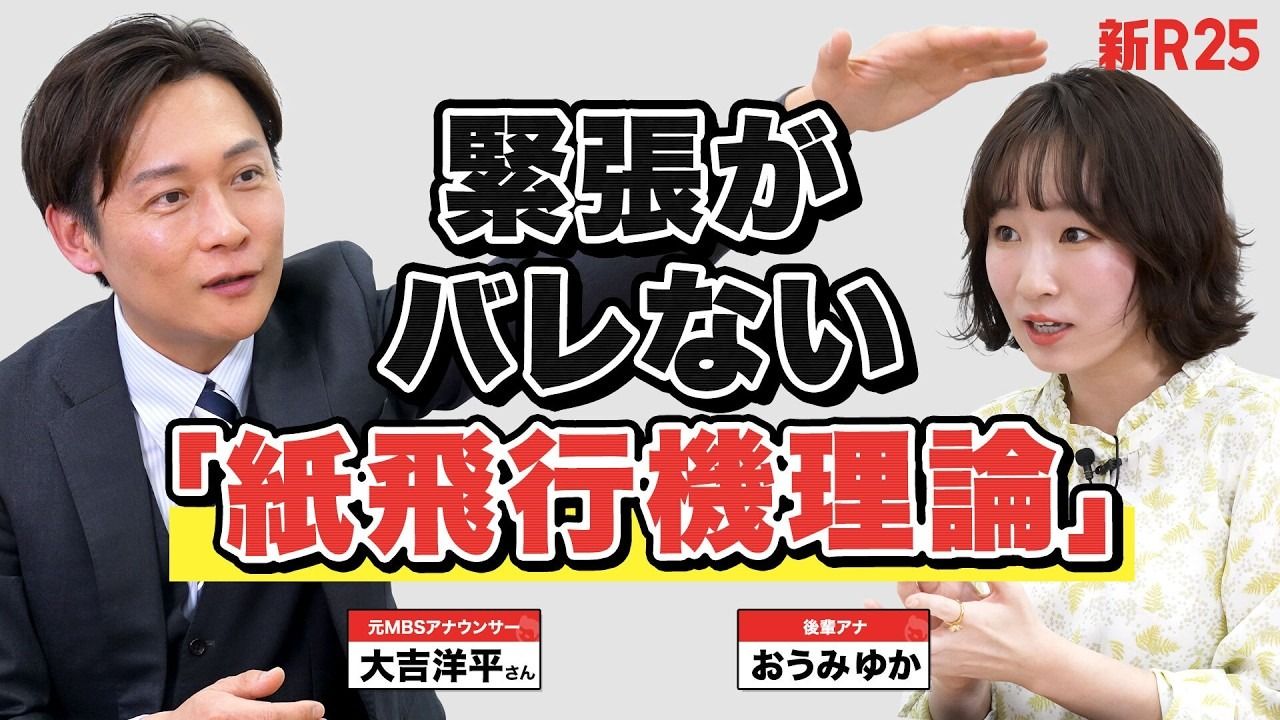
「緊張していい。堂々とビビれ」実況のプロが実践する、緊張がバレない"紙飛行機理論"
新R25編集部







