 ビジネスパーソンインタビュー
ビジネスパーソンインタビュー
新人研修で重要なのは「目線の提示」
有意義な新人研修とは? なぜ若いうちから本を読むべき? 有名企業3社の役員が熱弁
新R25編集部
そろそろ入社から1カ月。会社の一員としての基礎を叩き込まれる、「新人研修」を終える頃だと思います。
なかには泊り込みの合宿や、1カ月以上続く長期の研修を行う企業もあるようですが…「これ、意味あるのかな」って思う瞬間、ぶっちゃけありませんでしたか?
では、「本当に有意義な新人研修」や「新入社員が身につけるべき習慣」とは何なのでしょうか? 今回は、人材育成に長けた有名企業3社の役員のみなさんに語りあってもらいました。
【写真左】旅行サイト「エアトリ」の運営など4つの事業を営む株式会社エボラブルアジア代表取締役CFO 柴田裕亮(しばた ゆうすけ)さん/【写真中央】発売から2週間で5万部を突破した『THE TEAM』の著者であり、株式会社リンクアンドモチベーション取締役 麻野耕司(あさのこうじ)さん/【写真右】サイバーエージェント取締役 人事統括 曽山哲人(そやま てつひと)さん

ほし
いきなりですけど、「新人研修」って退屈じゃないですか?
入社して1カ月経とうとしてる今、研修がつまらなくてうんざりしてる新入社員は結構いると思います。
あの時間って、本当に意味があるのでしょうか?
「おぉ、まったく研修の意義を感じてない若手がきたぞ」の図

麻野さん
つまらないことの方が多いですよね、新人研修(笑)。

曽山さん
ほしさんが「つまらない」と言うのはおそらく、長いうえに一方的な研修を経験したからだと思います。そういう研修の場合は、目的を充分に果たせていないことが多いですね。

ほし
“長いうえに一方的”、ですか。

曽山さん
座学で、講師の話が延々と続くような研修です。情報量が多いわりに、受け手は興味を持てずにすぐ忘れるという。

ほし
あ、まさにそんな感じでした。バレないように寝てる人もチラホラ…でもそういう研修って珍しくないですよね。
サイバーエージェントでは、どんな研修をしているんですか?
新人研修は「知識」ではなく「意識」ファーストであるべき

曽山さん
サイバーエージェントでは、ビジネス職・エンジニア職・デザイナー職の全員が参加する研修は3日間だけですね。

麻野さん
僕のところも3日間です。

ほし
3日間だけ。短いですね。

曽山さん
数年前までは1カ月だったんですが、「早く配属してくれ」という現場の声と「研修が長い」って新入社員のクレームがありまして(笑)。徐々に短くしていって、今では3日間になっています。

ほし
その3日間では具体的になにをしているんですか?

曽山さん
5〜6人のグループになって、その代のスローガンを決めてもらっています。今年なら19年卒の全体スローガンをグループごとにプレゼンして、全員で投票して決めるっていう。

柴田さん
すごくいいですね、それ!

曽山さん
育成研修っていうのは、目線の提示がすごく大事です。
アクションを教えるというよりは、「この目線を持ちましょう」というメッセージング。

麻野さん
本当にそう思います。ウチの会社もかなり意識しています。

ほし
スローガンを決めることが、目線の提示になるんですか?

曽山さん
なります。視座って放っておくとどんどん下がっていくんですよ。入社当時はやる気に満ち溢れているけど、嫌な仕事とか上司に怒られたりすると、どんどんやる気がなくなるというのは視点が下がっている兆候です。
視座を上げるためには高い目標が必要で、かつ覚えやすいものがいい。もっと言えば、与えられるよりも、自分たちで言語化してつくったものがいいんです。愛着が生まれますから。

麻野さん
新人研修って、「知識」と「意識」の順序を間違えるとまったく響かないんですよ。
コンテンツうんぬんの前に、順序が正しいかどうかです。

ほし
リンクアンドモチベーションの研修は、どんな順序で行なっているんですか?

麻野さん
「エンゲージメント(共感)」「スタンス(姿勢)」「スキル(能力)」の順です。
意識はエンゲージメント、知識はスキルに当てはまると考えてください。
そもそも営業したくない、会社に共感してない人に、スキル叩き込もうとしても吸収できないでしょ? 喉乾いてないやつに「水飲め!」と強要しているのと同じですよ。
「そりゃ飲まないでしょう」「飲まないですね(笑)」

麻野さん
サイバーエージェントのスローガン研修も、会社と同期を好きになる仕掛けになってますよね。まず共感してから協力してスキルつけていく順序が大事で、知識は現場で身につけたらいいんです。

柴田さん
エボラブルアジアは、まさに「スキルは現場で身につけろ」を重視した研修になっています。いきなりお客様からの電話対応の経験もさせますし、お客様へのチケット発行もさせます。

ほし
え、早くないですか!?

曽山さん
エボラブルアジアさんみたいにBtoCのサービスを運営している会社は、現場を体感させることが、一番新入社員の意識を変えるんでしょうね。
危機意識を醸成するために「自分に足りないもの」を理解させることも重要

柴田さん
当社はお客様と直接やりとりをするサービスを運営しているので、新入社員かどうかは関係なく「お客様の前に立ったら会社の代表になる」という責任感を持ってもらう必要があります。

麻野さん
実際に電話一本とったらわかりますもんね。いかに自分が会社のサービスについて無知であるか。

柴田さん
そうです。危機感を抱かないと、必死でスキルを身につけようとは思わないですから。

曽山さん
「いかに自分がなにもできないか」を体感させられたら、新人研修はそれだけで成功とも言えますね。

ほし
サイバーエージェントでも、そういう研修があるんですか?

曽山さん
ありますよ。例えばメディア部門の研修は、「期限以内に参加者約30人が全員でロープレの複数ステップを突破せよ」というプログラムになっています。

麻野さん
いいですね、そのゲーム性! でも結構キツいんじゃないですか?

曽山さん
事業って、1人で勝ち上がっても意味がないじゃないですか。常に人を巻き込まないといけない立場なので、個としては優秀なメンバーが揃っていますが、「自分視点」のままではずっと無力なんですよね。
だから、「実際に自分が追い込まれているとき、隣のメンバーのためにどこまでやれるか」を突き詰める必要があります。

柴田さん
優秀な新人にこそ、足りないものを自覚させるのは研修のすごく大事なポイントですね。
「新入社員、まったく本を読めない問題」について

柴田さん
それからエボラブルアジアでは、新しく新人研修に「audiobook CAMP」を導入することにしました。

麻野さん
「audiobook CAMP」ってなんですか?

柴田さん
耳で聞く読書「audiobook.jp」の新社会人・若手社員向け月額サービスです。

ほし
本って、読まなきゃとは思いつつなかなかハードルが高いんですよね…忙しい新入社員ならなおさら。

柴田さん
その点「audiobook CAMP」は耳の“スキマ時間”を活用して情報のインプットができるのがメリットだと思いました。

曽山さん
20代のうちにものすごく本を読めてる人って、まだ少ないと思いますよ。
若手社員とご飯に行ったときにオススメの本をあげたりしますけど、普段から読んでる人は限られていますね。

柴田さん
当社の代表の吉村もおもしろかった本をみんなに勧めたり、「興味がある人は部屋に来てくれればいつでも貸しますよ」って伝えていた時期があるんですけど、食いつくのは一部の役員ばかりで…

ほし
私も“積ん読”しがちなので耳が痛いです…
文化庁が公表している平成25年度「国語に関する世論調査」では、約半数の47.5%が一月に読む本は「0冊」だと回答している。20代は40.5%だった。

曽山さん
やっぱり、若い人は紙の本にプレッシャーを感じますよね。

ほし
プレッシャー?

麻野さん
本をいざ手に持つと、「これ読み切れるかな」ってビビっちゃうんですよ。

ほし
なるほど、たしかにそうですね。
途中で読むのをやめるのってちょっとした挫折感がありますし、読みきれないかもと思うと手を出すのが億劫になります。

曽山さん
僕も20代のときは全然本を読めてなかったです。
多読になったのは、30代で人事になって「このままでは成果が出ない」という危機感を感じてからですね。

柴田さん
たしかに、そういう経験をしないとなかなか本を読む気になれない人も多いと思うんですけど、とくに20代の社員たちには読書の習慣をつけさせたいと思っていて。
だから移動時間やちょっとした休憩時間でも手を出しやすい「オーディオの本」は、読書のハードルを下げてあげる意味でもすごくいいなと思ったんですよね。

曽山さん
これなら若い人たちにも読んでもらえそうな気がします。

柴田さん
しかも、各業界で活躍しているセレクターが若手ビジネスパーソンにおすすめの本を毎月2冊選書してくれるので、選ぶ手間も省けるんですよ。

麻野さん
へ〜、いいですね!
読書の最大のメリットは「使える言葉」が増えること。優秀なリーダーは言葉が強い

ほし
みなさんものすごく本を読まれていると思うのですが、そもそも、なぜそんなに読書を重要だと考えているんですか?

曽山さん
出会った本の数だけ、「使える言葉」が増えていくからです。
成果を出し続けているすごい経営者は、みんな言葉のセンスがとてもいいですよね。誰でも言えるような、ありきたりな言葉を使わない。

ほし
たしかにそうですね。

曽山さん
優秀なリーダーって、本当に言葉の力が強いんですよ。
それはたくさん発信しているからとか、取材慣れしているからじゃないんです。単純に、使いこなせる言葉の量が違うから。語彙力の差です。

ほし
なるほど…人を動かしたいなら、言葉をたくさん持つことが大切なんですね。

曽山さん
そうです。言葉をたくさん持ちたいなら、本をたくさん読むこと。
麻野さん「めっちゃいいこと言うじゃないですか〜! 曽山さんの次にしゃべるの超イヤなんですけど〜!」

ほし
仕事でいろんな人と話しているうちに自然と語彙力が上がっていくということはないですか?

麻野さん
ものすごく表現豊かな人と会話をしていたとしても、彼らの言葉に触れただけで自分の表現力が上がるわけではないですよね。
曽山さんが言う「言葉を使いこなす」とは、言葉を自分のものにしているということです。
言葉に触れるシーン自体は他にもありますが、「言葉を染み込ませる」ことは、本でしかできないことだと思います。

ほし
言葉を染み込ませる。なるほど…!

麻野さん
それに人って、自分が思っている以上に“使う言葉”によって見える世界を左右されているんです。
ほしさん、蝶々ってキレイだと思いますか?

ほし
え? …そうですね、思います。

麻野さん
じゃあ、蛾は?

ほし
蛾…は、キレイだとは思わないですね。

麻野さん
でもフランス人は、両方キレイだと思うんですよ。なぜなら、蝶々も蛾も「パピヨン」と呼んでいて区別していないから。

曽山さん
へぇ…! 知らなかった!

柴田さん
おもしろいですね、それ。
蝶々と蛾の話で盛りあがる一同

麻野さん
日本食の味付けが繊細なのも、日本語が影響していると思います。
すなわち、使っている言葉の量や表現の豊かさは成果にあらわれるんです。だから語彙力が乏しい人は、5年10年経ったときにいい仕事ができなくなる可能性は高いですね。
読書に長い時間をかける時代は終わった。これからは「本×スキマ時間」の時代

柴田さん
僕、紙の本はバーっと流し読みして、本当にじっくり読みたいものはKindleで買うんですよね。「audiobook CAMP」も、本の内容をざっと頭に流すのに適していると思っていて。

曽山さん
そうですね。まずはオーディオから興味を持って、手元に置いておきたい内容だと思ったら買えばいいと思います。

柴田さん
今って欲しい情報は簡単にスマホで手に入るし、自分にとって有益になるかどうかわからないものに「しっかり時間をかける」のはとても難しい時代なんですよね。座学の研修に集中できないのも同じことなのかなと。
だからこそ、“有益な読書だけに集中できる環境”をつくってくれるオーディオ読書が必要だと感じています。

曽山さん
読者は長い時間をかけるものだったので、この変化はすごく大きいですね。これからは「本×スキマ時間」の時代です。

麻野さん
最後、2人ともめっちゃキレイにまとめましたね。仕事できすぎじゃないですか?(笑)
「本は浪費じゃなく投資」とはよく聞きますが、その本質は「言葉」にあったことを学べた今回の取材。
企業が読書のハードルを下げ、多読のきっかけになる「audiobook CAMP」を新人研修の一環として導入しておくことは、多くの人を動かすリーダーの育成につながりそうです。
〈取材・文=ほしゆき(@yknk_st)/編集=渡辺将基(@mw19830720)/撮影=三浦希衣子〉

ビジネスパーソンインタビュー
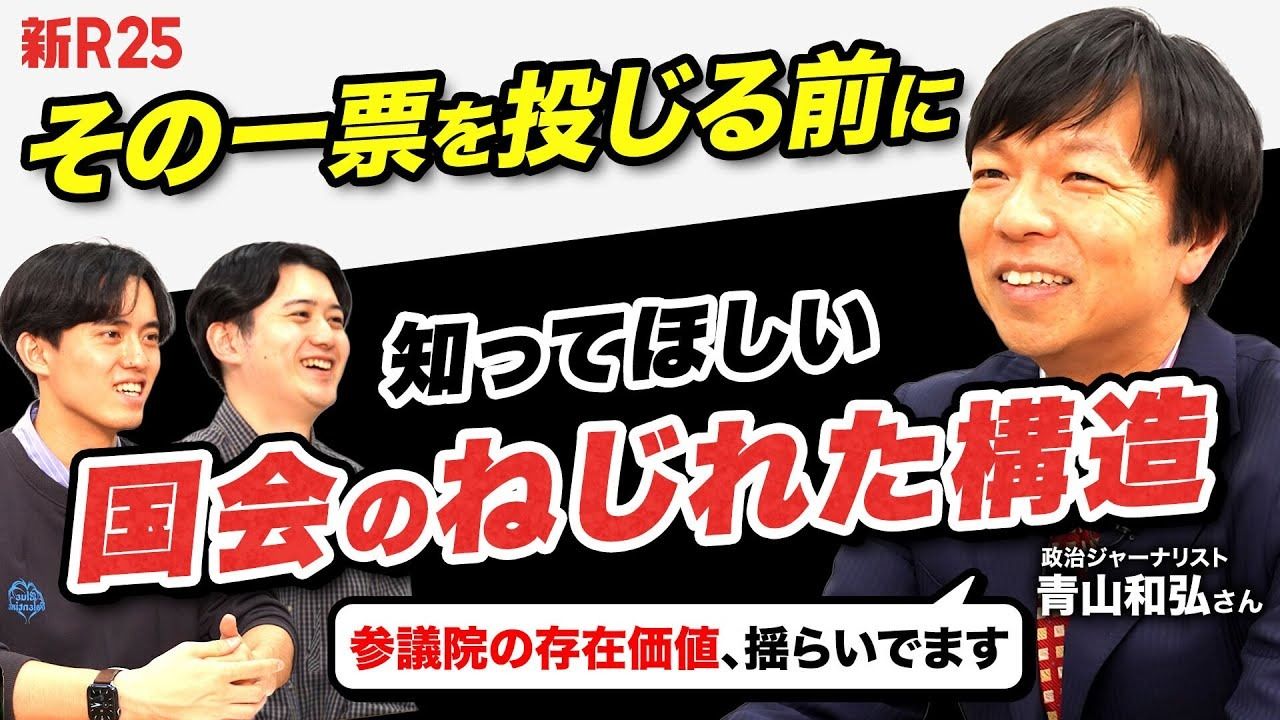
【参議院はAIに?】ダラダラ決められない国会なら、参議院を「革新の議会」に変える逆転の発想【Judge25 参議院必要?不要?】
新R25編集部
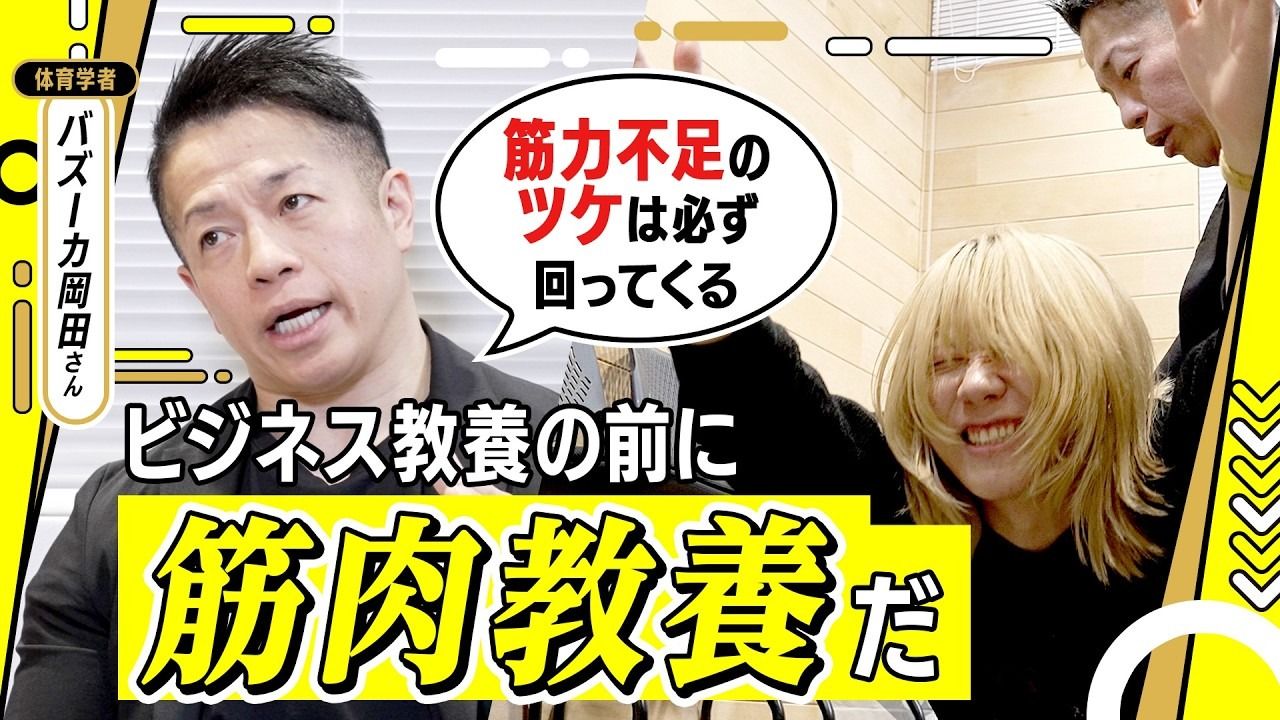
「ツケは必ず回ってくる」バズーカ岡田さんが岸谷蘭丸に説いた、「忙しいから」を理由に筋トレを一切しないことのリスク
新R25編集部
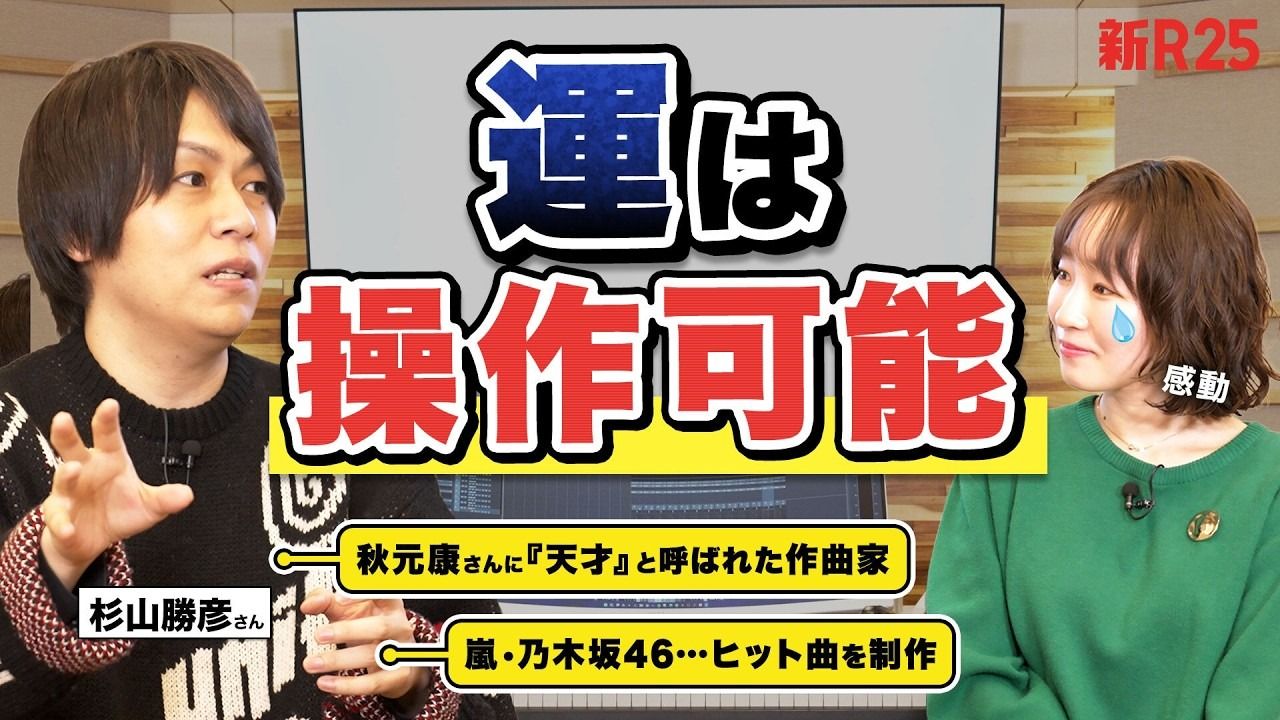
「実力はあるのに選ばれない人」の特徴は?秋元康さんに"天才"と呼ばれる作曲家の納得回答
新R25編集部
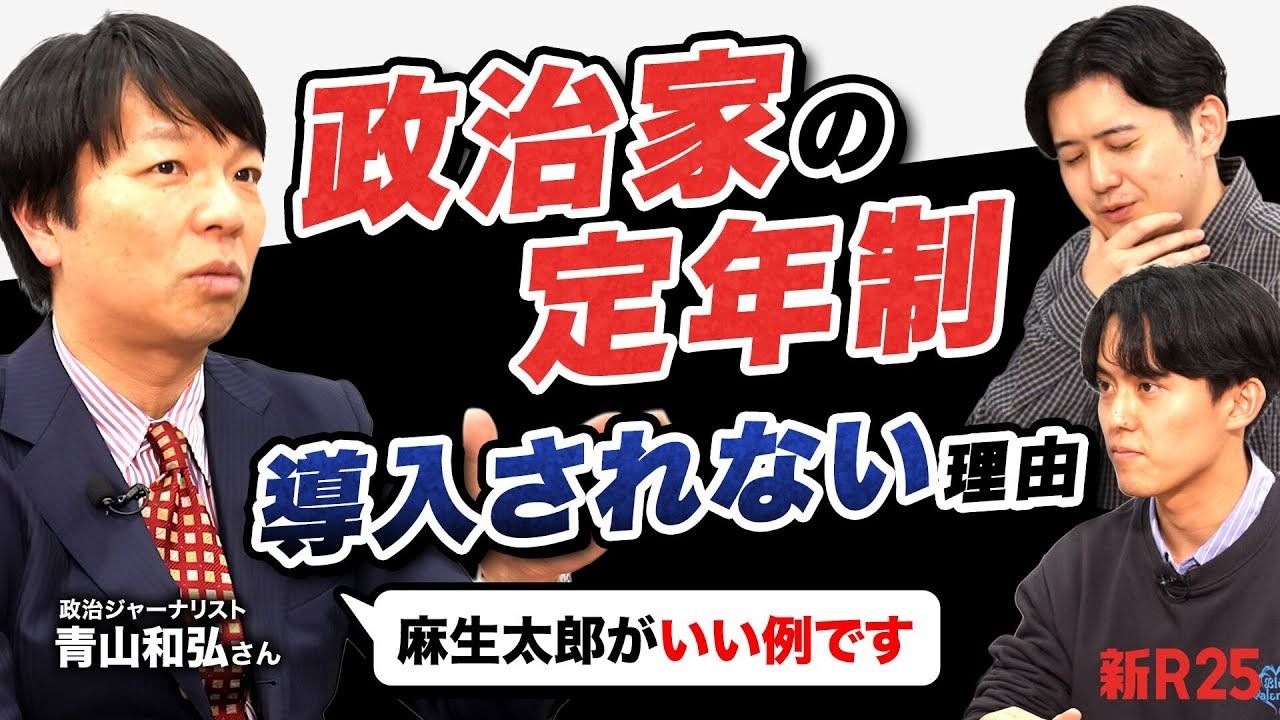
なぜ政治家だけ定年がない? "若手"52歳で社長を降りたCA藤田社長との「辞め時」の決定的違い【Judge25 政治家に定年は必要?】
新R25編集部
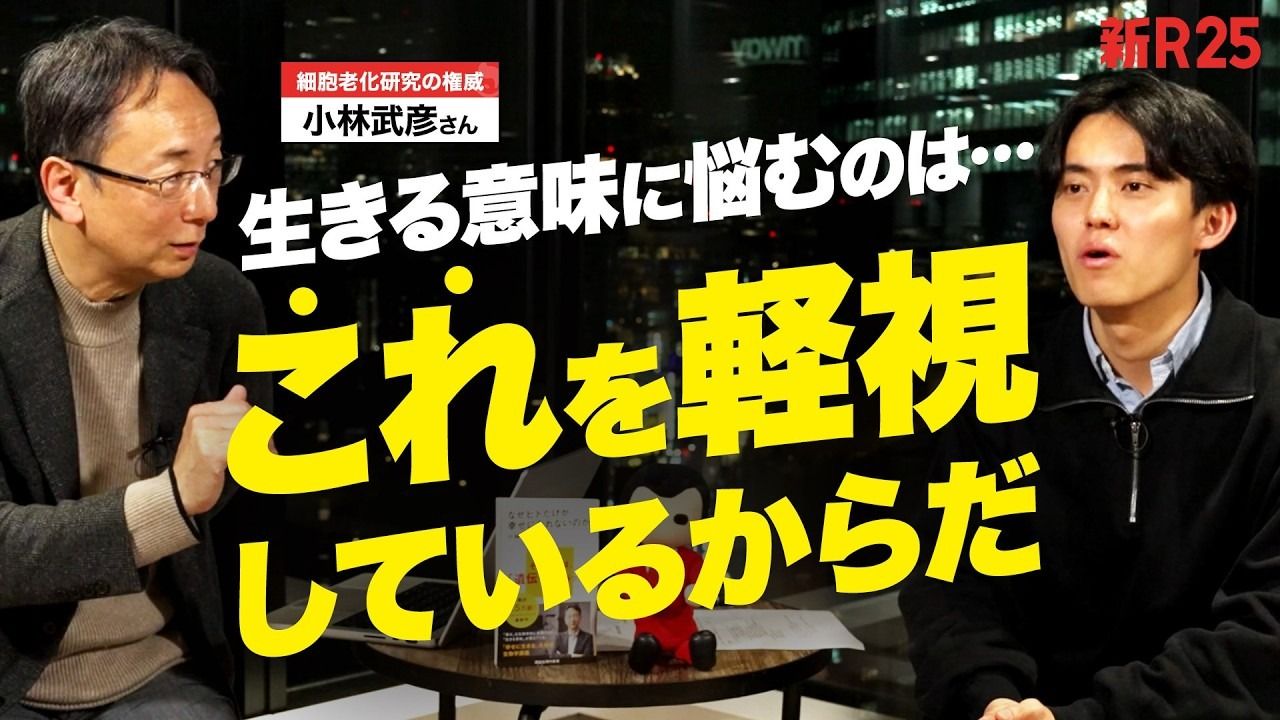
「意外と軽視されてるのが...」生物学者・小林武彦先生が教えてくれた、ヒトが生きる意味に悩む理由
新R25編集部
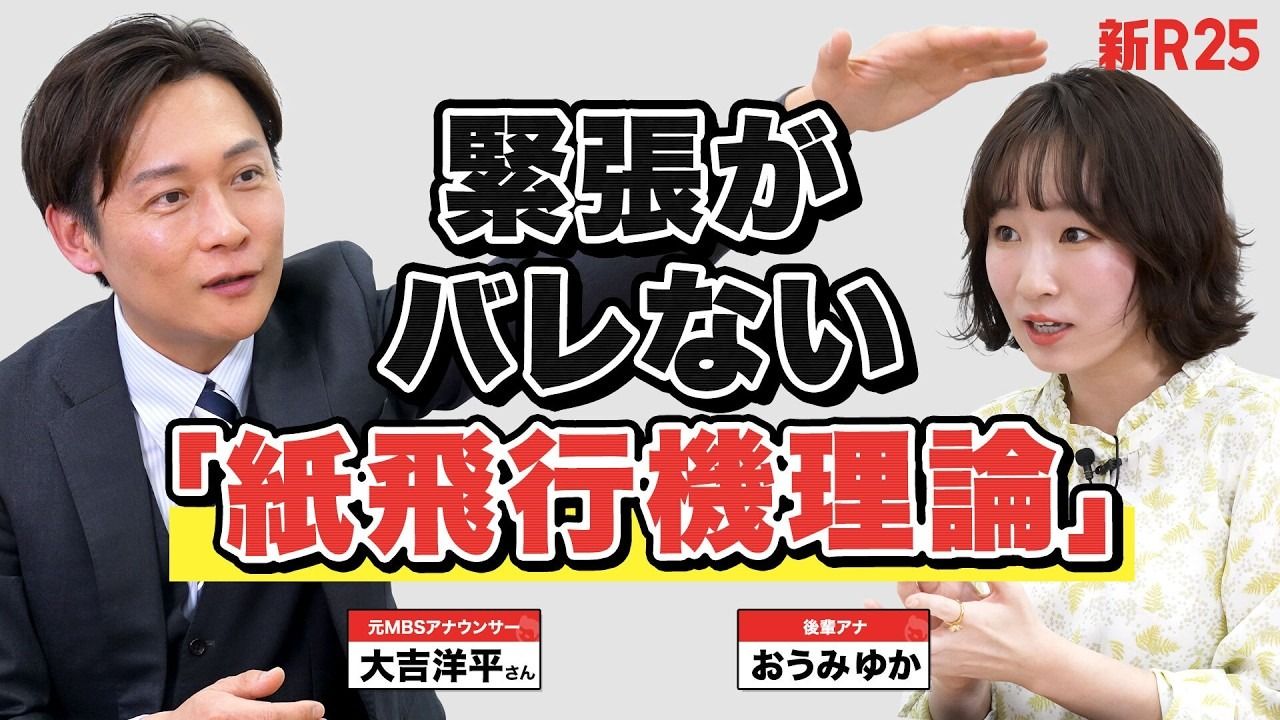
「緊張していい。堂々とビビれ」実況のプロが実践する、緊張がバレない"紙飛行機理論"
新R25編集部





















