 ビジネスパーソンインタビュー
ビジネスパーソンインタビュー
なぜ「お仕事しました報告」はカッコ悪く見える?
【コラム】目的と目標を明確にすれば、「お仕事しました報告」は「褒めてほしいアピール」にならない
新R25編集部
記事提供:サイボウズ式
サイボウズ式編集部より:チームワークや働き方に関するコラム「
ブロガーズ・コラム
」。はせおやさいさんのコラムです。
最近よく見かける「やりました」告知
最近、TwitterやFacebookでよく見かけるのが「お仕事しました!」という報告。
わたし自身も投稿してしまうのですが、「カッコ悪い」とネガティブに捉える人もいるようです。「わざわざ自分で言うものではない」という意見や、「自己満足ではないか」「単なる褒めて欲しいアピールではないか」…など、視点は様々。
たしかに、と感じるところもあるのですが、それでも自分がした仕事を知ってもらうためには、関わったことを周知していくのも必要なことだとも感じます。
では、なぜ「お仕事しました」報告をカッコ悪いと思ってしまうのでしょうか?
「カッコ悪い」と感じるとき、そこには「自意識」がある
わたし自身、自分がやった仕事を知ってほしい、こういうことができる人だと伝えたい、と思っていても、いざ投稿するとなると、どうもどこか座りの悪い、恥ずかしいような気がするときがあります。
「こんなこと投稿して、必死だな」と思われないだろうか、ダサい、痛いと思われていないだろうか…。葛藤しないことがない、とは言い切れません。
実際、自分がやった仕事を知ってほしい、と思うときの内心は必死ですし、より広く届いてほしいと思うときには何度も投稿してしまうことも。
実際その活動について「必死だな」「痛い」と思う人、思わない人、その両方がいることは確かでしょうし、もしかしたら好意的にとってくれている人のほうが多いかもしれません。
何より、それが自分の活動のプラスになるのであれば、堂々と告知すればいい。なのに、なぜカッコ悪いと思ってしまうのか。
「こんなふうに告知するって、ちょっとカッコ悪い」と感じるとき、そこには「自意識」があるのではないだろうかと思います。
わたしのように見せるのが恥ずかしい、カッコ悪いと思う人は、第三者から自分がどう見られるかについての自意識が強いのかもしれませんし、逆に平気な人は、そのぶん自意識から自由になれているのかな、と思います。
個人の美意識は他人に押し付けるものではない
これは、どちらが良い悪いではなく、個人の美学の話です。
自分のやった仕事を知ってもらうためなら「必死だな」と笑われてもいい、と割り切れる人もいれば、努力をアピールするのはカッコ悪い、いいものを作れたと思えばあとは周りが評価してくれるのを待つ、と思う人もいるかと思います。
「鴨の水掻き」(《気楽そうに浮かんでいる鴨も、水面下では水かきを絶えず動かしているところから》人知れない苦労があることのたとえ。ー出典:デジタル大辞林)ということわざもあるように、「苦労は人に見せるものではない」と思う美学もあるでしょう。
個人的には「自分の美学に反しない」限りはどんな報告をしてもいいのではと思っています。
「俺はやりましたアピールをしないよ」があってもいいし、「頑張ったので見てほしいよ!」があってもいい。あえて努力を隠し、涼し気な顔で頑張るほうが粋だ、評価は周りがするもので自分から言うものではない、という考え方もわかります。
もしかしたら世代的なもの、派手な自己アピールをよしとしない周囲の環境もあるかもしれません。
とはいえ、本人が自分で考えて出した結論にもとづく言動であり、美意識に則ったものであるならば、どちらも他者がわざわざ否定するものではないのではないかと思います。
自分をひとつの会社だと思ったとき、告知は「広報活動」
では「やりました!」アピールをどんなふうに捉えればいいのか。
わたしは個として自立するために、自分がやった仕事をアピールするのは、会社でいう「広報活動」的なものだと考えています。会社でも何か新しい製品をリリースすればPRを行いますし、そうでない、普段の楽しい風景を見せて、会社について紹介しているところもありますよね。
「いい仕事、いい活動をしていれば、おのずと周りは見ていてくれる」も事実かもしれませんが、黙っていたら誰も気づいてくれないのも、また事実。
ごくごく小さいベンチャーにいた頃、広報業務も兼任していたことがあるのですが、広報活動の重要なところは「こんなことできます」のアピールだけではない、と教わったことがありました。
小さいベンチャーにおいてはちょっとプレスリリースが途絶えただけで「最近見かけないけど、潰れたのかな?」と思われがちなので、「今もまだ活動してますよ!なくなってないですよ!」と知ってもらうことも目的のひとつなのだと。
個人を小さなベンチャー企業だと置き換えたとき、この考え方が当てはめられるのではないかと思います。やったこと、やりたいことをアピールしていかないと、周りは気づいてくれないし、気づいてもらえないと、「あれ、もうやめちゃったのかな」と思われかねません。
まだまだ複業可能な会社は少ないですが、会社でやった仕事に限らず、こんなことに興味がある!こんなことを手伝った!を周りに伝えていくことは個人のブランディングにとっても大切だと思うのです。
単なる「褒めてほしいアピール」にならないために
では、単なる「褒めてほしいアピール」をする構ってちゃん、にならないために、どう自戒していけばいいのか。
ここは、「アピールする目的と目標」を決めるべきではないかと思っています。
関わった仕事について告知の投稿をすることで、たとえば「自分がどんなことができる人間か知ってほしい」を目的とし、知ってもらった上で「お仕事の受注」を目標とする。もしくは、「自分がやっている活動をアピールする」ことを目的として、「賛同者を募る」のを目標とする。これも、会社の広報活動と一緒ですよね。
自分がこれを報告することでどんな効果が起きて欲しいのか、どんな仕事につなげたいのかをイメージしてみる、というのは大切だと思います。
個人的には、目的と目標がはっきりしている人ほど、「やりました」アピールに迷いがないし、「痛い」と言われてもさほど気にしていないように思えます。それはアピールは単なる手段であって、ちゃんと目的と目標があるからなのでしょうね。
もちろん「褒めてほしい」という欲求そのものは否定されるものではないけれど、それはそれ。自分の中で目的と目標、手段を明確に整理することで上手にSNSと付き合い、自分という「個」のブランディングに役立てていけるといいのではないかなと思っています。
〈文=はせ おやさい/イラスト=マツナガエイコ〉
本記事の提供元はこちら

ビジネスパーソンインタビュー
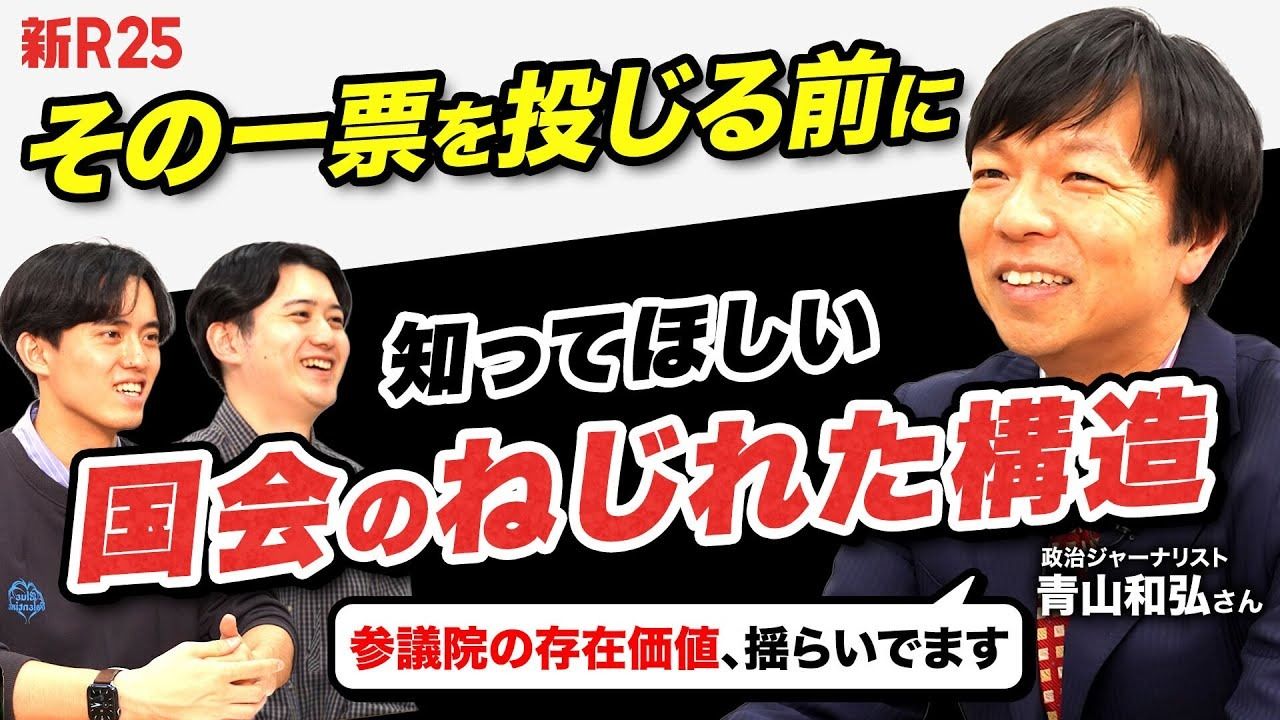
【参議院はAIに?】ダラダラ決められない国会なら、参議院を「革新の議会」に変える逆転の発想【Judge25 参議院必要?不要?】
新R25編集部
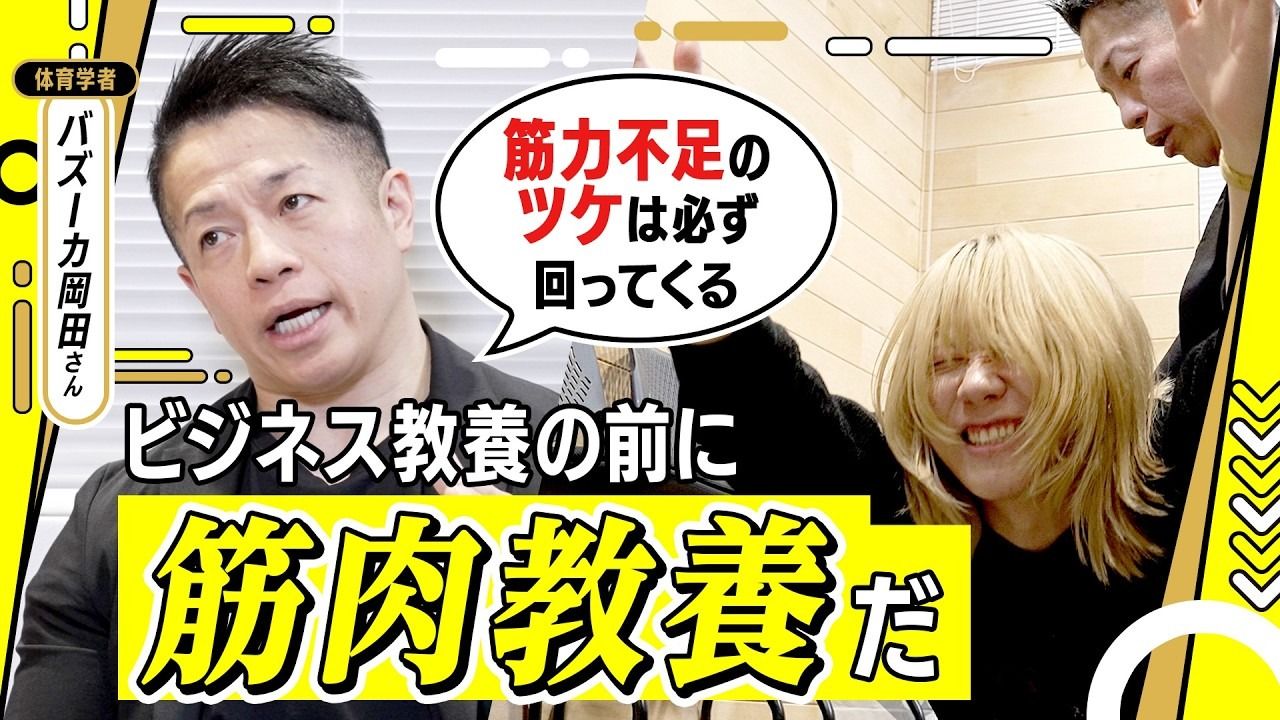
「ツケは必ず回ってくる」バズーカ岡田さんが岸谷蘭丸に説いた、「忙しいから」を理由に筋トレを一切しないことのリスク
新R25編集部
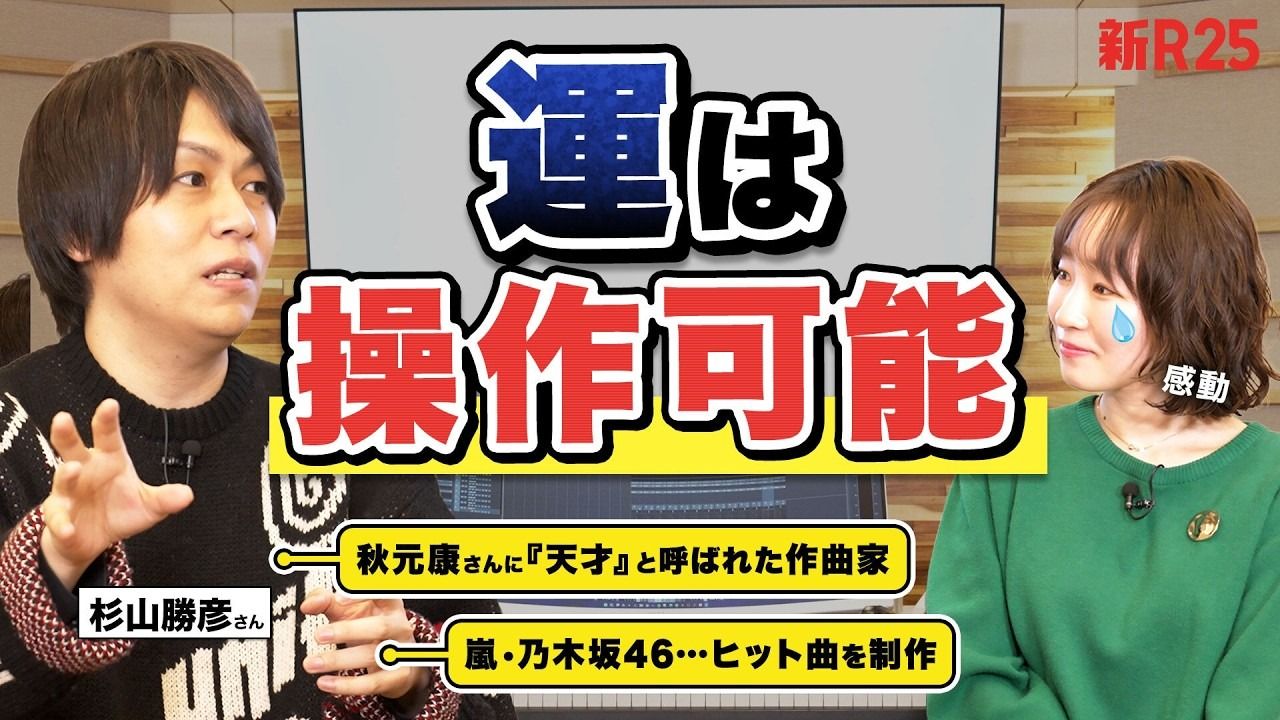
「実力はあるのに選ばれない人」の特徴は?秋元康さんに"天才"と呼ばれる作曲家の納得回答
新R25編集部
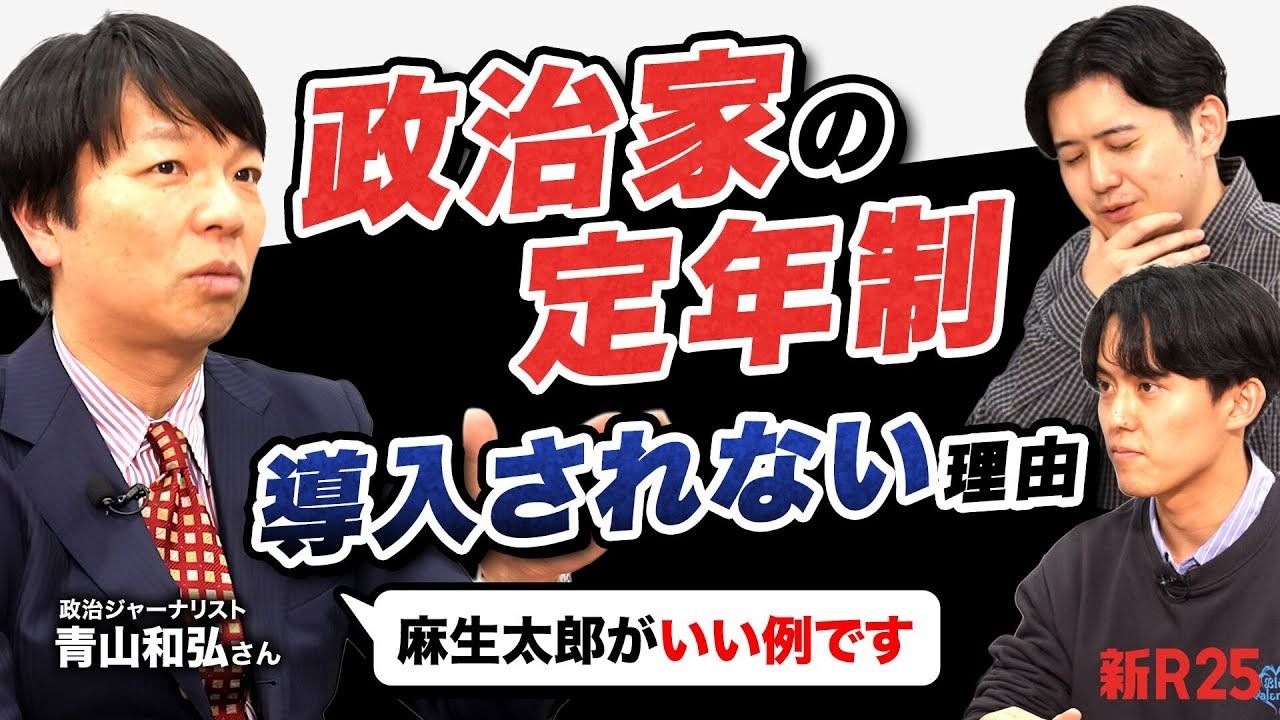
なぜ政治家だけ定年がない? "若手"52歳で社長を降りたCA藤田社長との「辞め時」の決定的違い【Judge25 政治家に定年は必要?】
新R25編集部
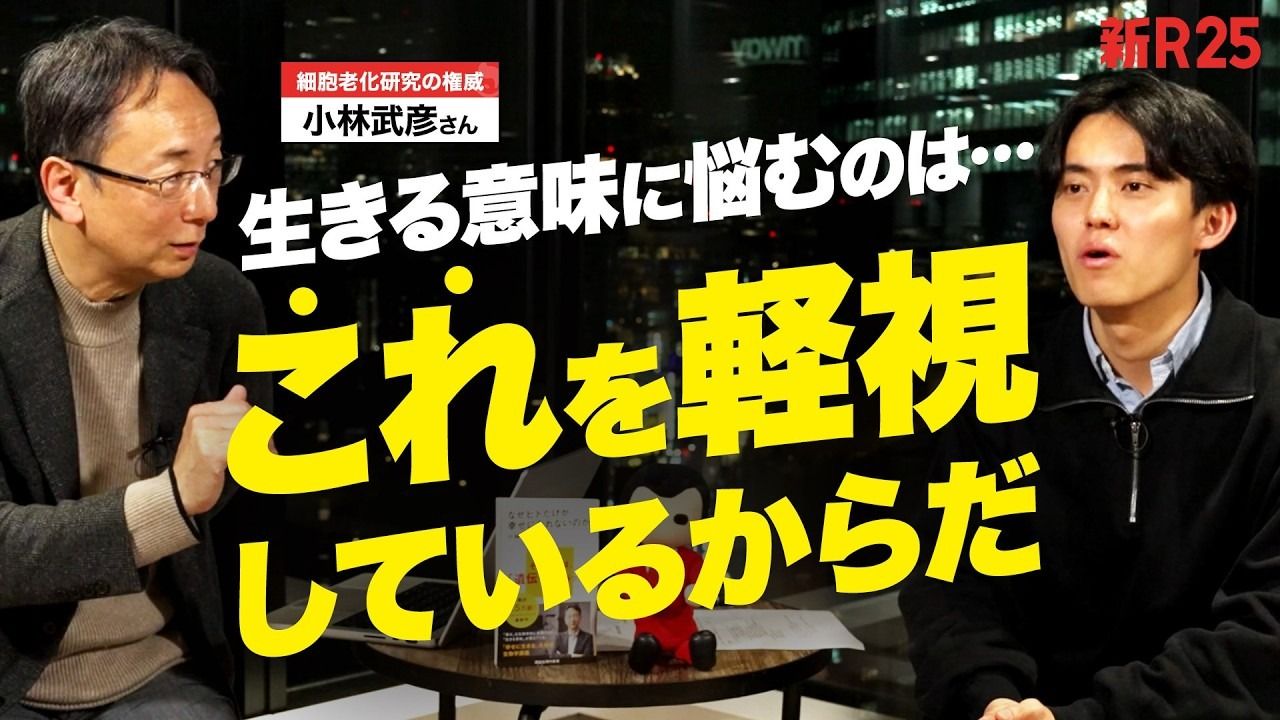
「意外と軽視されてるのが...」生物学者・小林武彦先生が教えてくれた、ヒトが生きる意味に悩む理由
新R25編集部
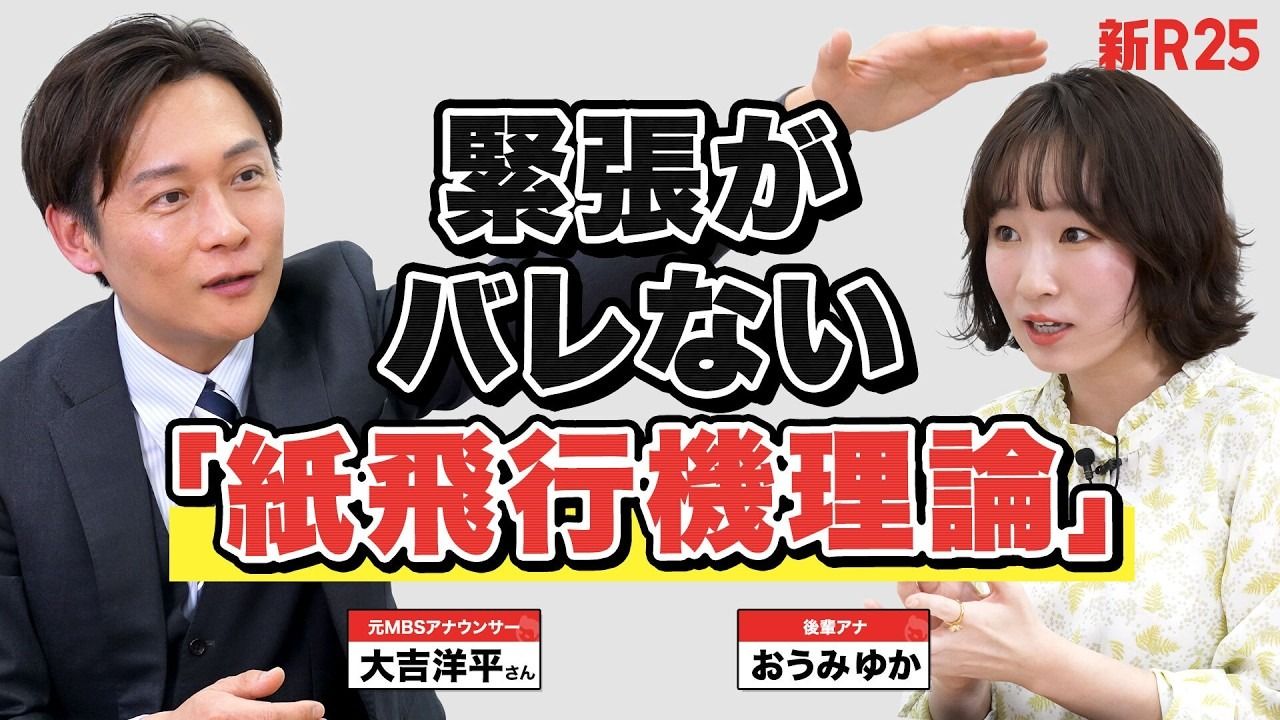
「緊張していい。堂々とビビれ」実況のプロが実践する、緊張がバレない"紙飛行機理論"
新R25編集部



