 ビジネスパーソンインタビュー
ビジネスパーソンインタビュー
日本を代表するクリエイターの“失敗”とは?
佐藤可士和が空回りしていた3年間。ブレイクスルーのきっかけは「ロールモデル」
新R25編集部
各業界の第一線で活躍するあの人にも、乗り越えられなかった“失敗”や、いまだに引きずっている“挫折”がある。本連載では、そんなR25世代が憧れる先輩たちの知られざる過去をフカボリする。
24歳で広告代理店・博報堂に入社し、関西支社にいきなり配属。多摩美術大学を卒業し、広告のアートディレクターになるためにやる気満々で入社した佐藤可士和さんにとって、それは思いも寄らない事態だった。
新人ながら100万円以上のMacを購入して意気込むも…“誰もわかってくれない”日々
「日本の広告の中心はやはり東京です。大きなクライアントのメジャーキャンペーンのような仕事は東京に集まるので、大阪だと単純にチャンスが減る。それに僕は東京生まれの東京育ちなので、『なぜ自分が大阪に?』と。だからすごくポツーンとなっちゃって」
だが、そんなことも言っていられない。目指すべき目標があるのだ。入ってすぐに、新しい表現技法を求めて高価なMacを自腹で購入。当時は100万円以上する高級品だ。今でこそデジタル作業でクリエイティブを制作するのは当たり前だが、1989年当時にそんなことをやっているクリエイターはほとんどいなかったらしい。
「博報堂でパソコンを使ってポスターを作ったのは、僕が初めてでした。その仕事が社内の作品検討会で大阪の代表に選ばれたんです。『関西支社新人の佐藤くんがコンピュータで作ったものらしいです。フロッピー入稿で』というような感じで検討会にかけられましたが、『?』といった反応でしたね」
「わかってもらえない」のであれば、広告的には“よくないクリエイティブ”だったのだろう。周囲に友人のいない環境を逆手にとって、がむしゃらに仕事に取り組んだ佐藤さんだが、当時は今のようにヒット作連発というわけにはいかなかったのだ。
「パーンと当たるものもあれば、三振もするんです。その違いや理由が、当時はわかりませんでした。クライアントの商品に、僕が新たなイメージを付与することが広告のクリエイティブだと思っていた。新しい何かを見つけてあげなきゃ!と焦っていたんです」
「イメージは足すのではなく、引き出すもの」憧れの先輩から学んだ仕事が伝説的な広告に
関西支社にいた3年間は、やる気が空回りした3年間だった。だが東京の本社に戻って、過ちとその理由に気づくことになる。
「もともと博報堂には、大貫卓也さん(日清食品「hungry?」などで知られる伝説的クリエイティブディレクター)に憧れて入社したんです。僕が東京に戻ったときは、大貫さんがちょうど独立されたタイミング。大貫さんが参加する大きなコンペがあって、若いアートディレクターが必要ということを聞いたので、『やります!』と立候補しました」
必死に大貫さんの仕事に食らいついた。2~3本一緒に仕事をし、転機となる仕事に出会う。1997年。ホンダの新型ミニバン・ステップワゴンの発売キャンペーンだ。
「大貫さんや(同案件を一緒に手がけた)鈴木聡さんというコピーライターの方から学んだのが、『イメージは付加するのではなく、相手から引き出すものなんだ』ということです。企業の本質を見つめ直して、本来の姿を引き出す。自分が何をやりたいかではなく、相手のやりたいことを見いだす。つまり、それまで僕が考えていたことと逆だった。そんなアプローチで取り組んだこのキャンペーンは、とてもうまくいきました」
うまくいったどころではなく、伝説的なクリエイティブになった。「こどもといっしょにどこいこう。」というキャッチコピーと、佐藤さん自身が描いたイラストレーションを用いた絵本の中に飛びこんだようなビジュアルは、クルマのあるライフスタイルを消費者に喚起させるみごとなコミュニケーションだった。“機能訴求”一辺倒だった自動車広告の価値観を一変させ、ステップワゴンはミニバン市場で1位を獲得した。
「話題の広告を作りたいし、クライアントに喜んでもらいたいし、賞ももらってデザイン的に評価されたいとずっと願っていましたが、鈴木さんたちと延々と話し合って本質に向き合い考えに考えたら、想像だにしていなかった新しい表現ができました。広告としても評価され、ずっとほしかったADC賞もいただき、クルマも売れて8年間もキャンペーンが続いたんです」
佐藤さんは、そこに至るまでのすべてを「ムダではなかった」と振り返る。
「方法論がわかっていなかったんですよ。どんなつまづきも、ムダではありません。結論に至るまでの過程です。僕の場合、解法は足し算でなければ、引き算でもなく、『答えは相手の中にある』と理解できたんです」
裏を返せば、失敗など捉え方ひとつなのだ。
「先日、桐生(祥秀)くんが日本人初の100m走9秒台という素晴しい記録を出しましたよね。そして9秒台を目指す過程で走ってきた10秒台のタイムは、9秒台を出すことに失敗したという捉え方には絶対になりませんよね」
成果が出ないことは誰にでもある。それを失敗だと捉えるのは時期尚早だ。仕事を重ねれば自ずと成果が出るようになっていく。
「長いスパンで見ないと、成否はわからないと思うんです。とはいえ毎回プロジェクトの目標はありますから、そこに対しての結果は真摯に受け止めるべきですが」
圧倒的に尊敬できる先輩に言われてようやく目が覚めた。ロールモデルは誰でも見つかる
だが、若かりし日の佐藤さんのように、「自分には、ほかの大人にはないセンスがある」と思い込んで意気揚々と会社に入っても、思うようにいかず何年も雌伏のときを過ごすケースは多い。あるいはそんなに自信を持たずに入社したとしても、そこから“自分の型”を見つけるのは容易なことではない。
「参考になるかはわからないですが、僕の場合は圧倒的な先輩たちに教わったことが大きいと思います。たとえば一緒にブレストしても、全然アイデアのレベルが違うし、口出しもできない。日本中がビックリする作品をたくさん作っているような、視点もデザインも、すべての面で尊敬できる先輩から『そうじゃないよ』と言われて、ようやく目が覚めた感じですね」
しかし、生き方も仕事も多様性に溢れた昨今は、ロールモデル不在の時代だとも言われている。目指すべき人はおろか、参考にすべきワークプランやライフプランも見つからない。そんな暗中模索の若手ビジネスマンは、いかに成長の指針を見いだすべきか。
「ロールモデルがない人は、『どうなりたいのか』が自分のなかで明確になっていない可能性があります。自分が成功するイメージや、こういう仕事がしたいとか、こういうことをやって認められたいというイメージがあれば、お手本になる人やチームは、きっとあるでしょう。まずは自分でどうなりたいか、どうしたいのかのイメージを持つことが優先で、そうすれば、目指すべきあり方は自ずと見つかると思います。僕はそう信じています」
<取材・文=吉州正行/撮影=林和也>
【佐藤可士和(さとう・かしわ)】
1965年東京都生まれ。多摩美大卒業後、博報堂入社。ホンダ「ステップワゴン」でADC賞受賞。2000年独立し、同年にクリエイティブスタジオ・SAMURAIを立ち上げる。国立新美術館や、ユニクロ、楽天グループ、セブン-イレブンジャパン、今治タオルのロゴデザインやブランドクリエイティブディレクションのほか、「カップヌードルミュージアム」「ふじようちえん」のトータルプロデュースなど、様々な領域においてデザインの力で新しい価値を提示するプロジェクトを手がける。有田焼創業400年事業「ARITA 400project」で作品を発表するなど、アートの分野でも活躍中。

ビジネスパーソンインタビュー

【NSC伝説のお笑い講師】本多正識さんが語る「面白くなる人」の共通点。“引き出しを増やす”一番簡単な方法とは?
新R25編集部
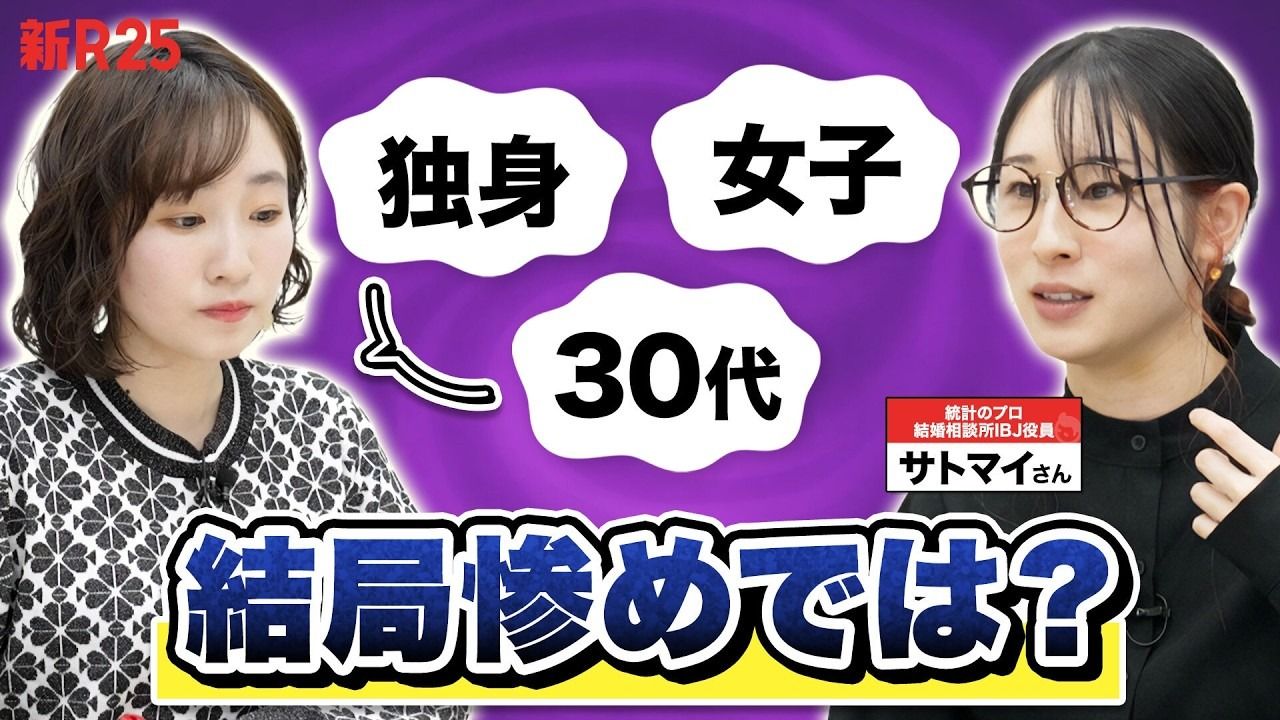
「30歳超えてまだ未婚?」冷ややかな視線に惑わされず“自己決定”する方法を、統計のプロが伝授
新R25編集部

「嫌われたくない」のは自分勝手?自分らしく話すための"嫌われる怖さ"の乗りこなしかた
新R25編集部

【女性は損か】成果を出すと嫌われる?育児でキャリアが止まる?男社会で勝ち続ける柴田陽子さんの一撃回答
新R25編集部

【ミエルTV】テレビCMはどこまで“見える化”できる? 3社が見据える「テレビCM運用」の超進化【AJA×ソニーマーケティング×日本テレビ(後編)】
新R25編集部
Sponsored

「病むくらいならコムドットを辞めてもいい。」それでも、やまとさんが"本気"の挑戦をし続ける理由
新R25編集部








