 ビジネスパーソンインタビュー
ビジネスパーソンインタビュー
リーダーになる人は「反脆く」あれ
「論理の鬼」が目指すはエモい組織!? ミラティブCEOが語る、組織に“わかりあい”が必要なワケ
新R25編集部
プレイヤーとしてある程度の成果を出せるようになったら、今度はリーダーになってチームを導く立場になります。
ただ、自分ひとりの成果の出し方と、メンバーを率いての成果の出し方はまったく別物。そのギャップに悩むリーダーも多いはず。
そんな悩みを解決するヒントになる組織があります。それは、赤川隼一さんが代表取締役を務める株式会社ミラティブ。
赤川さんは、元DeNAの最年少執行役員であり、「Yahoo! モバゲー」やDeNAの韓国支社を立ち上げた超優秀なビジネスマン。
起業家のけんすうさんは、赤川さんのことを「論理の鬼」「ギラギラに尖りきったすごい起業家」と評価しています。
そんな「論理の鬼」とも呼ばれる赤川さんが導き出したマネジメントの答えはなんと「エモ」。
チームを最大限に成長させるには、”感情”を意識しないといけないそうです。
赤川さんが自身の経験から導き出した「エモ」とマネジメントの相関性。ぜひご覧ください!
〈聞き手=福田啄也(新R25編集部)〉
【赤川隼一(あかがわ・じゅんいち)】1983年生まれ。広島県出身。2006年、新卒で株式会社ディー・エヌ・エーに入社。広告営業やマーケティングに携わった後、「Yahoo!モバゲー」を立ちあげ。その後、執行役員として海外事業の統括やゲーム開発に携わる。2018年2月、株式会社エモモ(現 ミラティブ)を創業
メンバーが「どんなことで感情が動くのか?」が鍵になる

福田
赤川さんのインタビュー記事などを拝見していると、「エモい経営」「エモい会社」という言葉が多く出てきます。
正直、ピンとこないのですが…どういう意味ですか?

赤川さん
仕事を通じて自分たちも心が動かされるような会社にしたい、ということで、状態としてはメンバーが自分のなかに秘めている感情を共有できている会社を目指しています。
ミラティブでは毎月一回、「プレミアムエモイデー」という日がありまして…
何ですかそれ

赤川さん
これは毎月、僕から事業の状況を共有する全体会議なのですが、本編の開始の前にメンバー全員が「最近あったエモい話」をするんですよ。
たとえば「最近○○さんに言われたことで結構マジで感動した」とか、“自分の感情が動いた話”を共有するんです。

福田
へええ!
ちなみに、赤川さんの最近の「エモい話」ってなんですか?

赤川さん
先日テレビに出していただいたんですけど、それを見ていた高校時代の先生からメールがあって。
その先生から「お前が年上の奥さんを見つけたことが嬉しくて、職員室でひとりでガッツポーズした」って言われました。
やばい、なんてコメントすればいいのかわからない

赤川さん
しょうもないですよね?
ただ、こんな「しょうもないけど心が動かされた話」でも、開示する場があることが大事なんです。
社長がしょうもない話をすることで、メンバーも最近気づいたことや些細なことも話してくれるようになる。
このプレミアムエモイデーでは、「あー、この人はこんなことが好きなんだ」とか「こんなことを大事にしているんだ」というのをお互い「なんとなく知る」ことが大事なんです。

福田
なるほど。ただ、それがマネジメントにどう生きるのでしょうか?
いまいちピンとこなくて…

赤川さん
マネジメントをすることにおいて、個人の感情を知ることは、組織を成長させるカギになるんです。
そのためには、僕の黒歴史からお話しましょう。
なんだなんだ
入社して半年で最年少マネージャーに昇格するも…

赤川さん
新卒でDeNAに入社したとき、携帯電話専用アフィリエイトサービス「ポケットアフィリエイト」(2013年サービス終了)の営業に配属されました。
その部署ですぐに成果を上げて、半年で最年少のマネージャーに就任したんです。

福田
赤川さんが入社した2006年のDeNAは、「モバゲータウン」がローンチされてすぐに成長している時期ですよね。
入社1年目でリーダーになれるなんてめちゃくちゃ優秀だな…

赤川さん
マネージャーになったとき、「入社半年くらいの僕が目標達成ができるんだから、普通にちゃんとやればチームメンバーも同じように目標達成できるっしょ」と思ってました。
だから、営業目標を達成できないメンバーに対しては「何で売れないんですか?(笑)」って、みんなの前で平気で言ってたんですよね。
新卒にそんなこと言われたら泣く

赤川さん
結局、メンバーの目標は毎月未達で、僕個人の売上でなんとかチームの目標を達成しているような状況でした。

福田
当時のメンバーの雰囲気はどうだったんですか?

赤川さん
たぶん最悪でした(笑)。僕の上司にも、チームメンバーからの愚痴が届いていたんでしょうね。
ある日呼び出されて、「チーム全員が目標を達成しないと、お前個人がいくら売ってても評価しないから」って厳しく言われました。
そこで初めてマネージャーとして、自分のやり方を考えるようになったんです。
本心を開示することで、初めて目標に向き合えた

赤川さん
僕がリーダーとして意識したのはDeNAの南場さん(創業者・現会長)でした。
南場さんってマッキンゼー出身なんで、ロジカルな思考がすごい人だと思われてる気がするんですが、南場さんの一番のすごさは「人をエモーションで動かす魔力」なんですよ。
ロジカルで力強い決断を下すけど、それを社員に話すときには「みんなが共感できる言葉」を使うんです。
DeNAで問題があり、南場さんが全社でスピーチをしたときには涙する社員もいたんだとか

赤川さん
僕自身もメンバーの感情を積極的に意識するように変えました。
メンバーに対して、「僕、チーム全員で達成したいんです。全員で達成したほうが気持ちいいじゃないですか!」と本心を暑苦しくちゃんと伝えたり、1on1では「〇〇さんは人生で何がしたいんですか?」「〇〇さんにとって仕事って何ですか?」って青臭い質問を投げかけたり。

福田
ただ仕事をしているだけではあまりしない会話ですね。

赤川さん
まだ新卒1年目っぽい不器用さがありましたけどね(笑)。
そういうメンバーの本心を聞いたうえで、初めてメンバーがどうやって目標達成するのか、という話に向き合うことができる。
それまでの僕は「自分ができるから、みんなもできるでしょ」って勝手に思い込んでメンバーを理解しようともしてなかったんです。
お互いに本心をわかりあえたことで、当時のメンバーは今会っても「たぶんDeNA史上最強の営業チームだったよねー」と思い出話ができるような誇れるチームになりました。
“わかりあう”マネジメントのメリット①「心理的安全性」が組織にあると安心

福田
「メンバーとわかりあえたことで成果があがった」…正直、ちょっとキレイごとのようにも感じますが…

赤川さん
まあ、そう思うでしょうね。
すみません…!

赤川さん
わかりあいを意識した組織には「心理的安全性」が担保されるんです。
この心理的安全性があると、会社組織だけじゃなく、コミュニティの会話など、何でも活発になるんですよ。
僕らの運営している、スマホ特化型ライブ配信サービス「Mirrativ」は、スマホゲーム配信者数が日本一(同社調べ)なんです。
それって何でだと思います?

福田
うーん…スマホさえあれば誰でも配信できる点ですかね?

赤川さん
ちがいます。
Mirrativでは、あらゆる点で「素人が配信するための心理的ハードルを下げる」ということを意識しているんです。
「ライブ配信する」って、まだまだ普通の人にとってハードル高いですよね。
だからこそ、サービスを触っていて「あ、これなら私でもやれるかも」って思ってもらえることをとにかく大事にした結果、配信者さんの数がすごく多くなりました。
たとえばアバター機能「エモモ」は、顔出しせずに配信できることを可能にしました。

赤川さん
ライブ配信してみたいけど、自分の容姿に自信がない方も多い。
でも、「自分の顔を出さずに配信ができる」という点が、その心理的ハードルを突破しました。「エモモ」をローンチした2018年は、配信者数は前年の10倍超に激増したんですよ。

赤川さん
会社組織もこれと同じで、プレミアムエモイデーのおかげもあって、組織内で「どんな話をしてもいいんだ」という心理的安全性が担保されると、メンバーは積極的に発言してくれるようになります。
正直、社長は現場から遠いのでトンチンカンなことを言うこともあると自覚しているので、現場を一番わかっている人が「ここはこうするべきだ」って発言してくれることが、組織の成長を加速させると思うんですよね。
“わかりあう”マネジメントのメリット②「メンバーの仕事への納得感が生まれる」

赤川さん
あと、今の時代はむしろメンバーの感情をちゃんと認識しないと、マネジメントが難しいんですよね。
個人側のパワーがとても大きくなっているので、給与や待遇だけでは組織に結びつけることができないんです。
優秀な人は、いつでも行きたい会社に転職できてしまいますから。

福田
「個の時代」を象徴するようなお話ですね。

赤川さん
「自分の感情が動く瞬間」とミラティブの仕事で輝く瞬間が一致することで、「その会社にいる意味」ができる。
「自分はこれをやりたくてやっている」という納得感が持てないと、人は動けないんですよ。
だから我々はミラティブに興味を持ってくれている人のために、「採用候補者様への手紙」などを発信して、とにかく「ミスマッチ」がないように注意しています。
ミラティブが公開しているスライド。ミラティブの働き方や待遇、組織構造などが丁寧に解説されています

赤川さん
そして人間性を含めてわかりあえているメンバーとだったら、「この人が言うなら仕方ない」という「論理を超えた信頼」も築けると思っていて。
なぜミラティブメンバーが、誰にも正解がわからない意思決定のときに僕の考えを聞いてくれるのかというと、ロジックの納得感はもちろんですが、「まぁしょうがねえなぁ」も含めた想いへの納得感がある、というのは大きいんじゃないですかね。

福田
それはめちゃくちゃわかる…全然わかってくれてない上司に言われても「なんでこの人のタメにやらないといけないんだ」っていう気持ちになります。

赤川さん
実はそういう「しょうがねえなあ」と思える人がトップにいないと、組織が維持できないんじゃないかなって思っています。
メンバー自身が「個人」として生きていくように、リーダーもまた「個人」として理解されて選ばれる存在にならないと。
リーダーになる人は「反脆く」あれ

福田
赤川さんのように、メンバーから「しょうがねえなあ」と思われるリーダーになるにはどうすればいいのでしょうか…?

赤川さん
ひとつは、積極的に自己開示をしていくことですかね。
そして、もうひとつは「反脆弱性」があることが大事だと思います。

福田
??

赤川さん
『ブラック・スワン』の著者であるタレブが2017年に書いた『反脆弱性』という本に影響を受けているんですけど…
世の中のことはだいたい3つの種類に分けられるんです。
「硬いもの」「脆いもの」、そして「反脆いもの」だと。
「硬いもの」は衝撃を受けても変わらないもの。逆に崩れてしまうのが「脆いもの」。
でも、世の中で長くつづいているものは、実は「硬いもの」ではなくて、衝撃を受けるとそれを逆に糧にして立ち直れる「反脆いもの」だと言っています。

赤川さん
たとえば、ワクチンって体にウイルスを入れると耐性ができる、という仕組みじゃないですか。
あえて、衝撃を受けたことで強くなれるのが「反脆弱性」で、世の中で長く続いているものにはだいたいこういう「衝撃や変化への強さ」があるんですよ。
シリコンバレーには「失敗を奨励する文化」があるんですが、それは「反脆くあれ」ってこと。
逆にウォール街の銀行システムは脆いもの、と本書では表現されていて、実際にリーマン・ショックのときに大きく崩れてしまいましたよね。

福田
ふむふむ。

赤川さん
リーダーは積極的に失敗して、それを糧にしてきた経験が必要なんです。
そうすればプレイヤーとしても成長できるし、「あの人は何度も失敗して、立ち直った経験があるから強い」と信頼されるんです。「最後はなんとかいい形に着地させるだろう」と思われるというか。
僕がリーダーとして誇れることは、とにかくたくさん失敗してきたこと。
だからミラティブでもリスクを抑えて「小さく早く失敗すること」を大事にしているし、失敗の数だけ組織としてもこれからも成長することができると確信しています。
メンバーのことを理解しようと努力するリーダーは多いでしょう。
ただ一方で、“メンバーに自分のことを理解してもらおう”としている人は少ないのではないでしょうか?(というか自分もそうだな…)
赤川さんはインタビューで「これは黒歴史なんですけど…」と言って、積極的に「自己開示」をしてくれていました。そのおかげかたった1時間のなかでも、僕は赤川さんとわかりあえた気がします。
もしあなたが会社で業務以外の話を避けているとしたら…さっそく「最近あったエモい話」から始めてみましょう!

ビジネスパーソンインタビュー
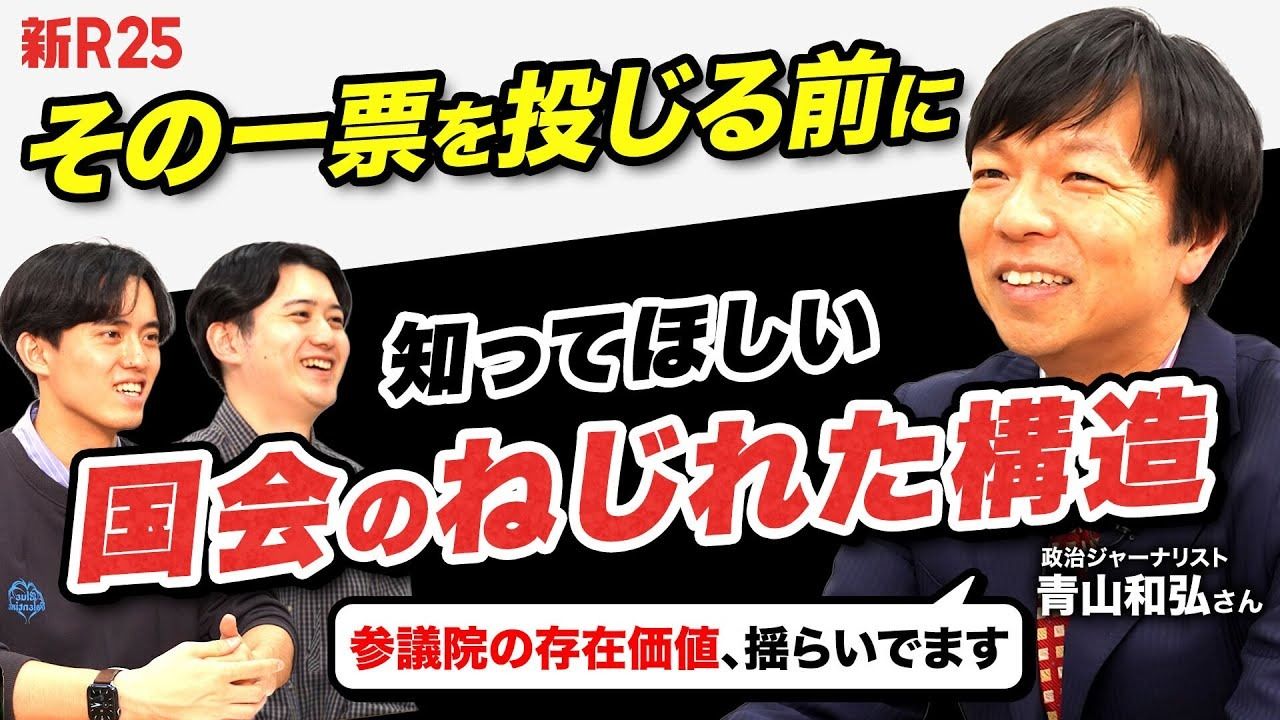
【参議院はAIに?】ダラダラ決められない国会なら、参議院を「革新の議会」に変える逆転の発想【Judge25 参議院必要?不要?】
新R25編集部
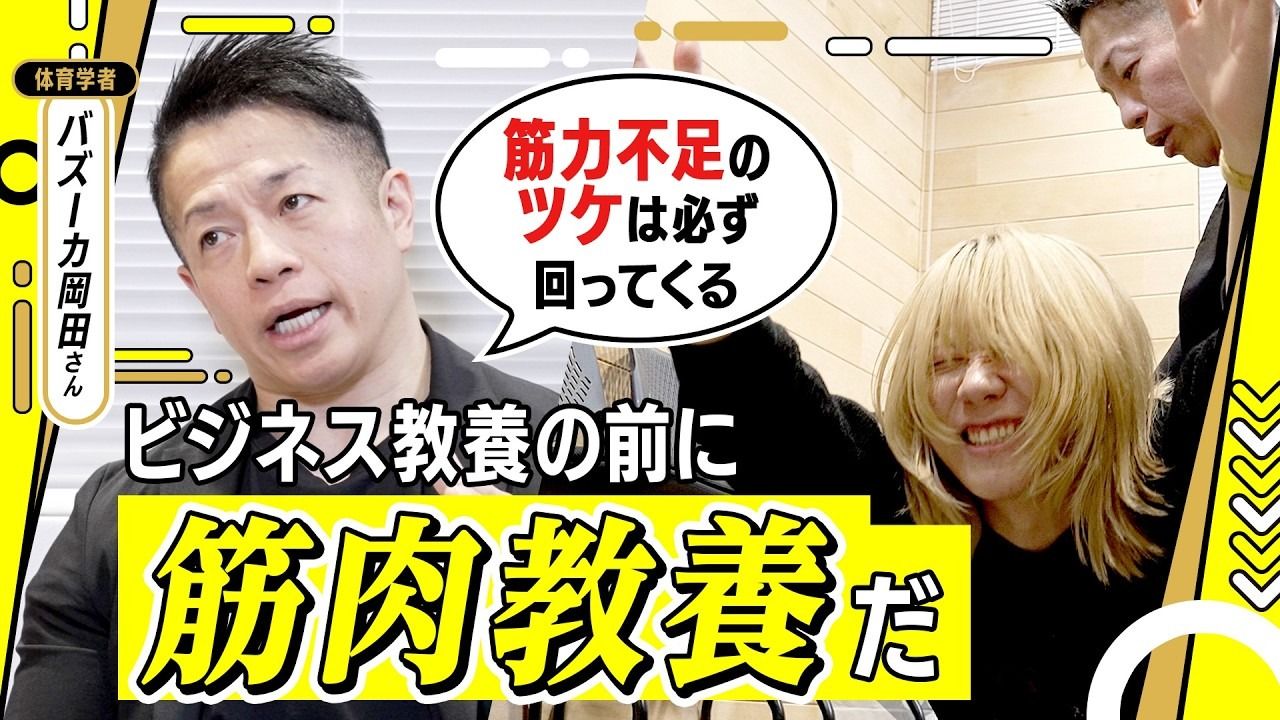
「ツケは必ず回ってくる」バズーカ岡田さんが岸谷蘭丸に説いた、「忙しいから」を理由に筋トレを一切しないことのリスク
新R25編集部
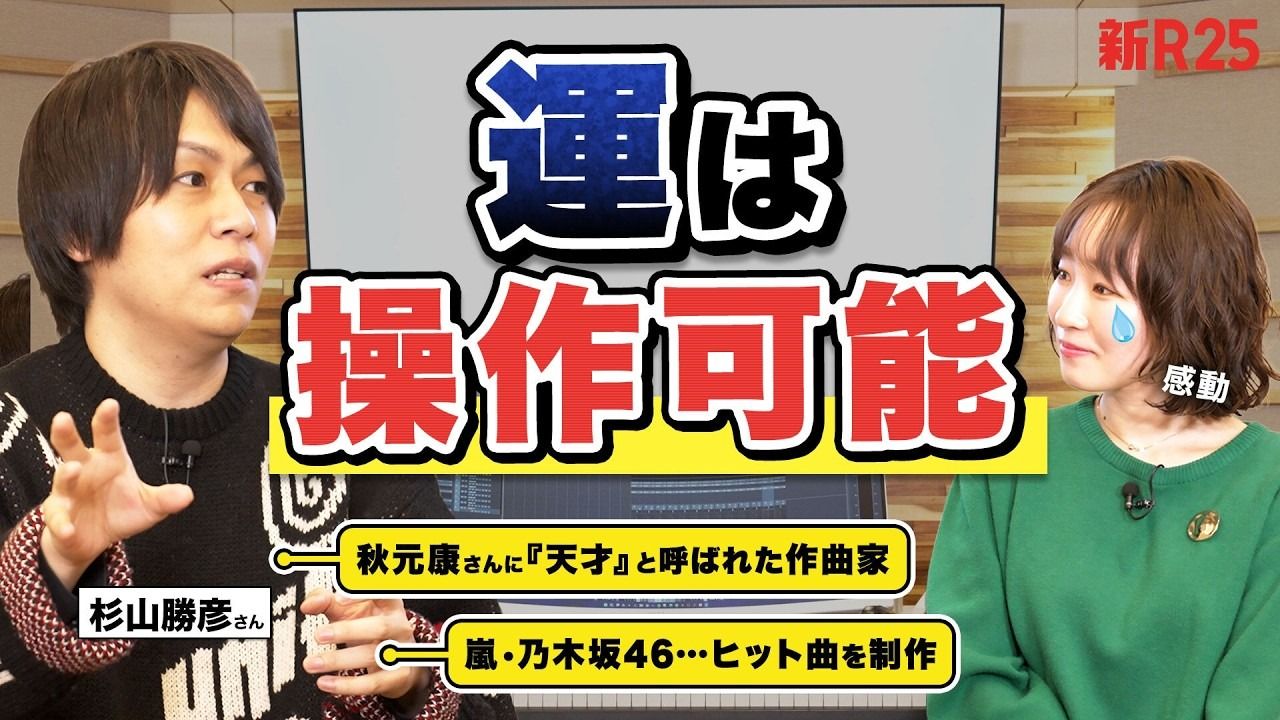
「実力はあるのに選ばれない人」の特徴は?秋元康さんに"天才"と呼ばれる作曲家の納得回答
新R25編集部
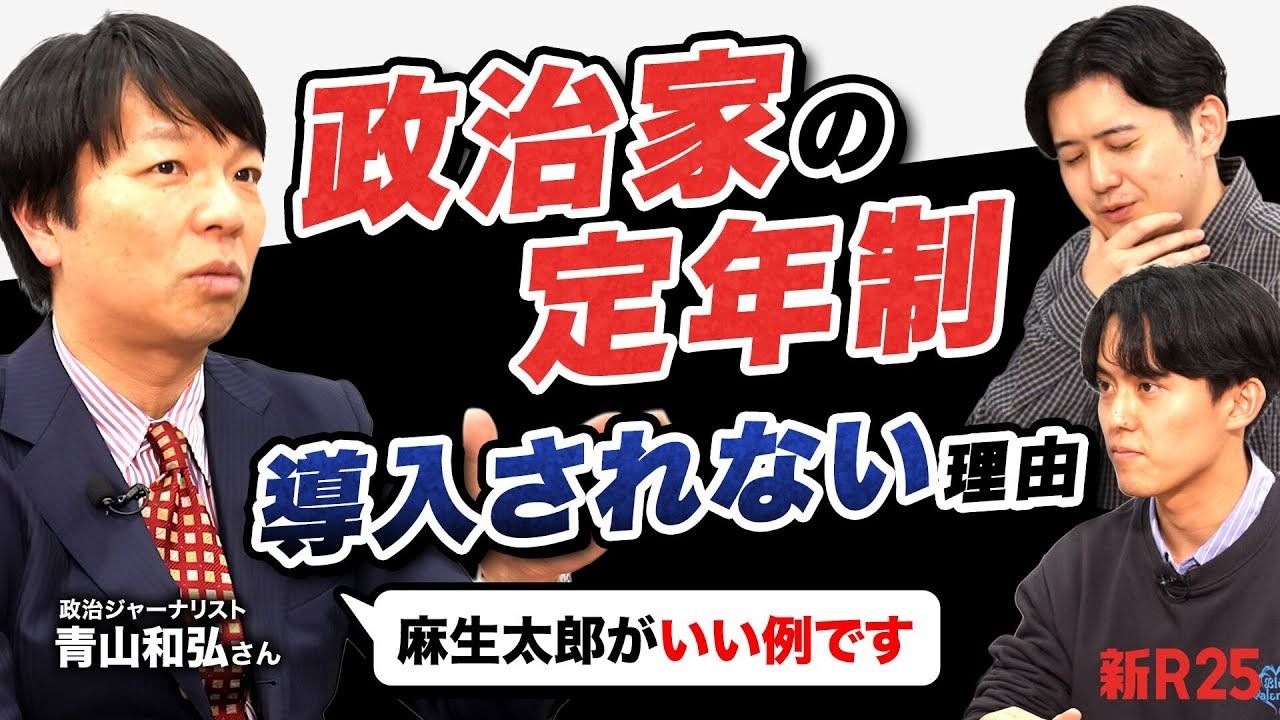
なぜ政治家だけ定年がない? "若手"52歳で社長を降りたCA藤田社長との「辞め時」の決定的違い【Judge25 政治家に定年は必要?】
新R25編集部
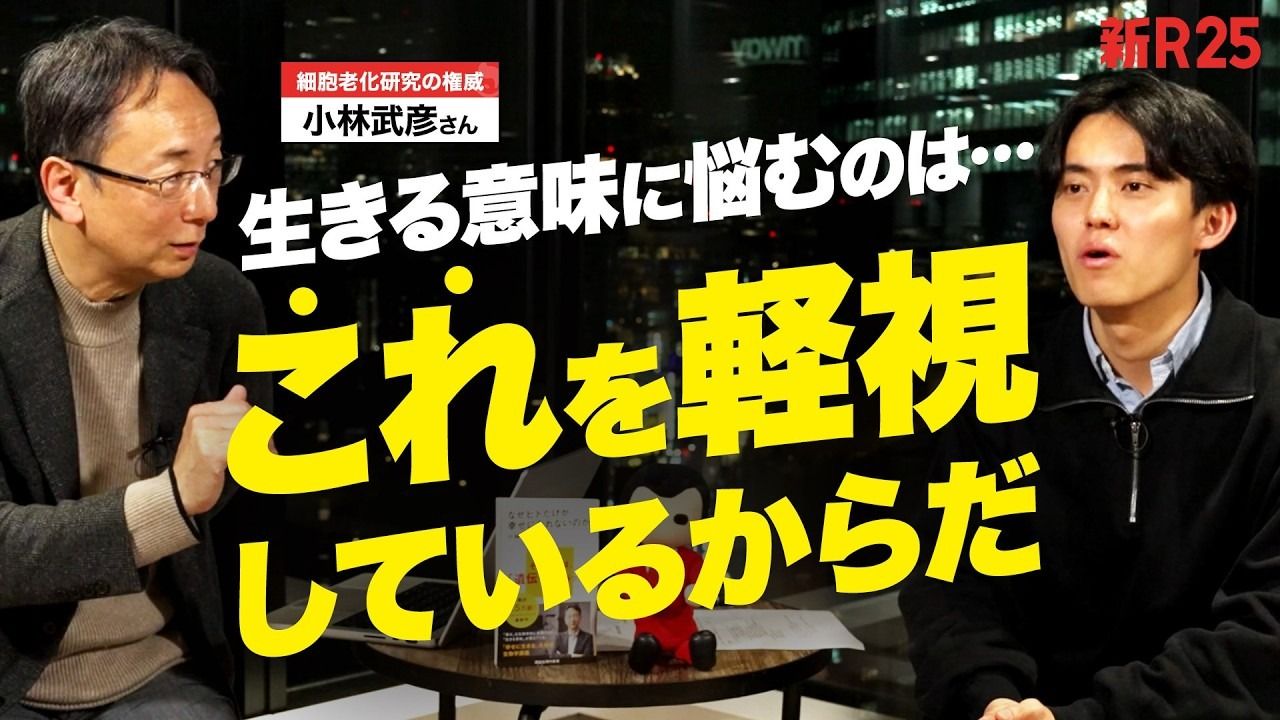
「意外と軽視されてるのが...」生物学者・小林武彦先生が教えてくれた、ヒトが生きる意味に悩む理由
新R25編集部
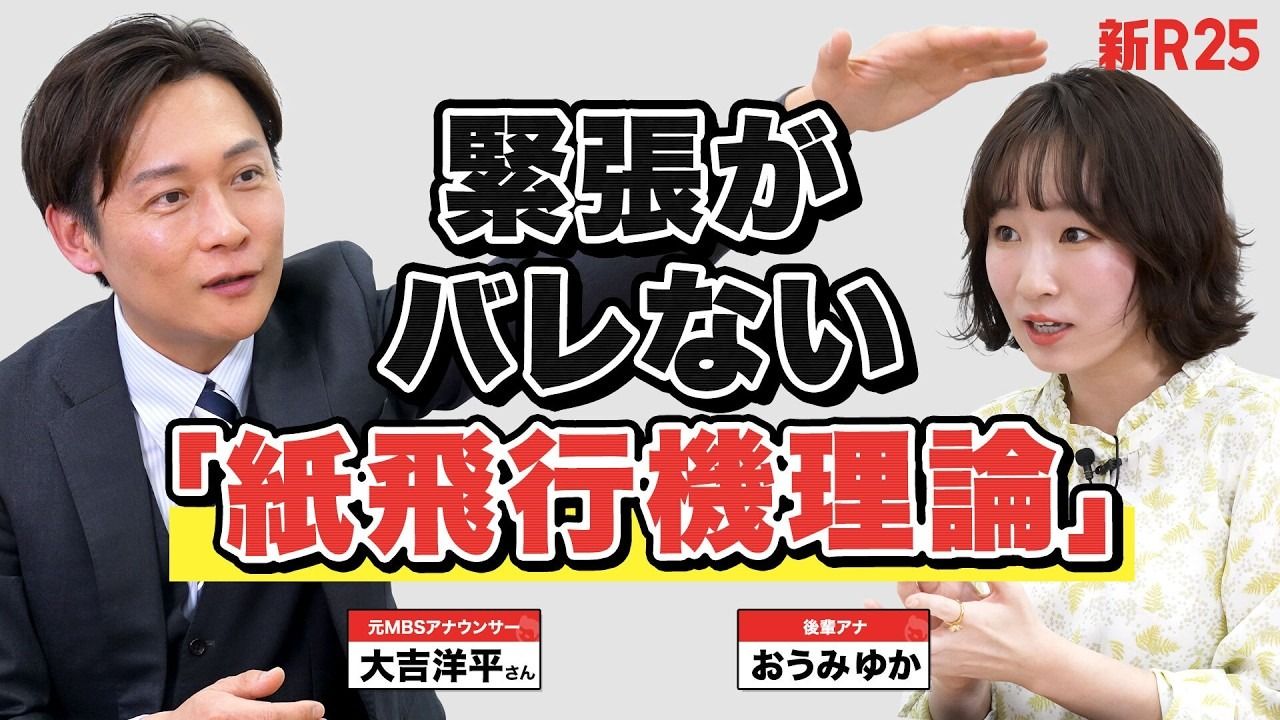
「緊張していい。堂々とビビれ」実況のプロが実践する、緊張がバレない"紙飛行機理論"
新R25編集部














