 ビジネスパーソンインタビュー
ビジネスパーソンインタビュー
夢はプロセスにこそ意味がある
【1万字抜粋】何度もブレイクできたのはなぜ? 中田敦彦『幸福論 「しくじり」の哲学』
新R25編集部
目次
- なぜ「武勇伝」はヒットしたのか?中田敦彦が語る「ブレイクに必要なたったひとつの答え」
- 相方・藤森慎吾との出会いがブレイクへの大きな要因だった
- 従来の型では勝てない。苦肉の策で生まれた「武勇伝」
- なぜ「武勇伝」はヒットしたのか?
- 「低迷したオリラジを救ったのは“言葉の力”」オリラジ中田が言語力を磨く理由
- 落ち込んだとき、力になったのは“言葉”だった
- 言葉は人を動かす最大の武器
- 夢への道のりをどれだけ楽しめるか。『PERFECT HUMAN』でわかった“やりきり力”
- 代表作「武勇伝」を刷新させたかった
- 「二番目に手を挙げる」も強みになる
- 夢はプロセスを味わい尽くせた者が勝つ
- 「同世代の同性がファンにいたら、その芸人は大丈夫」YouTubeの世界へと踏み出せた、島田紳助の言葉
- 1年で登録者数200万人を突破!『中田敦彦のYouTube大学』
- 新ジャンルへ参入するときは、自分の強みを生かすこと
- YouTubeの世界へ踏み出せた、島田紳助の言葉
- 立ち上がるパワーをもらえる、温かい一冊
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦さん。
リズム芸「武勇伝」で、デビュー後いきなりの大ブレイク。トントン拍子で芸能界への階段を駆け上がるも、人気を継続させることができずに低迷。「浮き沈みの激しい芸人人生だった」とこれまでの歩みを振り返ります。
芸人の活動以外にも、ダンスミュージック『PERFECT HUMAN』 をリリースしたり、YouTubeへと主戦場を移したりと、活動の幅を広げています。
8月28日に徳間書店より発売された、中田さんの哲学的自叙伝『幸福論 「しくじり」の哲学』では、成功としくじりを繰り返しているという中田さんならではの、今の時代を生き抜くための幸福論が描かれています。
今回は同書より、中田さんの若手芸人時代〜YouTubeへ主戦場を移すまでの葛藤や学びをご紹介します。
なぜ「武勇伝」はヒットしたのか?中田敦彦が語る「ブレイクに必要なたったひとつの答え」
相方・藤森慎吾との出会いがブレイクへの大きな要因だった
ぼくがお笑いの世界にうまく入っていけたのは、よき相方と出会えたことがほとんどすべての要因だったと言っていい。
藤森慎吾とは大学時代のアルバイト先で知り合った。損害保険会社の自動車事故受付センターだ。
夜間のデスク仕事という地味な職場にあって、彼は異色な存在だった。
ブカッとした流行りのファッションに全身を包んで、とにかくよく目立つ。
最初に声をかけたのはぼくのほうからだった。なにも「相方にならないか?」と言ったわけではない。
当時のぼくは、コミュニケーションをとることの重要性をようやく学びはじめたころだから、気になるひとにはどんどん話しかけるようにしていたのだ。
慎吾のほうも当時からいまと変わらずノリが軽いというか、気さくなほうだったので、意気投合するのに時間はかからなかった。
アルバイト先だけに留まらず、そのほかの時間にもどこかへ遊びに行ったり、家にゲームをしに来たりとしょっちゅうつるむようになった。
あるとき、ぼくの部屋で慎吾が1本のビデオテープを目にして、「なにこれ?」と聞いてきた。学園祭でぼくが舞台に立ったときの様子を記録しておいた映像だ。
そう正直に話し、でも見せるほどのものじゃないと弁明はしたけれど、彼がすごく見たが るので恥を忍んで見せることにした。
その日はそのまま帰っていった慎吾が、数日後に会ったときに言い出した。
「お笑い、やらない?俺と一緒に」
ぼくは彼に聞き返した。本気で言っているのか? 人生懸けてやるつもり? 彼は少しためらいながらも、いいよ、ふたりでやってやろうぜと返してきた。
正直なところ、ぼくはその言葉を待ち望んでいた。
最初から、ああこいつとだったらお笑い、やれるかもしれないと思っていた。
でも、半端な気持ちでやるようでは、学園祭のときと同じように、学生の思い出づくり程度のことで終わってしまう。
ぼくはそんなことをしたいわけじゃなかった。
人生のほかの可能性を投げうって、真剣にお笑いで勝負をしてみたいと思っていた。
相方となる人物には、同等以上の覚悟を持っていてもらわないと困る。
慎吾とだったらうまくいきそうな予感はあったが、それも彼がお笑いのことを真剣に考えるのであればというのが大前提だ。
それでぼくから「お笑いやろう」と言い出すことは、決してしまい、あちらが言い出したら、そのときは本気でふたりで打って出ようと、固く心に誓っていたのだった。
首尾よく慎吾が「お笑いだ!」と言い出してくれて、ぼくらはコンビとしてスタートを切ることができたのだけれど、相手が慎吾であるのは心強かった。
というのも彼には、なんといっても「華」がある。
いまもそうだが、彼は当時から本当に華のある人間だった。
アルバイト先でよく目立っていたのに留まらない。おそらくはどんな場に出ても、彼の周りはパッと明るくなる。そういう能力を備えていた。
特に芸事の世界では、華があるというのはとてつもないアドバンテージとなる。
どんなに容姿端麗で話術が冴えた人間がいても、華がある者には敵わなかったりするものだ。
なぜかはわからないけれど、その場の空気をいつもアイツが持っていってしまう…というような経験、ないだろうか?
あれはその人間の華に、知らず知らずだれもが惹かれている結果だ。
「華」はしかも、いくら努力したって手に入れられるものじゃない。
持っているひとはもともと持っているし、生まれつき持っていないひとが急にこれを手に入れるということもまずない。
だからこそ、華のある人物というのは貴重であり、そういうひとがひとたび芸事に目を向けたらたいへんなアドバンテージとなるのである。
慎吾は、生まれつき「持っている」ひとだとぼくには見えた。それがうらやましかった。
せっかくならば活かすべきだとも思った。
だからこそ、ぼくは彼に強く惹かれていったのだ。
従来の型では勝てない。苦肉の策で生まれた「武勇伝」
当初のぼくらは、オーソドックスな漫才ネタをしていた。
自分なりに猛勉強して、練りに練ったネタだったし、かなり練習もしていたので、ネタ見せをすると講師陣の評価も、まあ悪くはなかった。
でもそれは、あくまでも「悪くはない」という程度のもの。
これでは突出した存在にはなれなそうだった。どうしたらいいかと思案した。
ふつうに漫才をやっているかぎり、これ以上おもしろくするのはなかなか難しい。
だったら、漫才の型にあまり捉われず、ちょっとふざけた漫才をやってみてしまおうかと思った。
というのも、これは吉本興業がもともと関西で生まれたこととも関係するのかもしれないが、勢いよくしゃべり倒すあの漫才のかたちは、どうしても関西弁を駆使するひとたちに分があるように感じられたのだ。
ノリというかドライブ感は、彼らのほうがやはり断然いい。
大阪に住んでいたことはあるとはいえ根無し草のぼくと、長野県出身で東京に出てきていた慎吾のコンビは、純粋に語り口の妙味のようなところで勝負する「しゃべり倒し漫才」でのし上がるのは難しいかもしれない。
ならば俺たちは漫才の亜種(あしゅ)をやってしまえ!と開き直った。
そうして追い詰められて捻り出した策が、のちにぼくらをデビューへと導いてくれることになる。
そう、「武勇伝」ネタの原型は、そんな苦肉の発想から生まれていった。
なぜ「武勇伝」はヒットしたのか?
それにしてもぼくらのデビューネタとなった「武勇伝」は、どうしてあんなにウケたのか。
なぜあのころの自分たちに、ブームを起こすようなネタを生み出すことができたのだろう。
はっきりとした答えは、自分のなかを探っても見出すことができない。
もうひとつ遡って、学生時代の学園祭で初めてお笑いの舞台を踏んだときも、まったく経験がなかったというのになぜそれなりにウケをとれたのか。
緻密な計算のもとに高い成功確率が割り出され、それを実行したまでのこと…と言えればいいが、まったくそんなことはない。
学園祭も「武勇伝」も緻密な計画を立てられていたとは言い難い。
けれど、「これならいける!」というイメージを強く抱いて、そこへ向けてできることをすべてやったというプロセスは共通している。
単純な話、準備を尽くしたかどうかが、ひとつの分かれ目ということである。
そのステージに向けて、どれだけ真摯に向き合い、全精力を傾けたか。
できることをすべてやり尽くしたと、心の底から言えるかどうか。
あんがいそんなことが最重要だったりするのだ。
本当のところをいえば、だれのどんなネタだって、真の「おもしろ度合い」なんて測りようもない。
人気の定番ネタ、一世を風靡したネタは数多いけれど、そういうものは純粋なネタのおもしろさとしてもちゃんと最上位になるだろうか?
好みや時代も関係してくるものだから一概には測れないだろうし、あらためて内容や完成度をチェックしてみれば「それほどでも…」というものだってけっこうあるではないか。
つまりは、ひとに受け入れてもらえるか、笑いを生み出せるかどうかは、ネタそのものの精度ばかりとは言い切れない。
ではなにが分かれ目になるのかといえば、やりきった感の末に漂ってくる演者の自信のようなもの。それが大きく作用していそうだ。
そう考えれば、学園祭で初めて経験したステージも、一心不乱に完成させた「武勇伝」も、自分のなかでやり切った感は充分にある。
その時点でのベストを尽くして、 考えに考え抜いた。すると、おのずと結果がついてきたのである。
「低迷したオリラジを救ったのは“言葉の力”」オリラジ中田が言語力を磨く理由
落ち込んだとき、力になったのは“言葉”だった
言葉を武器に生きていこう。それはぼくの生きる指針のひとつだ。
言葉を強く意識することによって、救われたことは数知れない。
たとえば、芸能の世界に付きものの「浮き沈み」への対処もそう。
ぼくらオリエンタルラジオは、なかなか激しい浮き沈みを体験してきた。
デビュー時は「武勇伝」というリズムネタを引っさげて、「新しい感覚の笑いが出てきたぞ!」と注目された。時分(じぶん)の花を咲かせることができたわけだ。
しかしその花はさほど長く持たなかった。勢いのまま自分たちの名を冠した番組まで持つことができたのに、うまく軌道にのせることができなかった。
冠番組の終了とともに人気は引き、ひとつまたひとつと仕事を失った。
その後いくつかの紆余曲折を経て、楽曲『PERFECT HUMAN』が大ヒット。さらにそのあと、ぼくはYouTubeをはじめて半年でチャンネル登録者数100万人を突破することができた。
こうしてあらためてたどると、復元力がひとつのポイントだったのだなと思う。
低迷したときも歩みを止めず、現状を分析して次の手を探る。
それができたから、何度落ち込んでも盛り返すことができたのだ。
その際に自分の力になってくれたのは、やはり言葉だ。
自分の立場をあれこれ考えたり分析したりするのは、言葉の力。新たに活動の方向性を決めるときにも、言語力が唯一最大の武器として機能してくれた。
もちろんお笑いのネタや動画コンテンツなど、ぼくが生み出すエンターテインメントの中身をつくるうえでも、言葉の力はなにより大切だ。
いまのぼくは『YouTube大学』と称して日々動画をアップしていたり、オンラインサロンのメンバーとZoomなどでコミュニケーションをとり続けたりしているわけだが、そのときに提供したりやりとりしたりしているのは、当然ながら言葉である。
『YouTube大学』では、難解そうな歴史的問題や書物の内容を噛み砕いて紹介するのが、ぼくのスタンスであり役目だと任じている。
わかりやすくロジカルな話し方の訓練をしているんですかと問われることも増えた。
特別なトレーニングをしているわけじゃない。あるとすれば、これまでの積み重ねがものを言っているということだろうか。
たとえ話がわかりやすいと言ってもらえることもある。
このコツとして思い当たるのは、エピソードを仕込みすぎないということだ。
だれかとの対話はもちろん、ひとり語りであっても、その場に即した対応をしないと言葉が生き生きとしてこない。
話の流れを無視して無理にエピソードを披露しても、記憶力自慢くらいにしかならない。
いまそこで展開されている話のポイントをさらにはっきりさせるために、ときにたとえ話を用いるのである。
思えば、言葉の力が必要となるのは、芸人として舞台に上がるときだけにかぎらない。
生きていくあらゆる場面で使えるのが言語力だ。
ぼくはまだまだこの力を磨いていいきたいし、言葉とともに生き、言葉の力を活かした仕事をしていきたいと思っている。
言葉は人を動かす最大の武器
ぼくは芸人からはじめてずいぶん活動の範囲を拡げてきたけれど、比較的スムーズに移行できたのは言葉の力のおかげだと思っている。
言語運用能力とはもっとも応用範囲の広い武器だと実感する。
ぼくは近年、Tシャツなどの物販をしてきた。はじめたころは音楽フェスなどに出向いて販売をしたが、そんなとき、ただモノを並べて置いているだけではなかなか売れない。
そこでぼくが前に出て行って、商品についてあれこれウンチクや思いを語りまくって伝えると、たくさん売れるようになる。
芸人として名前と顔を知ってもらっているアドバンテージはあるだろう。けれどモノが売れるのはそうしたネームバリューの力ではない。
ぼくはその場で発する言葉の力だけで、なんとかひとの気持ちを購買にまで持っていこうと必死にしゃべる。するとモノはなんとか売れる。
「言葉が届いた」結果なのだ。
こうしてモノを買う場面で考えるとわかりやすいように、ひとは言葉によって動かされる面が多分にある。
最初は買うつもりもなくぼくの話だけ聞いていたひとが、話が終わるころにはTシャツを手にしているということは、ひとの言葉によってひとの行動が変化したということ。
ひとは言葉によって意思を変えられてしまったり、楽しくなったり悲しくなったり、感情がどんどん突き動かされる。
ひとをこんなに自在に操れるものを、ぼくは言葉以外に知らない。
たとえば宗教というものは強大な力を持つが、あれも基本的には言葉で神や天国や地獄の存在をひとに知らしめている。真理はこうだと、言葉によって信じさせるのだ。
言葉が世界を設定し、ひとを動かしているのは事実だ。だからこそぼくは言葉を武器にしたいと思ったし、その武器をもっともっと磨きたいと日々考え続けている。
夢への道のりをどれだけ楽しめるか。『PERFECT HUMAN』でわかった“やりきり力”
代表作「武勇伝」を刷新させたかった
大ヒットした『PERFECT HUMAN』(※)は、どんな経緯でできあがっていったのか。
(※)ダンス&ボーカルユニットの「RADIO FISH」名義で、2015年にリリース。
「RADIO FISH」はオリエンタルラジオと、ダンサーとして活動している中田さんの弟 FISHBOY、同じくダンサーの Show-hey、SHiN、RIHITO の6人からなるチーム 。
踊ったあとに小首をかしげてポーズをとりながら、 「Iʼm a perfect human.」 と決め台詞を発するパフォーマンスが話題に。
リリース翌年の2016年末に、日本レコード大賞企画賞を受賞。同年の大晦日、NHK紅白歌合戦に出場。
当初のぼくの狙いは、オリエンタルラジオのデビューネタにして代表作「武勇伝」を刷新することだった。
せっかくの持ちネタである。時代に合わせて、またぼくらの成長に応じたアップデートができないものか。模索していたのである。
が、なかなか妙手が浮かばない。そこで、少し理屈っぽく考えてみた。
「武勇伝」はリズムネタである。速いテンポのリズムに笑いのネタをのせてグルーヴを生み出し、お客さんの気持ちを巻き込みながら展開させる。
ぼくらとお客さんが同じノリを感じられれば、ネタの中身がどうあれ笑いはどんどん生み出せるようになっていく。
ということは、これ、ほとんど音楽じゃないか?演者とオーディエンスがノリを共有して互いに気持ちよくなるのだから。
快感と高揚の生み出し方が、音楽と同じなのである。なるほど、リズムネタは突き詰めると音楽だ。
ならば「武勇伝」をイジるよりも、新しい音楽をやってしまったほうが拡がりも出るんじゃないかと思い至った。
お笑い芸人がやるからこそ意味のある音楽のかたちが、ひょっとしたらあるのかもしれない。
そう考えたらワクワクしてきた。これは自分が熱中してやれそうなことだ。
ただ、もう少し考えを詰めないといけない。音楽をやるのはいいとして、さすがにぼくらオリエンタルラジオが歌声一本で勝負できるほど世のなかは甘くない。
たしかに慎吾は、かなり歌がうまい。さすが「チャラ男」というべきか、カラオケが得意中の得意。それでも本職の歌い手とはレベルが違うに決まっている。
ならば歌をメインに据えず、ダンスミュージックでいくのはどうだろう?
身体のキレなら「武勇伝」のパフォーマンスで磨いてきたし、ぼくらには舞台慣れしているという強みもある。
そう、番組の企画で社交ダンスに打ち込んだことなんかも活かせそうだ…。
さらには、ぼくの弟はダンサーなのだ。彼に聞けばダンス界の現状がわかるだろうし、なんなら彼も引き入れて一緒にプロジェクトを進めるのもいい。
弟に相談してみると、ダンス界の課題をいろいろ教えてくれた。
彼は言った、日本はまだまだなんだと。
米国じゃダンサーといえばパフォーマー、アーティストとして大いにリスペクトされる存在。トップ層は高額のギャラを手にしている。日本にはそういう土壌がまったくできていないという。
なるほど確かに日本では、ダンスがエンターテインメント界の中心であったためしはないかもしれない。主流はいつも歌謡曲的な文化だったろう。
舞台の中心に歌うひとがいて、その歌い手を盛り立てるために周りに演奏者や踊るひとがいるというかたち。
集団芸ともいうべきダンスミュージックの定着も、日本ではまだまだこれから。
ならばぼくらもその一助になろうと考えた。
「二番目に手を挙げる」も強みになる
もちろん、「流れ」がきているという確信と勝算はあった。
日本のエンターテインメント最前線では、ダンサーに陽が当たりつつあったのだ。 流れを先導していたのは、言わずと知れたEXILEファミリー。
EXILE本体はもとより、三代目J SOUL BROTHERSやGENERATIONSと、あのころにはさまざまなグループが表舞台に出てパフォーマンスを繰り広げていた。
彼らのパフォーマンスにはボーカルもいるが、そこだけ注目されるようにはなっていない。
ダンサーすべてに陽が当たるつくりになっていて、そのひとりひとりがアーティストとして輝いていた。
ファミリーのリーダーであるHIROさん自身がダンサーだからこそ、ダンサーを独り立ちさせるしくみを目指し、実際に築き上げられたのだろう。
流れを生み出そうと企図して実践してしまうとは、端的にすごい。
この機に乗じて俺たちもやろう!ということだったわけだ。
他人の褌(ふんどし)を借りてて…、と思われるだろうか?
いやいや、時代の流れには敏感であるべきだし、これをうまく活用することは、物事を成功させるひとつの大きな秘訣である。
それに、だ。
「二番目に手を挙げる」というのは、ぼくの得意なパターンでもある。
すでに芽の出ているおもしろいものを早いうちに見つけ出し、そのジャンルを丸ごと好きになって熱中する。それをできるのがぼくの強みだと、自分で認識している。
マーケティング用語に「アーリーアダプター」という言葉がある。新しい商品やサービスをいち早く受け入れ、活用し、拡めていくひとのこと。
ぼくは明らかにアーリーアダプターとしてのふるまいが得意だ。なにもない荒野を耕してどこにもなかった芽を見つけ出す「最初のひと」というよりも、「二番目にやってくるひと」。
これは善し悪しではなく自分がそういうタイプなのだから、強みに変えていかない手はないのだ。
あの時期に「ダンスミュージックをやるぞ!」と躊躇なく言えたのは、アーリーアダプターとしてのぼく自身の感覚を信じていたからこそだ。
『PERFECT HUMAN』をヒットに持ち込めたのはタイミングがすべてだったのかといえば、そうでもない。別の力学も働いていた。
この成功はメンバーそれぞれの熱意と力量を、最もよく発揮できる方法が模索された結果だ。
実は『PERFECT HUMAN』は、RADIO FISHの最初の楽曲ではない。
ダンス&ボーカルユニットとしてのRADIO FISHは、先に述べた意図と方針のもと『PERFECT HUMAN』が出る前年の2014年に活動をはじめ、すでに4曲をリリースしていた。
ただあまり注目されていなかっただけで。 音楽をやりたいんだ!という熱に浮かされてはじめたRADIO FISHだったが、 最初はなかなかしっくりこなかった。なぜだろう?
明確にわかったことがひとつ。どうやらぼくが足を引っ張っている、という事実だ。
ダンスがプロと比べてしまえば見劣りするのは当然。加えてぼくは、歌があまり得意じゃない。
「音楽やろうぜ!」と言い出した当の本人が元凶なのである。途中でぼくはその受け入れ難い事実を突きつけられた。
ふつうならそこで心が折れ、裏に引っ込もうとするかもしれない。
けれど、そのときのぼくはそうしなかった。
このプロジェクトの目的は、ダンスミュージックで成功すること。そして、かかわる人間がみんな最大限に熱くなれることだ。
ぼくが裏に引っ込んでしまったら、ぼくがたぎらせていた熱量は消えてしまい、当初の思いが成就しない。
なにか方策を考えなくてはいけない。
そこでまず、曲の内容にひねりを加えた。いっそぼくをなんらかのカリスマと想定して、みんながぼくを呼び込む歌にしてしまえ。
そういう設定にしたうえで、ぼくはサビがくるまでうしろに控えておく。
それまではほかのメンバーが存分に能力を発揮し、高質なパフォーマンスを披露する。
曲がサビに差しかかり、ハイライトを迎えると、
「ナ・カ・タ ナカタ ナ・カ・タ…」
の呼び声に押されて、いよいよぼくの登場。
短い時間で、できるかぎりのパフォーマンスをする。
これならぼくの能力不足は露呈せず、作品の完成度と熱量を上げることができる。
そうして出来あがった『PERFECT HUMAN』は大ヒットを記録し、紅白歌合戦にまで出場するほどのブームを巻き起こした。
思った以上に派手な音楽活動ができて、 ぼくは大満足だった。 想定外で紅白までいってしまって、そこから先はどうするか。選択が分かれるところだ。
ぼくをはじめメンバーそれぞれがRADIO FISHを大切にしつつ、また新たにやりたいことを追求していくことになった。
ぼくからすれば、その選択はごく自然なことである。
音楽を生涯の生業にするのだという道は本業のひとでもとても険しい道だ。是が非でもダンス一本で食っていく!という決意や実力だって、もちろんない。
ぼくはただ、熱狂できるなにかが欲しくて、あのときは音楽で自分を燃焼させたかった。
夢はプロセスを味わい尽くせた者が勝つ
ぼくはいつだってなにかに「なる」ことを目的とはしていない。
ただひたすらそれを「やる」ことが重要だと思っている。
そもそも音楽に取り組む前だって、ぼくは芸人に「なる」ことができていたのかどうか?そう自問すれば、心許ないところもある。
ただし、芸人としての仕事やパフォーマンスを「やる」ことをしていたのは間違いない。
ステージに立ってコントや漫才をやり、テレビ番組に出演する活動は確かにしてきたのだ。
思うに物事は、目標に達すること自体が楽しいんじゃない。目標に向けてなにかをやっているときがいちばん楽しいのだ。
夢と呼ばれるものは、そういうしくみだ。
だれしも夢が叶うことよりも、夢を追っている時間こそ楽しくてしかたないはずなのだ、きっと。
ということは、夢へ向かう道のりをどれだけ楽しもうとするか。それが勝負である。
だから途中で「本当に夢を叶える才能が自分にあるのか」なんて考える必要はどこにもない。
夢が叶おうが叶わなかろうが、本当のところはどっちでもいいのである。
それよりも、プロセスを味わい尽くした者の勝ち。ぼくはそう信じている。
ただし、プロセスを長くしようとして、あまりに壮大な目標や夢を掲げてしまってもいけない。
あまりに道のりが長すぎると、途中で熱が冷めてしまう。挫折のような感情だけが残りそうで、それはそれで怖いではないか。
そこでぼくはいつも、さほど長期にわたらず、手の届きそうな目標や夢を設定するようにしている。
そういえば受験勉強をしていた高校生のときも、とにかく薄い問題集ばかり買ってきて、全部やり切るという勉強をしていた。
分厚い問題集では途中で心が折れてしまそうだからだ。
モチベーションを無理なく持続させられる薄い本に取り組んで、最後まで終えたら「やったぞー!」と投げ捨てる。そんな勉強方法だった。
小さい達成感や成功体験を積み重ねると、そのうち自分なりの自信も生まれてくる。
「やり切った」という感覚は、次へ進む原動力になる。
やり切った感をたっぷり味わえたぼくは、また別のことにも気持ちを向けられたのだった。
「同世代の同性がファンにいたら、その芸人は大丈夫」YouTubeの世界へと踏み出せた、島田紳助の言葉
1年で登録者数200万人を突破!『中田敦彦のYouTube大学』
ありがたいことにいま、ぼくはYouTubeの世界で名を知ってもらえるようになった。
芸人からユーチューバーになって成功している代表格は、偉大な先輩たる「カジサック」ことキングコングの梶原雄太さんだろう。
そこに名を連ねることができるようになったのならなによりだ。
2019年4月に開設し、日々更新してきたぼくのYouTube チャンネルは、『中田敦彦のYouTube大学』という。
おかげさまでスタートから1カ月でチャンネル登録者数が25万人に達し、1年で200万人を突破できた。
ぼくにとっては、オリエンタルラジオでの「武勇伝」、RADIO FISHでの『PERFECT HUMAN』に続いて、3回めの大きなインパクトを残せた仕事となった。
右も左もわからなかったYouTubeの世界で結果を出せたのは、自分としても大きな自信につながる。
というのもYouTubeの世界は独自の生態系が築かれていて、いくらテレビに出ていて知名度のある人物だとしても、それがそのままチャンネル登録者数に結びつかないところがあるからだ。
ぼくのような立場の者からすると、成功の法則をなかなか見出しづらかったのだ。
幸いぼくは過去の成功体験にあまり重きを置かないタイプなのでよかった。
自分のなかに出来あがった成功法則に寄りかかるつもりなどない。
むしろまったく新しいことをやるほうがワクワクするし、失敗や批判や逆境をある程度は楽しんでしまおうとする自分がいる。
特になにも恐れることなく、イチから自分をカスタマイズしていけたことが、YouTubeの世界で居場所を見つけることにつながったのだと思う。
新ジャンルへ参入するときは、自分の強みを生かすこと
YouTube のコンテンツにはいろんなジャンルが存在する。
ぼくの場合は「教育系」 というカテゴリーということになる。
「前から興味はあった、でもちょっと難しそうだから手つかずだったな」 とだれもが思うようなテーマを取り上げて、できるかぎりわかりやすく、そしておもしろく解説するのが目的だ。
「学ぶって、楽しい」をコンセプトに据えて、「YouTube×教育×お笑い」の相乗効果を狙っているのである。
新しいジャンルへ参入するにあたっては、自分の強みを生かしていくことが肝要だ。
もともとぼくは芸人として一種の「プレゼン芸」を得意としていた面があった。
テレビ番組『しくじり先生 俺みたいになるな』では、あるテーマについていかに説得力あるプレゼンをできるかが勝負だった。
そこでプレゼン力を認めてもらえて、『中田歴史塾』という特番までさせてもらった。
YouTubeに活動の軸を移しても、長年培ってきたこの能力がぼくを助けてくれている。
「教育系」コンテンツということで、当初は歴史、文学、ビジネスといった分野を取りあげて紹介してきた。
その後はさらに数学や物理などの理系、さらに名作と呼ばれる漫画、はたまた都市伝説なんかにも領域を拡げていった。
片足でしっかり基本路線は踏まえつつ、もう片方の足でさまざまな分野を探る、いわゆる「ピボット」をつねにしてきたのである。
新しく流入してくれる視聴者層を探し続けなければ、勢いは維持できない。
YouTubeの動画コンテンツが消費されていくスピードは速い。それに合わせてぼくは毎日、新作動画をアップしている。
1本につき20~30分のものが多いだろうか。 このペースで動画をアップしていくのはなかなか大変な作業ではある。
ぼくの生活の大半の時間は、動画のためのインプット、準備、収録に充てられている。
学んで、すぐに出す。インプットしたら、すぐにアウトプットと慌ただしい。
けれどこのリズムはぼくの性格にも合っているし、動画の鮮度を保つのにも寄与している。
日々、新しい本を読んで知識を入れているわけだが、その段階では自分のほうが教えてもらう側、生徒役として存在している。
学習者であるあいだ、ぼくの内面は、なるほど、へえー、そうかわかった!となかなか忙しい。
そうした感情の揺れを、そのまま動画を観るひとにも味わってもらえるのが、速いサイクルで動画を更新しているメリットだろう。
そう、講義型の動画を配信しているとはいっても、ぼくはなにも知識をひけらかそうというつもりなんてない。
「学び」や「知」のおもしろさ、そのおもしろさとともに湧き起こる熱気、興奮、それこそを伝えたいのである。
YouTube の世界は回転が早いから、仮説と検証を繰り返してどんどん内容や見せ方を修正していけるのもいい。
いわゆる「PDCA」をグルングルンと回せるわけだ。
これはぼくの性に合っているし、ビジネス方面のマインドやメソッドを体得するのにも打ってつけの場だ。
PDCAを回していく過程では、ヒットしているYouTubeコンテンツはもちろん、他ジャンルのヒット作もどしどし参照する。
うまくいっている他者を嫉妬や悪口の対象にしていても意味はない。
嫉妬するほど成功しているものを見つけたら、ぜひここから学びたい、そこにはなにかすごい秘訣が隠されているはずだから、と考えるべきだ。
いいものを見つけたら、近づいてよくよく観察し、真似できるところはないか検証する。
そんなことをしていたら自分のオリジナリティはどうなる?などと心配する必要はまったくない。
なにかを必死に真似ていれば、その過程で自分の個性というのはきっと滲み出てくるものだから。
YouTubeの世界へ踏み出せた、島田紳助の言葉
それにしても、ぼくはなぜあのタイミングで、いきなりYouTubeへと舵を切ったのか。
その判断に疑問を抱く向きもあるだろう。
たしかに転身前のぼくはテレビやラジオのレギュラー番組をいくつも抱え、まあそれなりにメディアで顔を見る芸人ではあったはずなのだ。
でもぼくはみずから、仕事の方向性を変える決断をした。そのきっかけは2017年あたりにある。
当時、RADIO FISHで出した楽曲『PERFECT HUMAN』が、大ヒットを記録していた。
相方の慎吾もぼくも、中堅タレントとしてこのまま次なるステージへ上っていける気配はあった。
ただぼくは、表面上の「なんとなく」な事象だけを見て満足することはできなかった。
現状をもう少し踏み込んで分析するべきじゃないか、という漠(ばく)とした不安があった。
そこで、自分たちのことをマーケティング的な視点から見つめなおしてみた。
すると、ひとつの事実に気づく。
ぼくらが取っているテレビの視聴率は、一面では必要な数字に達していない。いや、全体的にはおおむね好調だ。
とりわけ20~30代の視聴者からは、なかなかいい数字が取れている。
けれど一方で、50代からの数字や支持が、さっぱりだったのだ。
つまりぼくらオリエンタルラジオは、自分たちと同世代かやや若い世代には、受け入れてもらえている。が、上の世代からのウケはどうもイマイチだった。
いまは地上波テレビの視聴層が高齢化してきている。50代以上の層がテレビ視聴のメイン層であって、これからその傾向はますます強くなっていくだろう。
メイン層からのウケがイマイチであるぼくらオリエンタルラジオは、地上波テレビの世界で今後、中核を担うポジションに立ちづらいんじゃないかという予想が立つ。
結果、ぼくはテレビで「自分の裁量で表現をやり切る」ことをあきらめざるを得ないと結論づけた。
なにかをあきらめるというのは、非常につらい。
しかも、これまで懸命に闘ってきた場において、自分の限界を認めなくてはいけないというのは…。
とはいえ、そこでただクヨクヨしたり腐ったりしてしまうのは、もっとカッコ悪い。
ぼくはただなにかをあきらめるわけじゃない。
ひとつの舞台をあきらめたら、そこから違う舞台を目指すのだ。
これは闘いの場を変えるというだけ、と自分の気持ちを切り替えた。
視聴者の高齢化によって、地上波テレビと自分たちの存在の折り合いが悪くなると予想できるなら、みずから仕事の方向性を変えていかなければいけない。
さて、ではどちらの方向へ進むべきか。そう考えていたとき、かつて耳にした島田紳助さんの言葉が頭をよぎった。
「同世代の同性がファンにいたら、その芸人はだいじょうぶ」 というものだった。
そうか。幸いぼくらには同世代のファンがいてくれる。同性のファンもあんがい多い。
チャラ男キャラで売っている相方の慎吾は、男女分け隔てなく広い人気を得ている。
一方、ウンチクを述べ立てる芸風のぼくは、どちらかというと男性に支持されやすい傾向がある。
同世代の同性ファンを大切にするという観点から、今後の方向性を考えるのがいいだろう。
ぼくらを支持してくれる層はいまなにに目を向けているのか。
その答えはすぐに見つかった。
彼らの嗜好は地上波テレビよりも、いまや配信動画にシフトしつつある。
それはあれこれのデータを見てもわかるところだし、なにより自分の周りを見回して、そのひとたちのふだんの時間の過ごし方を訊けば明らか。
人気ユーチューバーが続々と登場して話題をさらっているのを見ても、時代の流れがどうなっているのかははっきりしている。
自分を支持してくれそうな人たちがどこを向いているか、なにが好きなのかわかったのだから、こちらからその世界に飛び込むしかない。
よし、YouTube の世界に分け入るぞ!この判断は、ぼくのなかでは必然だった。
立ち上がるパワーをもらえる、温かい一冊
『幸福論』では、お笑いを志した学生時代の話から、運営しているYouTubeやオンラインサロンの話など、中田さんの“これまで”と“今”がギュッと詰まっています。
ストイックな中田さんの哲学は、毎日の生活で意識したくなるものばかり。
落ち込んだ後に立ち上がるパワーをもらえる一冊です。ぜひお手に取ってみてください。

ビジネスパーソンインタビュー

【ミエルTV】テレビCMはどこまで“見える化”できる? 3社が見据える「テレビCM運用」の超進化【AJA×ソニーマーケティング×日本テレビ(後編)】
NEW
新R25編集部
Sponsored

自己肯定より効くのは、"自己否定を味方につける"こと。髭男爵・山田ルイ53世さん流「憧れ癖」をやめる考え方
新R25編集部

【ミエルTV】危機感を大きな可能性に。テレビCMを“Web広告化”させた3社の共闘【AJA×ソニーマーケティング×日本テレビ(前編)】
新R25編集部
Sponsored
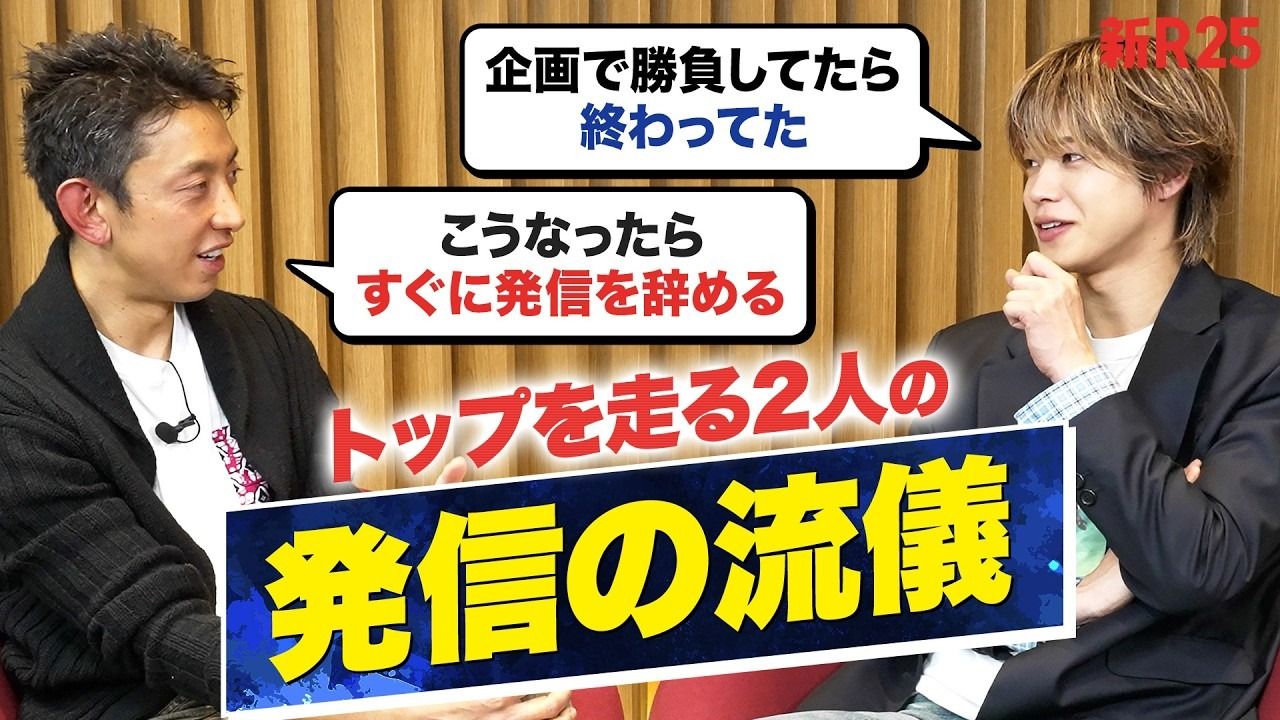
田中渓「こうなったらすぐに発信を辞める」やまと「コムドットの企画はお粗末」トップを走り続ける2人の“発信の流儀”
新R25編集部

「お金の不安は習慣で消せる」統計のプロ、サトマイさん流“お金のコントロール術”
新R25編集部
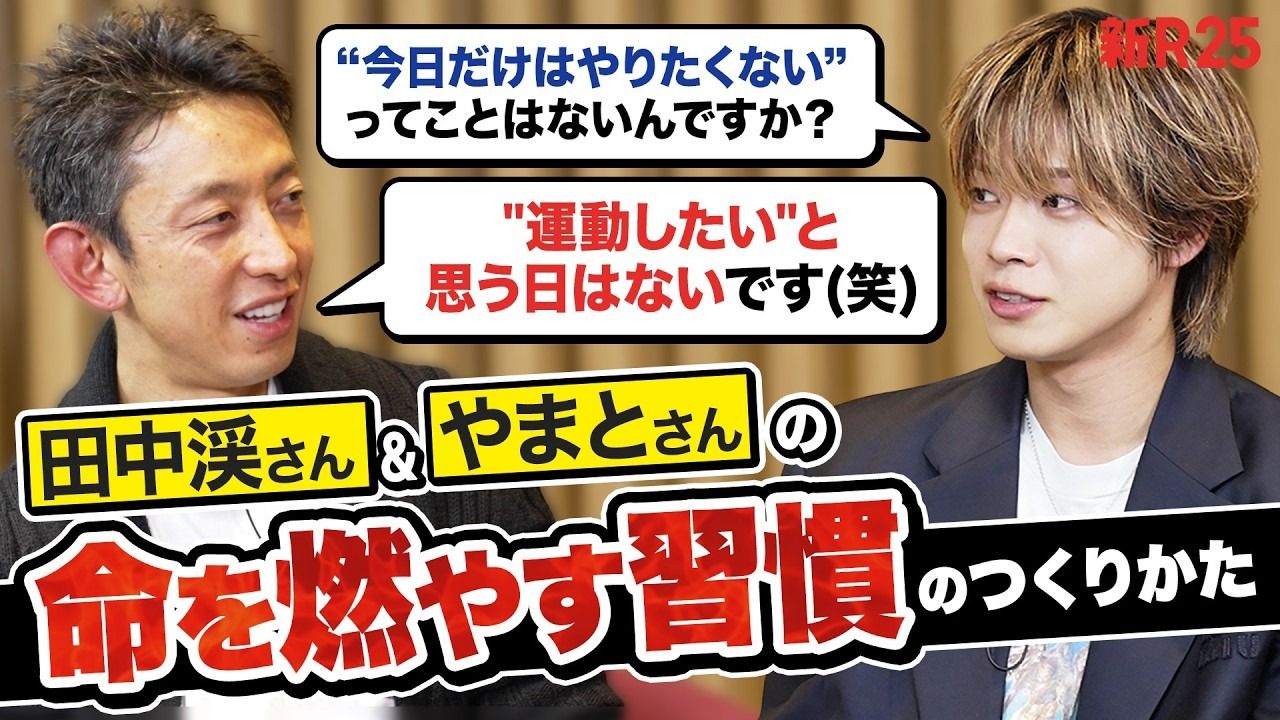
「朝起きて“運動したい”と思う日はない。でも...」全く異なる舞台で成功した田中渓&コムドットやまとが“命を燃やし続ける”理由
新R25編集部











