 ビジネスパーソンインタビュー
ビジネスパーソンインタビュー
山口周著『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか』より
高すぎる達成意欲はリスクにもなる。「美意識」はエリートを犯罪から守る知性だ
新R25編集部
世の中に流通しているビジネス本は数知れず。
日々たくさんの本を読んでなんとなく学びになっている気もするけど、せっかくだから確実に僕らの資産になる「珠玉の1冊」が知りたい。
そこで新R25では、ビジネスの最前線で活躍する先輩たちに「20代がいいキャリアを積むために読むべき本」をピックアップしてもらいました。
それがこの連載「20代の課題図書」。
第3回の推薦者はTheBreakthrough Company GO代表取締役の三浦崇宏さん!
選んだのは、山口周さんの著書『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか ~経営における「アート」と「サイエンス」~』です。
著者の山口さんは、「分析」「論理」「理性」を重視する現代の企業およびビジネスマンは、これからの時代を舵取りすることはできないと強く主張しています。
三陽商会と新しいパーソナルオーダースーツブランド「STORY & THE STUDY」を手がけている三浦さんが推薦する同書より、「ビジネスマンになぜ美意識が必要なのか?」という点を3記事にわたってお届けします。

エリートを犯罪から守るための「美意識」
一般に「エリート」という言葉を聞いて「犯罪」を連想する人は多くないでしょう。
私たちは、エリートというと、清廉で高潔な人物をなんとなく想定してしまいがちです。
しかし、実はエリートが身を持ち崩す大きな要因の一つが、「犯罪」なのだということを忘れてはなりません。
昨今の日本企業でコンプライアンス違反を主導した経営幹部の多くは、有名大学を卒業して大企業に就職した典型的なエリートだったということを思い出してください。
なぜエリートはしばしば犯罪に手を染めるのか?
これには「動機」が作用していると考えられます。ハーバード大学の行動心理学の教授で、私が勤務しているコーン・フェリー・ヘイグループの創業者の一人でもあるデイビッド・マクレランドは、社会性動機を、
1.達成動機=設定したゴールを達成したいという動機
2.親和動機=人と仲良くしたいという動機
3.パワー動機=多くの人に影響を与えたい、羨望を受けたいという動機
の3つに分類し、動機のプロファイルによって適する職業やポジションが変わることを発見しました。
ここで問題になるのが「達成動機」です。コーン・フェリー・ヘイグループの分析によると、高い業績を上げる人材は、統計的に強い達成動機を持つことがわかっています。
達成動機というのは「与えられた目標を達成したい」という欲求ですから、高い業績を上げた人物が強い達成動機を持っているというのは、とてもわかりやすい話ですね。
高い目標を掲げて、その達成に向けて限界まで努力するという態度は、褒められこそすれ非難されるべきものではありません。
私たちの多くは、そのような態度を持つことを、ある種の「絶対善」として教育されてきてしまっています。
しかし、一方で問題もある。
というのも「高すぎる達成動機」を持つ人は、「達成できない」という自分を許すことができないために、粉飾決算などのコンプライアンス違反を犯すリスクが高いんですね。
目標達成後により高い目標を掲げれば、いずれは限界が来ることになります。
そのときに「ここが限界だ」と認めることができない人、つまり「強い達成動機を持つ人」は、そこでなんとかして目標を達成しようとして、法的・倫理的にギリギリなラインまで近接してしまう。
この「粘り」が、彼らエリートを、エリートの立場に押し上げる原動力になったわけですが、その原動力が、やがて身の破滅を招く要因になってしまうわけです。

エンロンのジェフリー・スキリング
この点にこそ「エリートにこそ美意識が必要である」と考える理由があります。
高すぎる達成動機と犯罪という問題を考える際、真っ先に浮かび上がってくる人物がいます。
かつてエンロンのCEOを務め、100億円以上にもなる年収を得ていたジェフリー・スキリングです。
スキリングは、ハーバード・ビジネス・スクールを卒業したのち、マッキンゼーに入社し、そこで史上最年少のパートナーに昇進します。
やがて自分が担当していた顧客であるエンロンの創業者であるケネス・レイから請われ、エンロンのCEOに就任したわけですが、ご存知の通り、その後、エンロンは組織ぐるみの粉飾決算に手を染め、スキリングは実刑判決を受けることになります。
これは「達成動機の強い人」が描きがちな、典型的ジェットコースター型のキャリアと言えます。
エンロン事件は金額のスケールがあまりにも大きかったこともあって、「稀有なエリートの凋落」という文脈で語られがちですが、こういうことは乱暴に言えば「よくあること」なんですね。
さて、興味深いのは、この裁判の過程でスキリング側が展開した抗弁です。わかりやすく言えば、「みんなやっていたことで、自分だけが告発されるのはおかしい」という内容なんですね。
これはつまり、やっていることの倫理的な是非はともかく、法律や慣例(=みんなやってる)に照らして自分の行為に脱法性はないと主張しているわけです。
しかし、このような実定法主義の考え方は、構造変化が激しく起きる社会においては、倫理的に許されない領域まで踏み込んでしまう可能性が高い。
ここで判断の拠り所になるのは、わかりやすく言えば道徳や世界観といった個人の内面的な規範、つまり「美意識」ということになります。
「世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのか?」、その問いに対するわかりやすい答えがここで浮かび上がってきます。
大きな権力を持ち、他者の人生を左右する影響力を持つのがエリートです。
そういう立場にある人物であるからこそ、「美意識に基づいた自己規範」を身につける必要がある。
なぜなら、そのような影響力のある人物こそ、「法律的にはギリギリOK」という一線とは別の、より普遍的なルールでもって自らの能力を制御しなければならないからです。
『イノベーションのジレンマ』の著者であるハーバード大学のクレイトン・クリステンセンは、2010年の同校卒業生に対して、先述したジェフリー・スキリングを含め、同窓生の何人かが犯罪を犯し、結果的に栄光に満ちた人生を棒に振ったという事実に触れながら「犯罪者にならないために」という題でスピーチを行っています。
彼がその中で述べているアドバイスは「人生を評価する自分なりのモノサシを持ちなさい」というもので、筆者が言わんとしていることと基本的に同じことです。

コンピテンシーとしての「美意識」を鍛える
コンピテンシーとはもともと、筆者が勤務するコーン・フェリー・ヘイグループの創業期に、数々の組織開発・人材育成のコンセプトを生み出したハーバードの行動心理学教授、デイビッド・マクレランドが生み出したコンセプトです。
筆者が勤務しているコーン・フェリー・ヘイグループは40年以上にわたって、世界中の企業や非営利組織において類い稀な実績を残した人を多面的に観察・分析し、業種・職種を問わずに共通して観察される行動や思考のパターンを整理して、これをコンピテンシーと名付けました。
現在ではおよそ20程度のコンピテンシーがあることがわかっていますが、この中の一つの項目に「誠実性」というものがあります。
おそらく、多くの人は「誠実性」と聞くと「ルールや規則に実直に従う」といったイメージを思い浮かべるでしょう。とくに、コンプライアンス違反が続発している昨今の日本の状況を知っていれば、なおさらそう思うかもしれません。
コンピテンシーには発揮のレベルがあります。「誠実性」に関して言えば、与えられた規則やルールに実直に従うというのは、低レベルの発揮でしかありません。
では、高いレベルで「誠実性」のコンピテンシーを発揮しているというのはどういう状況を言うのでしょうか?
「誠実性」のコンピテンシーを高い水準で発揮している人は、外部から与えられたルールや規則ではなく、自分の中にある基準に照らして、難しい判断をしています。
そういった行動や思考を発揮している人は、「誠実性」のコンピテンシーを高い水準で発揮している、と言うことができます。
「誠実さ」という言葉には二面性があります。一般に、日本人の多くは、自分が所属する社会や組織において共有されているルールや規範に対して実直に従うことを「誠実さ」だと考える傾向があります。
しかし、もしその社会や組織において共有されているルールや規範が、倫理的に間違っているとしたらどうなるのでしょうか?
このようなことは過去の歴史上に何度も起きています。
例えば、三菱自動車は1977年から2000年の20年以上にわたって、計10車種、合計で69万台のリコールにつながる可能性がある不具合情報を隠していました。
このリコール隠しによる対処の遅れから、走行中のトラックから脱落したタイヤが歩道を歩いている親子連れを直撃し、当時29歳の母親が死亡、その子供たちも負傷するという悲痛な事件を起こしています。
このリコール隠しの発覚により、同社は深刻な経営危機に陥るわけですが、筆者にとって不可解なのは、なぜ20年以上にわたって、このような大規模なリコール隠しが可能だったのか、という点です。
重大な事故につながりかねない不具合を隠す、あるいは実際に重大な事故が起こった後も、それを隠し続けるということを、数千人単位の組織でやり続けることができた、ということは一つの必然的な帰結をもたらします。
それは、これらの非倫理的な営みに携わっていた人たちにとって、「誠実さ」とは、自分が所属する組織の規範・ルールに従うことであり、社会的な規範あるいは自分の中の規範に従うことではなかった、ということです。

「悪とは、システムを無批判に受け入れること」
この問題を考えるにあたって、哲学者のハンナ・アーレントの主張を紐解いてみましょう。
ハンナ・アーレントはアイヒマン裁判を傍聴し、その模様を『イェルサレムのアイヒマン』という直截な題名の本で著しているのですが、ポイントはその副題です。
※アイヒマン…ナチス政権下のドイツの親衛隊将校で、アウシュヴィッツ強制収容所へのユダヤ人大量移送に関わった。「ユダヤ人問題の最終的解決」に関与し、数百万の人々を強制収容所へ移送において指揮的役割を担ったとされる。
興味深いことに、アーレントはこの本の副題に「悪の陳腐さについての報告」と記しているんですね。
アーレントは、アイヒマンが、ユダヤ民族に対する憤怒の憎悪や欧州大陸に対する激烈な攻撃心といったものではなく、ただ純粋にナチス党で出世するために、与えられた任務を一生懸命にこなそうとして、この恐るべき犯罪を犯すに至った経緯を傍聴し、最終的にこのようにまとめています。
曰く「悪とは、システムを無批判に受け入れることである」と。
そしてアーレントは、「陳腐」という言葉を用いて、この「システムを無批判に受け入れるという悪」は、我々の誰もが犯すことになってもおかしくないのだ、という警鐘を鳴らしています。
アーレントが指摘するように、「悪」というものが、システムを受け入れ、それに実直に従おうとする「誠実さ」によって引き起こされるのだとすれば、私たちは「悪」に手を染めないために、どうすればいいのか?
結論は明らかです。「システムを相対化すること」しかありません。
自分なりの「美意識」を持ち、その美意識に照らしてシステムを批判的に見ることでしか、私たちは「悪」から遠ざかるすべはないのです。
重要なのは、システムの要求に適合しながら、システムを批判的に見る、ということです。
なぜこれが重要かというと、システムを修正できるのはシステムに適応している人だけだからです。
ここまでくればもうわかりますね、そう、システムに適応している人たちというのはつまり、いわゆるエリートです。
最適化していることで、様々な便益を与えてくれるシステムを、その便益にかどわかされずに、批判的に相対化する。
これがまさに、21世紀を生きるエリートに求められている知的態度なのだ、ということです。
これからのビジネスの必須スキル「美意識」を磨くために必要な一冊
ビジネスとは畑が違うと思われていた「アート」「美意識」の世界。
ただ、山口さんは、社会が十分に成熟した今だからこそ、「美意識」を基準にした判断が求められると言います。
「美意識を高めるには何をしたらいいのか?」
その答えはぜひ『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』でお確かめください。
また新R25では、山口さんの著書『ニュータイプの時代』の抜粋記事も公開中。こちらも合わせてどうぞ!

ビジネスパーソンインタビュー

【参議院はAIに?】ダラダラ決められない国会なら、参議院を「革新の議会」に変える逆転の発想【Judge25 参議院必要?不要?】
新R25編集部

「ツケは必ず回ってくる」バズーカ岡田さんが岸谷蘭丸に説いた、「忙しいから」を理由に筋トレを一切しないことのリスク
新R25編集部
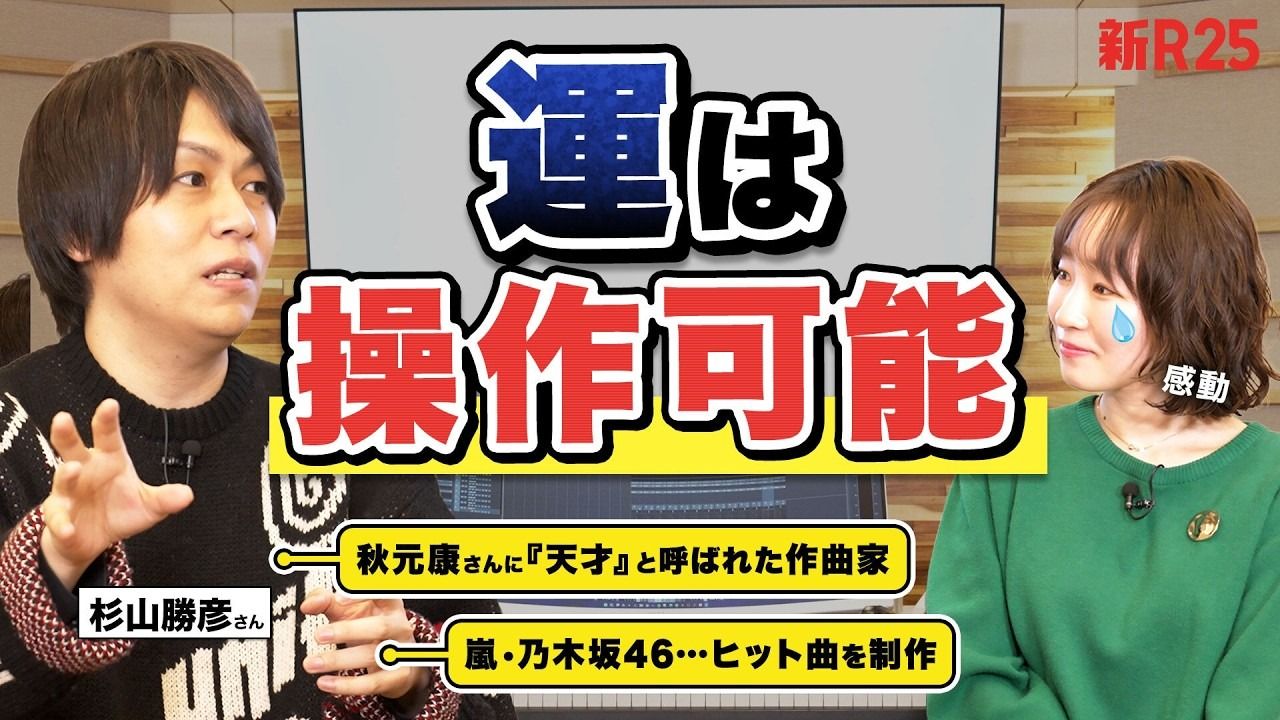
「実力はあるのに選ばれない人」の特徴は?秋元康さんに"天才"と呼ばれる作曲家の納得回答
新R25編集部

なぜ政治家だけ定年がない? "若手"52歳で社長を降りたCA藤田社長との「辞め時」の決定的違い【Judge25 政治家に定年は必要?】
新R25編集部
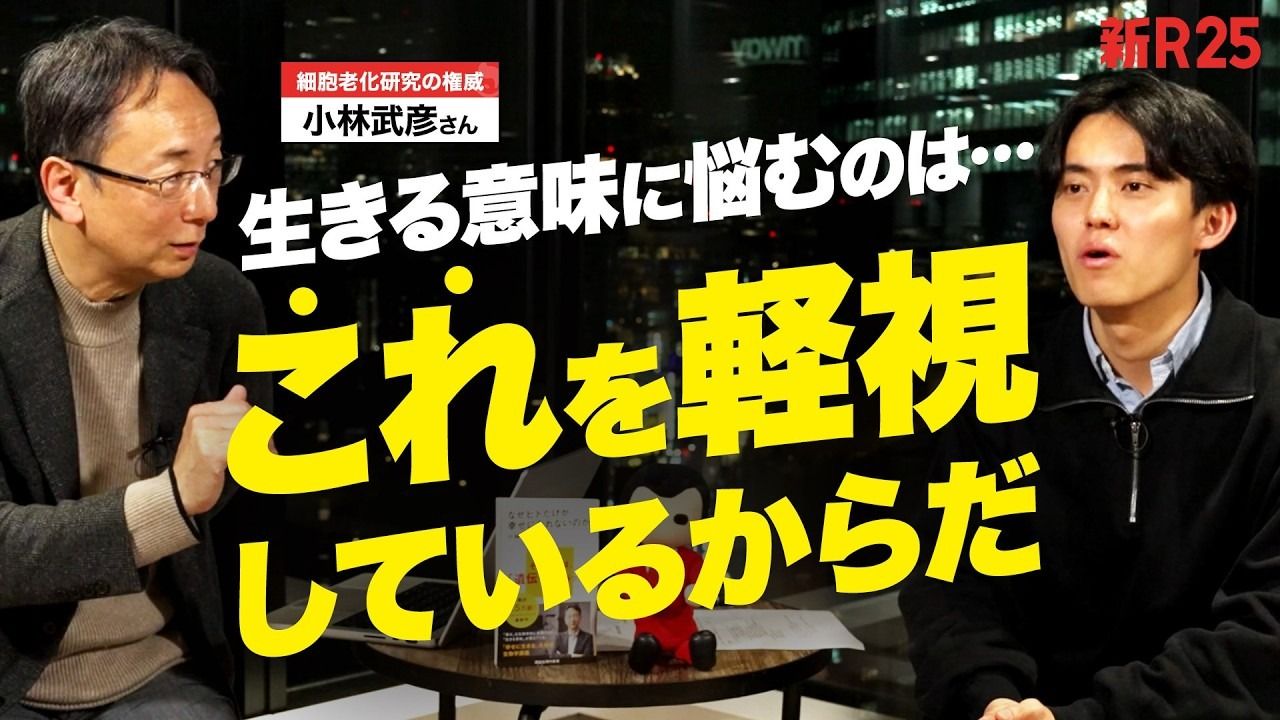
「意外と軽視されてるのが...」生物学者・小林武彦先生が教えてくれた、ヒトが生きる意味に悩む理由
新R25編集部

「緊張していい。堂々とビビれ」実況のプロが実践する、緊張がバレない"紙飛行機理論"
新R25編集部






