 ビジネスパーソンインタビュー
ビジネスパーソンインタビュー
ビジネスモデルの秘密をひもとく
ドラッグストアの売上No.1は「食品」だった! なぜスーパーより安くできる?
新R25編集部
医薬品、化粧品から日用品まで。今や生活に必要なものはほぼそろう「ドラッグストア」だが、店舗によっては「食品」の価格がスーパーより安いこともめずらしくない。メイン商品ではないはずの食品が、なぜここまで安く売られているのだろうか?
ドラッグストアの売上No.1は「食品」だった!来店頻度を高める狙い
(経済産業省「平成28年小売業販売を振り返る」より)
経済産業省のデータによると、平成28年度のドラッグストアの商品販売額は5兆7258億円。そのなかでも最も大きいのが「食品」で1兆4915億円と全体の26%を占める結果に。“ドラッグ”ストアとはいいつつも、一番売れているのは食品だったとは…!
経済ジャーナリストの高井尚之さんは次のように語る。
「まず、昭和時代の『薬局』と現代の『ドラッグストア』の違いは“敷居の低さ”です。ドアをなくして気軽に入れるようにし、洗剤やティッシュペーパーなど、日常使いの家庭品を安くして、お客さんの来店頻度を高めました。食品の取り扱い拡大も、その延長線上にあります。2000年代初めはペットボトル飲料が安い程度でしたが、現在は、店によっては冷凍食品も充実して食品スーパーのような品ぞろえになった。高齢化社会の進展と取り扱い品目の拡大で、年々市場は伸び、百貨店の市場規模を超えました」
原価は20%未満。高収益な化粧品や薬が売れれば、日用品や食品は薄利でもOK
ドラッグストアの食品が安いのは、大きく分けてふたつの理由があるという。
「ドラッグストアの入口脇にある“かご”に入っている食品、店頭に積まれている食品、ティッシュペーパー、洗剤などの目玉商品で来店客の興味を引き、原価率の低い(=儲けが大きい)化粧品や医薬品で利益を出すのが、ドラッグストアのビジネスモデルです」
ドラッグストアは利益率の高い「化粧品・医薬品」が充実しているため、日用品や食品は薄利で売ることができる。原理はわかったけど、実際に化粧品などの原価率はどれくらい?
「一概にはいえませんが、化粧品の例でいえば基本は20%未満でしょう。食品や家庭品に比べて利益率が高い商品だといえます。また、メーカーが研究開発した成果(技術や成分)を複数ブランドで展開することもある。育毛剤を例にとれば、同じ会社の3000円の『化粧品ブランド』も、980円の『家庭品ブランド』も、薬効成分や発毛促進技術は同じというケースも。メーカーにとって、化粧品はブランド価値を上乗せして横展開しやすい商品だといえます」
なるほど。たしかに自分も「なんとなくパッケージがオシャレ」というだけで、チョット高価な商品にも手を出してしまいがちかも…。
マツキヨは店舗数No.1のスーパー・マックスバリュよりも多い。大量発注できるから安く仕入れられる
最近では大規模チェーンのドラッグストアが増え、売上上位の「マツモトキヨシ」や「ツルハホールディングス」、「ウエルシアホールディングス」はそれぞれ全国に1500以上の店舗をもつ。スーパーマーケットの中では最も店舗数の多い「マックスバリュ」(600店舗以上)の2倍以上だ。このようなチェーンの強みを生かした“大量発注”も、食品の安さに深く関係しているのだとか。
「ドラッグストアが『この商品をこれだけたくさん発注するので、安くしてください』と打診して食品メーカー側と思惑が一致すれば、それが“客寄せ”の目玉商品となります。“冷夏でビールが伸びなかった”などの季節要因や、“決算前で数字を上げたいから少し安くして売り切ろう”など、メーカー側の事情で安く卸してもらえることもあるでしょう」
なるほど…。じゃあ、ドラッグストアで安く売られている食品に注目すれば、メーカーや小売業界の“今”が見えてくるということか。
最近では生鮮食品まで扱う店舗も増えており、“一軒で買い物が完結”なんてスタイルも確立されつつあるドラッグストア業界。今後どんな進化を遂げていくのか、注目していきたいところだ。
〈取材・文=池田麻友菜〉

ビジネスパーソンインタビュー
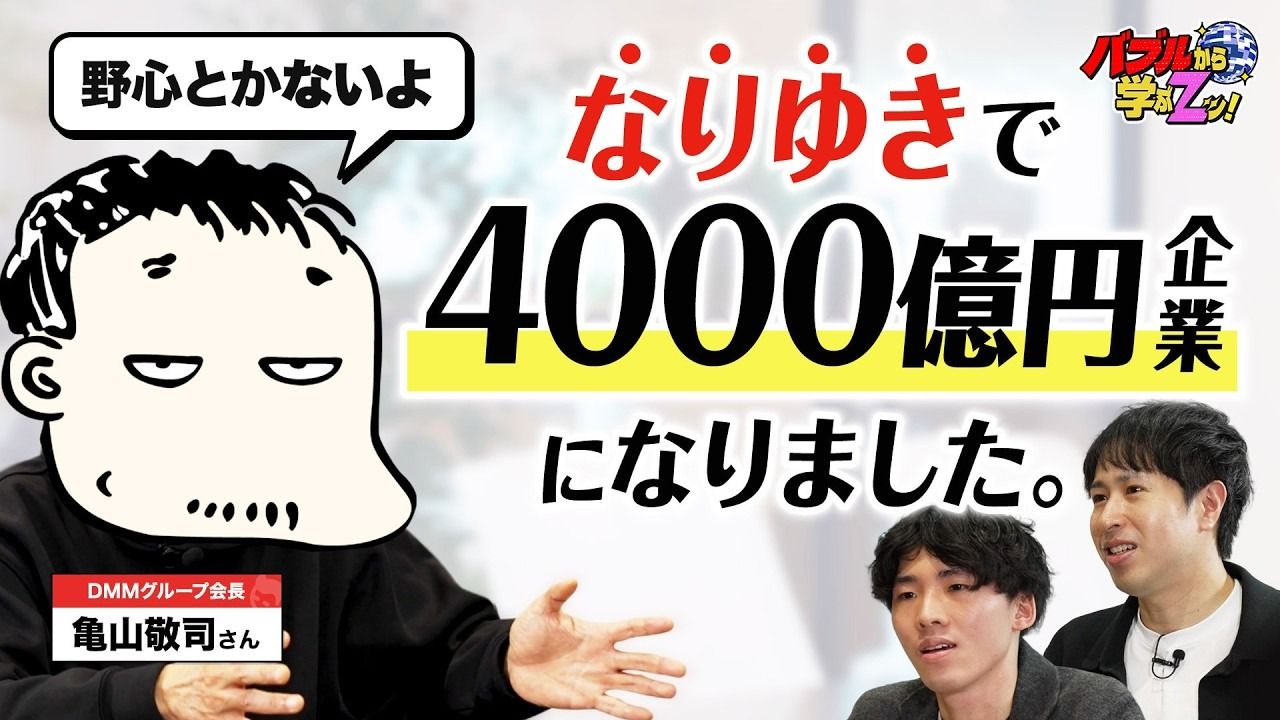
「たいした野心もなかった」「テレビを見て流行りに便乗」露天商出身のDMM亀山会長がこんなに会社を大きくできたのはなぜ?
新R25編集部
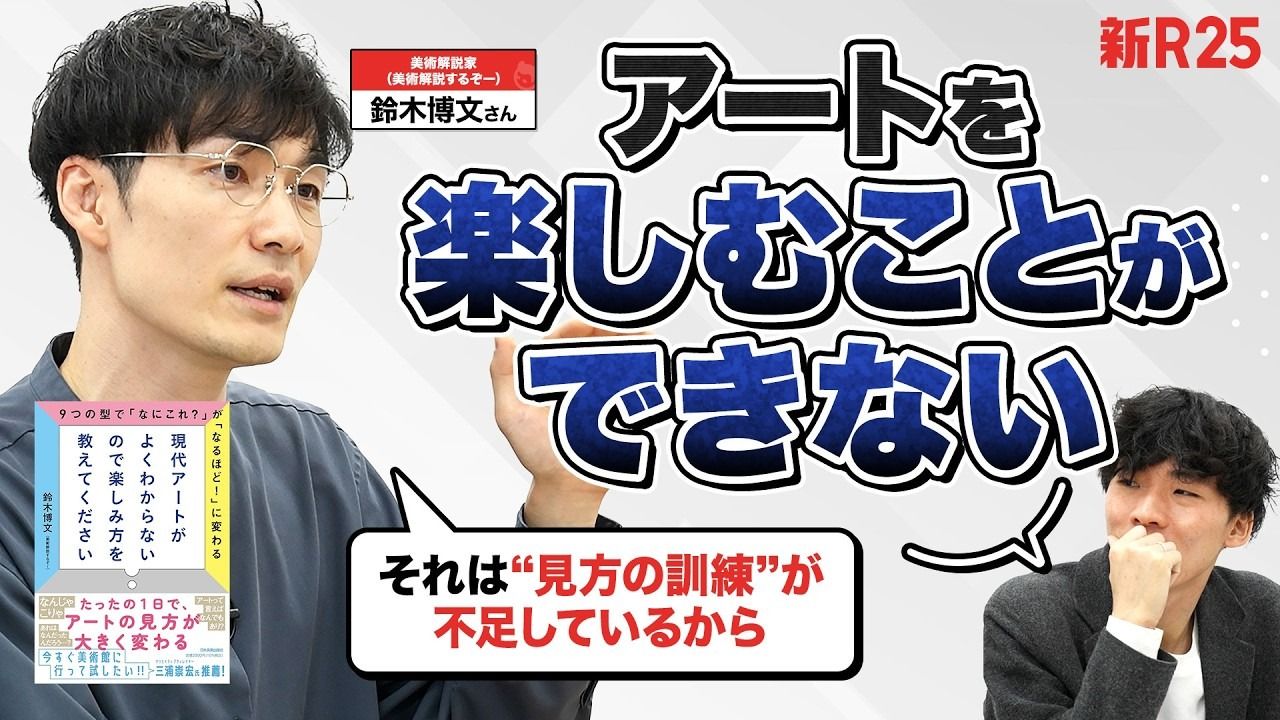
「つまらないのは当然です」現代アートを難しくしている“誤解”をほどく! 美術解説するぞーさんが語る目からウロコの特別授業。
新R25編集部
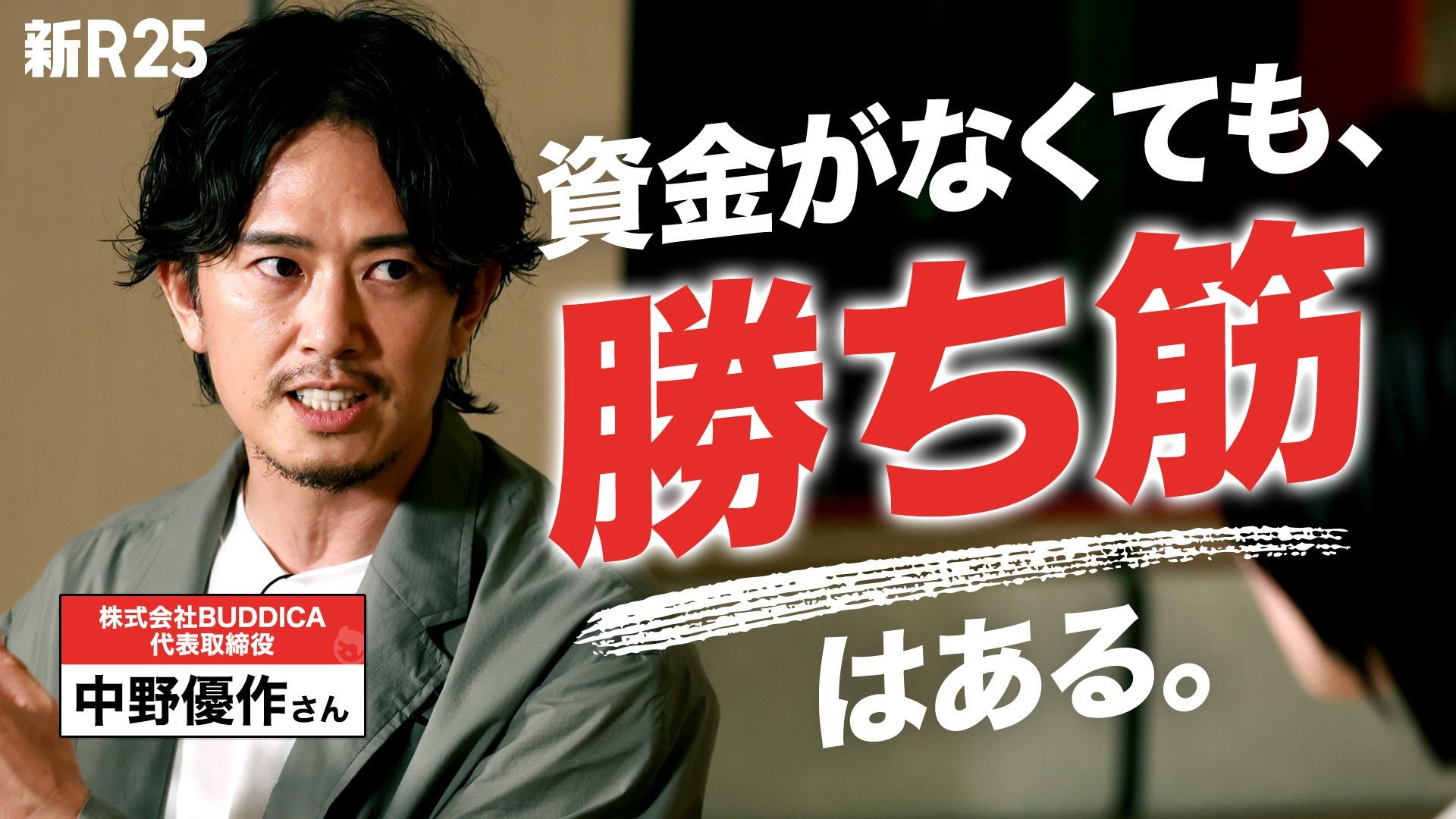
口座残高「数万円」→年商135億へ。レガシー業界を突き抜けた中野優作さんの“起業の心得”
新R25編集部
Sponsored
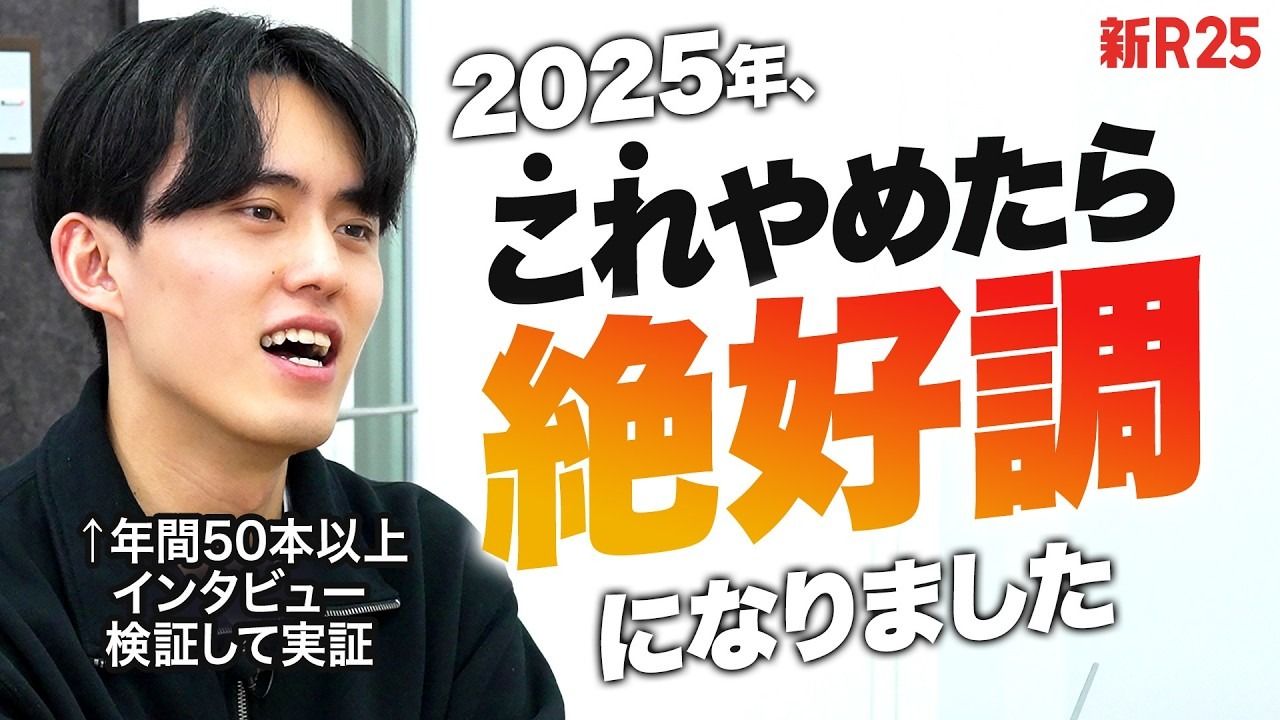
「気づいたら1日が終わってる」Z世代が変わった。50人以上に悩み相談してたどりついた、3つの“やめてよかった”習慣
新R25編集部
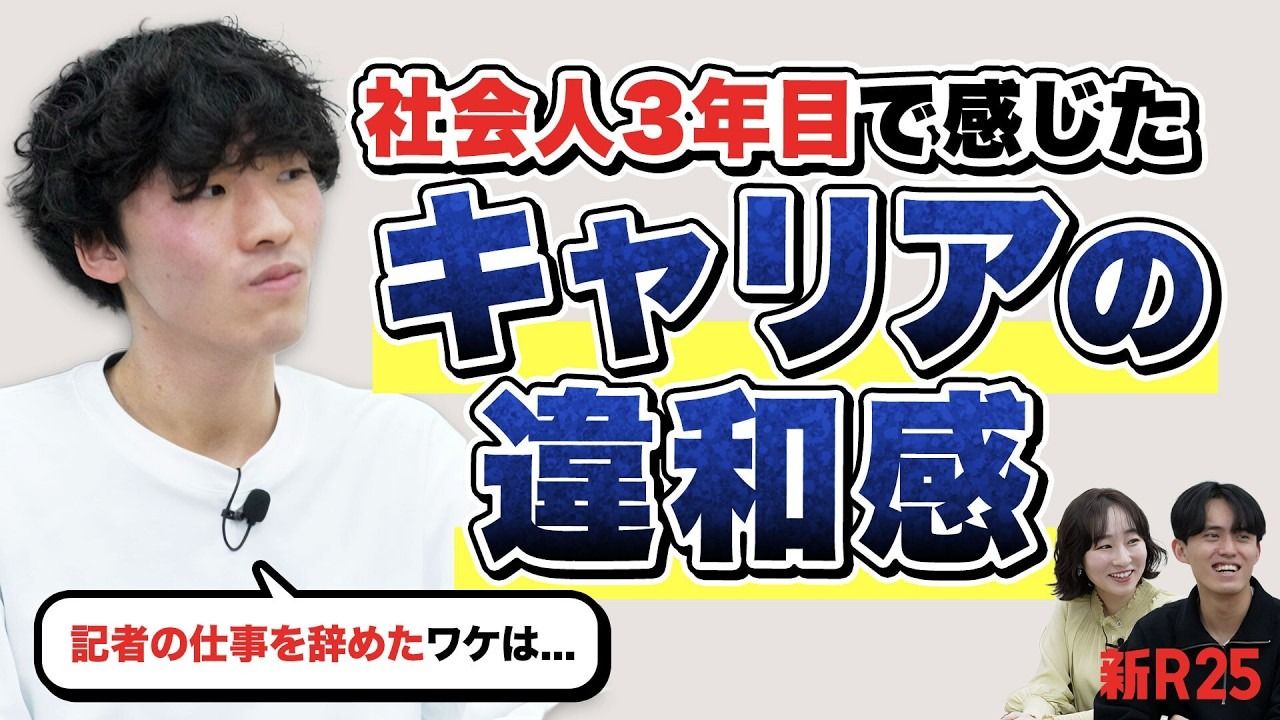
「AI時代、この専門で生き残れるのか?」社会人3年目で感じた“キャリアの違和感”NHK記者からYouTubeの世界へ
新R25編集部

「転職、正直ナメてました」局アナから転身。容赦ないIT企業の洗礼と人生観を変えた気づき【1年振り返り】
新R25編集部





