 ビジネスパーソンインタビュー
ビジネスパーソンインタビュー
インプットのしすぎが邪魔になることも!?
本気でサボってリラックスするのも大事な仕事。「アイデアが次々と浮かぶ方法」はある?
新R25編集部
仕事で、面白い企画や“アイデア”を求められるもなかなか出せず、悶々とすることってありませんか?アイデアが次々と浮かぶ方法があればいいのに…。
そんな夢のような方法を求めて、鋼鉄よりも強靭な繊維「人工クモ糸」や唾液による「がんスクリーニング検査」など、おどろきのアイデアを生み出しつづける慶應義塾大学先端生命科学研究所(以下、先端研)所長・冨田勝教授を訪ねてきました。
ジャグジー、自然、散歩…ひらめきの“確率”を上げる共通項は“開放感”
【冨田勝(とみた・まさる)】慶應義塾大学先端生命科学研究所所長、同大学環境情報学部教授。医学博士、工学博士。人工知能など情報科学の応用技術をベースに、ヒトゲノム解析やメタボロノーム解析などの生命科学分野の研究で数々の功績を挙げている

編集部・N
本日は、「アイデアが次々と浮かぶ方法」を求めてやってまいりました。

冨田教授
アイデアって出そうと思って出るものではないので、方法論やトレーニングで出やすくなるものでもありません。ただ、パッとひらめく“確率”を上げることは可能ですよ。

編集部・N
それを教えてください! どうやったらひらめきの確率は上がりますか?

冨田教授
まずはリラックスした状態になることです。方法はさまざまですが、自然を感じられる場所に行ったり、散歩をしたり。

編集部・N
一般のビジネスマン、特に都内勤務だと自然を感じるのはなかなか難しいです…

冨田教授
なにも森の中に行かなくても、緑の多いカフェスペースや公園なんかで休憩時間をすごしてもいいんですよ。狭い会議室やデスクで悶々としているより、ずっとアイデアが出やすくなります。
外に出られないときは、自然を感じてリラックスできるBGMなどもいいと思います。

編集部・N
そういえば、冨田教授が所長を務めていらっしゃる先端研には“ジャグジー”があるそうですね。

冨田教授
ええ。ジャグジーに限らず、とにかくリラックスできる環境ではいいアイデアがひらめきやすいですね。先端研のある山形県鶴岡市は非常に自然豊かで、アイデアを生み出すには最高の環境なんです。
企業でも、アイデアを出し合うために合宿をするときは、那須とか軽井沢とか自然豊かな場所へ行きますよね?
いいアイデアを出すには人がたくさんいる狭い場所よりも、自然豊かで開放的な環境のほうがいいということを日本人は知っているからです。
NASAでもできなかったアイデア。冨田教授のイチオシは「酒席でアイデアを出す」

編集部・N
ひらめきの確率を上げるために、ほかにはどんな方法がありますか?

冨田教授
酒席ですね。

編集部・N
酒席!? アイデアとどう関係があるんですか?

冨田教授
「独創的なアイデアは会議室ではなく、酒席から生まれる」というのが私のモットーなんです(笑)。
人工クモ糸(鋼鉄より強く、ナイロンのように伸縮性のある繊維素材)の量産に成功した「Spiber」というベンチャーが鶴岡市にあるのですが、これは関山くん(「Spiber」取締役兼代表執行役・関山和秀氏)が大学4年の酒の席で思いついたものなんです。
人工クモ糸の量産は、NASAですら巨額の費用をかけても難しいことでした。

冨田教授
ブレイクスルーできるアイデアというのは、「何言ってるの?」という突飛なものです。そうしたアイデアは会議室では出てこないし、仮に思いついていたとしても言い出せない。
でもお酒の席だと、みんなリラックスして楽しい雰囲気なので、アイデアもどんどん出るし、それを否定することもないわけです。

編集部・N
お酒はアイデアを出やすくするいい媒介なんですね。でも、お酒が飲めない人は参考にできない…

冨田教授
お酒が飲めない人でも酒席という、くだけた“雰囲気”がアイデアには有効なんです。みんながワイワイ意見を出し合う輪に入りやすくなりますから。
誰かの出したアイデアに、ツッコミを入れたり「こうしたらいい」と言ったりするうちに、より面白いものに進化していく。
酒席で毎回いいアイデアが出るわけではないですが、少なくとも会議室にこもっているよりは、ひらめきの“確率”は上がりますよ。
情報を整理する脳のシステムを“緩ませる”ために、意図的なリラックスが必要

冨田教授
温泉に行ってお酒を飲みながらアイデア合宿をするとかね。楽しいでしょ?

編集部・N
楽しそう! ですが、楽しすぎてアイデア出しをサボりそうな気も…

冨田教授
もともと人間は脳内にいろんなアイデアの種(情報)があり、それらをきちんと整理するために、理性を働かせて取捨選択するシステムを持っているんです。
ただ、このシステムが機能しすぎていると情報が整理されすぎていて、“ひらめき”にはつながりにくい。

編集部・N
そこで、温泉や酒席が効くと…?

冨田教授
そうなんです。ぼーっとしたり、リラックスしたりするとそのシステムが緩み、アイデアが出やすくなるんです。
だから、本当にアイデアを出したいなら「サボリ」だとは思わず、本気でリラックスするべきなんですよ。
インプットしすぎると、ひらめきの邪魔になることも!?

編集部・N
あと、たくさんの情報を常にインプットすることも、アイデアを出しやすい頭になりますよね?

冨田教授
アイデアのレベルによりますが、その真逆を唱える説もあります。「多量の教科書的知識や情報がひらめきの邪魔をする」と。

編集部・N
え!

たとえば、ノーベル賞を取るような大発見は分野外の人から生まれることが多いんです。
それは、その分野の常識的な知識にとらわれることなく、自由に考えられるから。

編集部・N
では、同じ部署や業界だけでなく、異業種やいろんな年代の人たちとの交流も、ひらめきの確率を上げることになりそうですね。

冨田教授
そうですね。
専門外の分野においては無知だからこそ新しい気づきがあるし、多様な情報に触れることで脳も刺激を受けやすい。
それで、面白いアイデアが出てきやすくなるんです。
やはり「アイデアが次々と浮かぶ方法」なんて都合の良いものはありませんでした。しかし、具体的なアクションでひらめきの“確率”を上げることはできる。
アイデアが出てこないで悶々としている人は、まずは仕事帰りに同僚と“酒席”ブレストを試してみては?
〈取材・文=新R25編集部/撮影=冨永智子〉
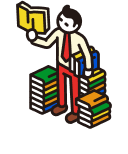
シゴトに効く「カラダハック」

サウナーが言う「ととのう」ってどういう状態?「最強の温泉習慣」著者のドクターに聞いた
新R25編集部

倦怠感の原因にも? 仕事のパフォーマンスを左右する「目のコンディション」の整え方
新R25編集部
Sponsored

夜型生活は頭が悪くなる!? “時間”の専門家が語る「ラクに早起きできる方法」とは
新R25編集部

休日は脳内をこう整えよ。幸福学者が教える「憂鬱な月曜を晴れやかに迎える方法」
新R25編集部

成功者が自殺してしまうのはなぜ? 脳科学的に「幸せになる方法」を教えてもらった
新R25編集部

スマホを触るのが一番ダメ。精神科医が教えてくれた、脳に効く「いいダラダラ」
新R25編集部

ビジネスパーソンインタビュー
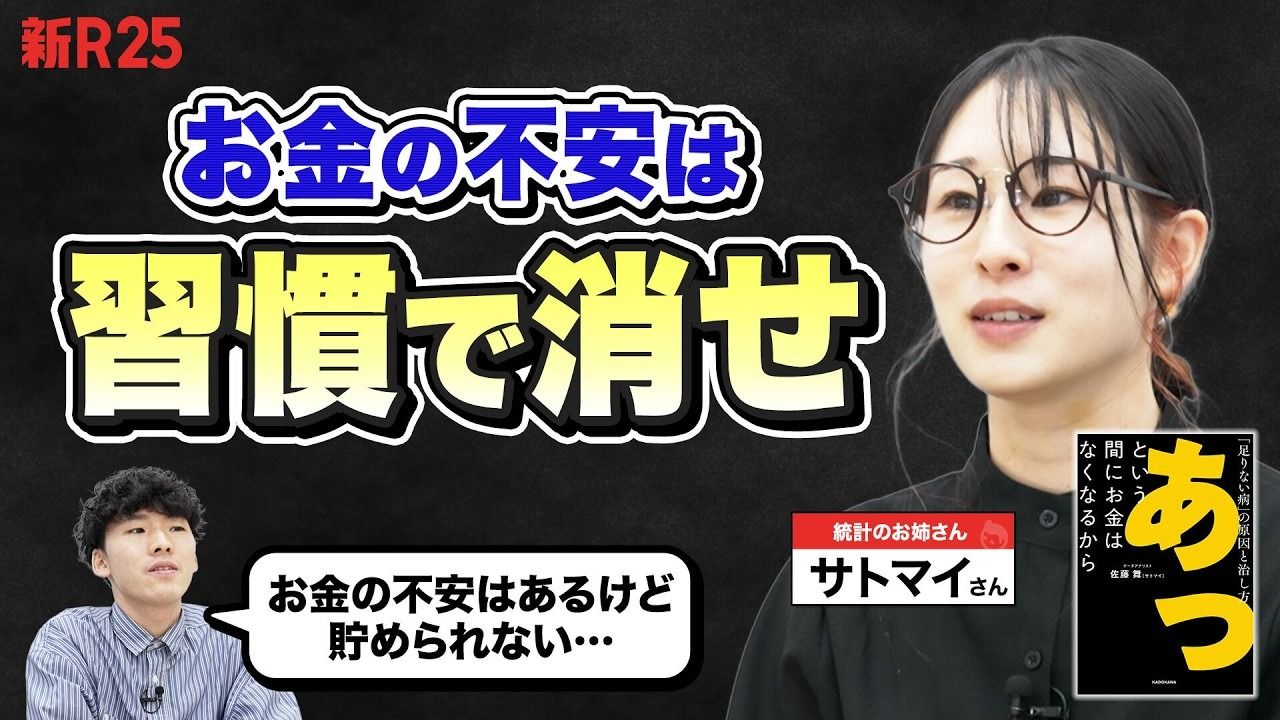
「お金の不安は習慣で消せる」統計のプロ、サトマイさん流“お金のコントロール術”
新R25編集部
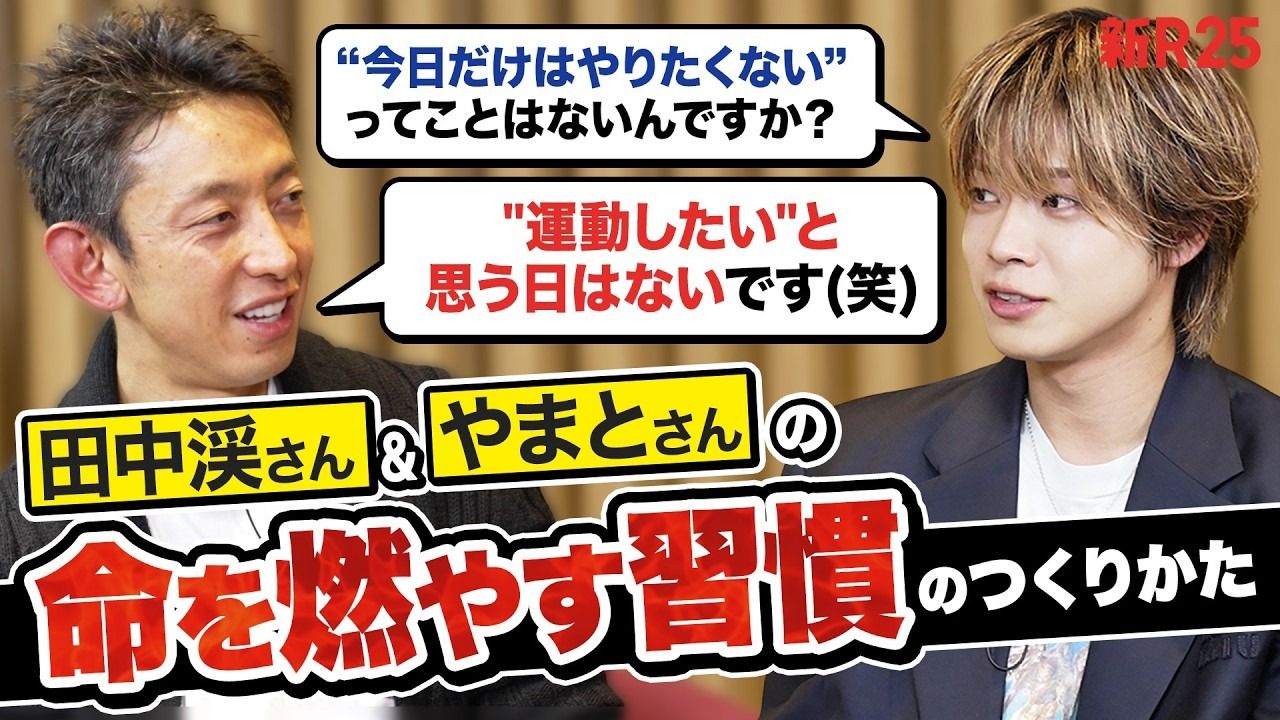
「朝起きて“運動したい”と思う日はない。でも...」全く異なる舞台で成功した田中渓&コムドットやまとが“命を燃やし続ける”理由
新R25編集部
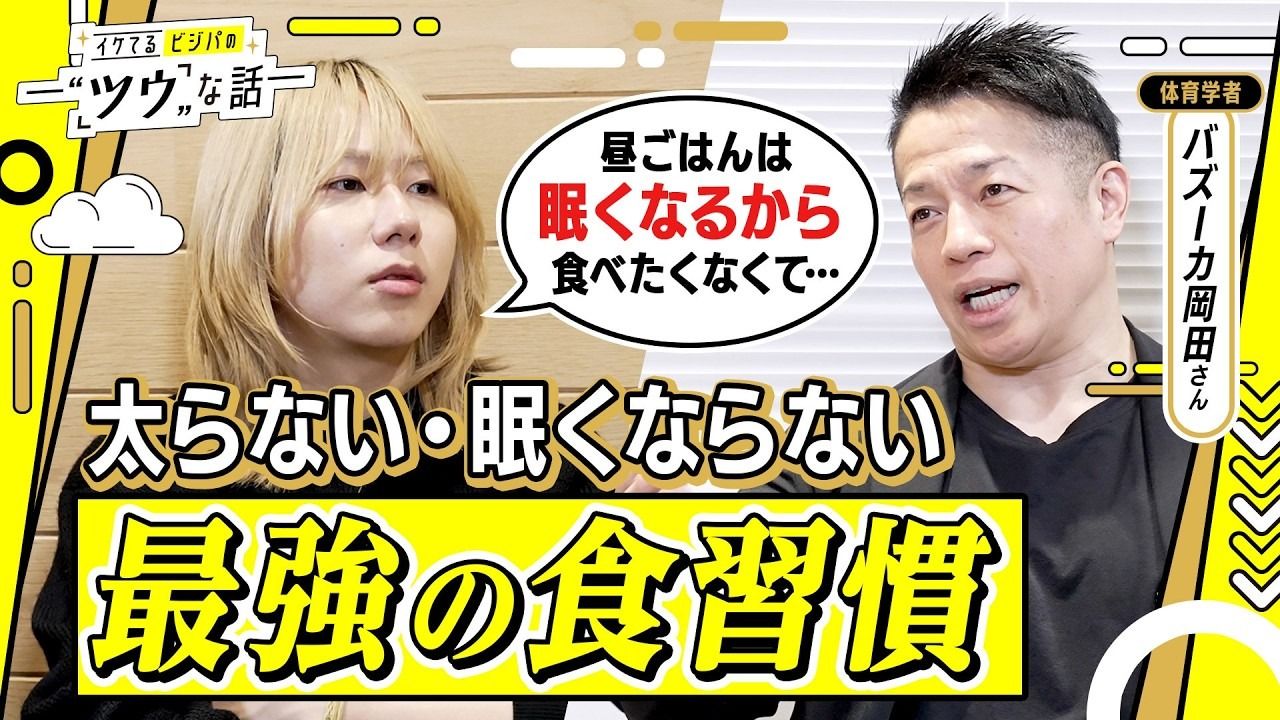
「昼食後は眠いし、会食三昧で太っちゃって…」と悩む岸谷蘭丸にバズーカ岡田さんが授けた、眠くならない・太らない"最強の食習慣"
新R25編集部
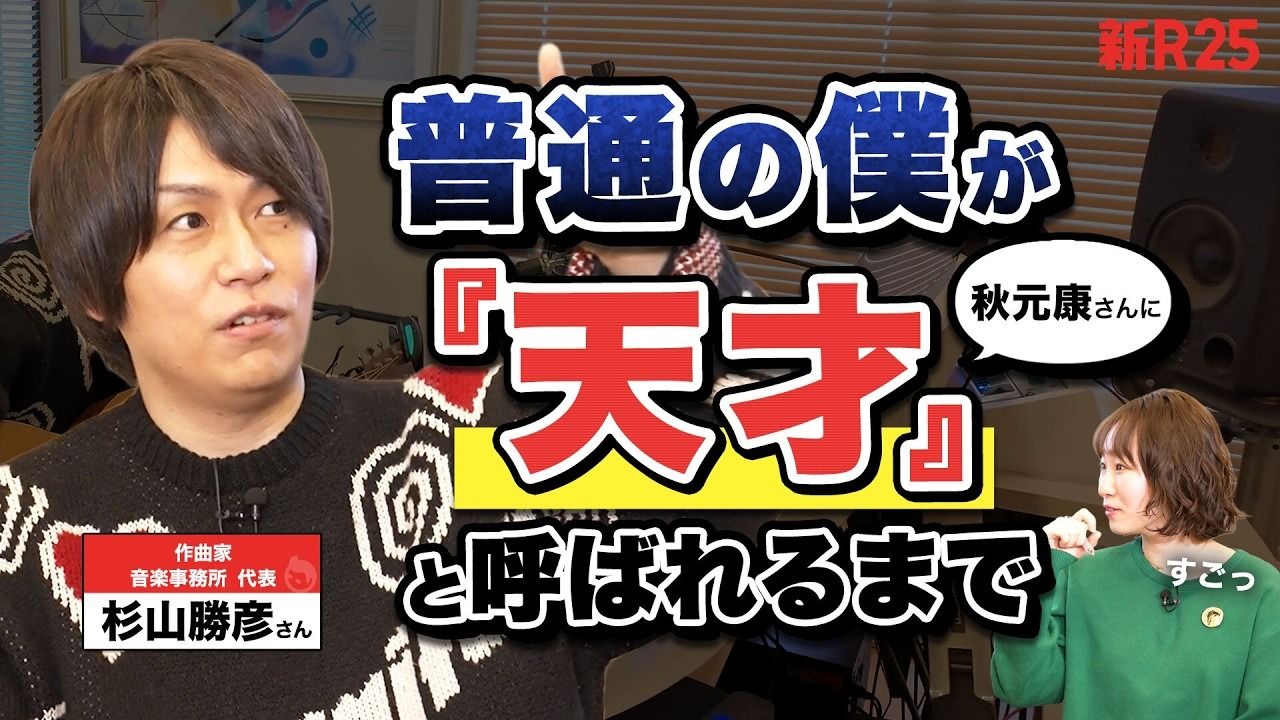
ハッタリで掴んだ作曲家の座。才能もコネもなかった杉山勝彦さんが、秋元康さんに「天才」と呼ばれるまで
新R25編集部
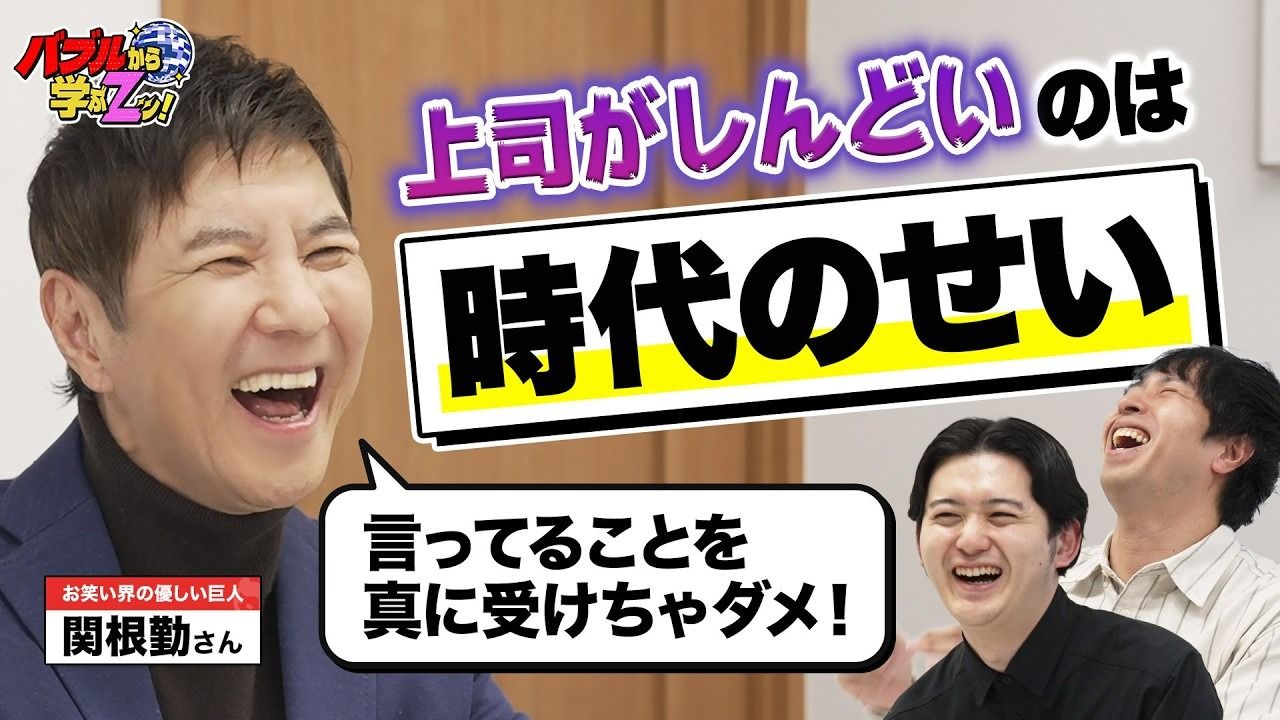
【半世紀売れつづけた“優しい巨人”】ブレずに変化してきた関根勤さんがZ世代に伝えたい「傷つかない思考法」
新R25編集部
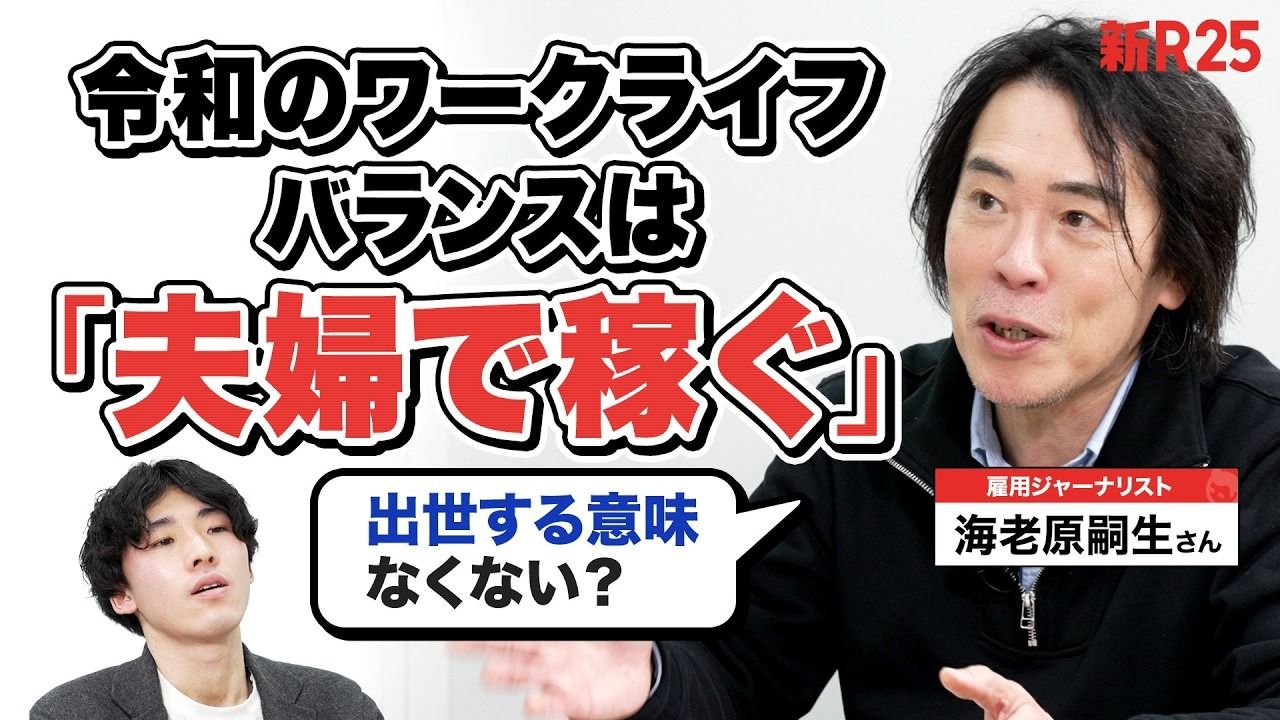
「令和の出世って意味あるの?」雇用ジャーナリスト海老原さんが語る“ワークライフバランスの誤解”
新R25編集部
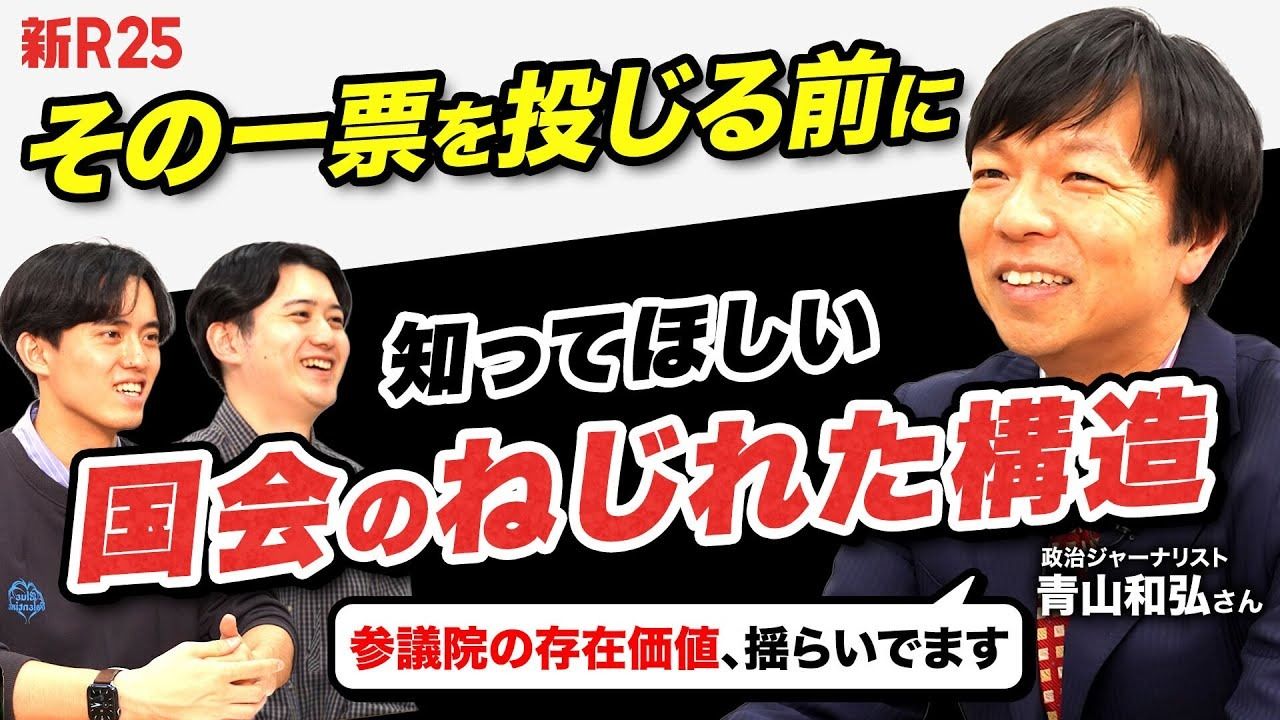
【参議院はAIに?】ダラダラ決められない国会なら、参議院を「革新の議会」に変える逆転の発想【Judge25 参議院必要?不要?】
新R25編集部
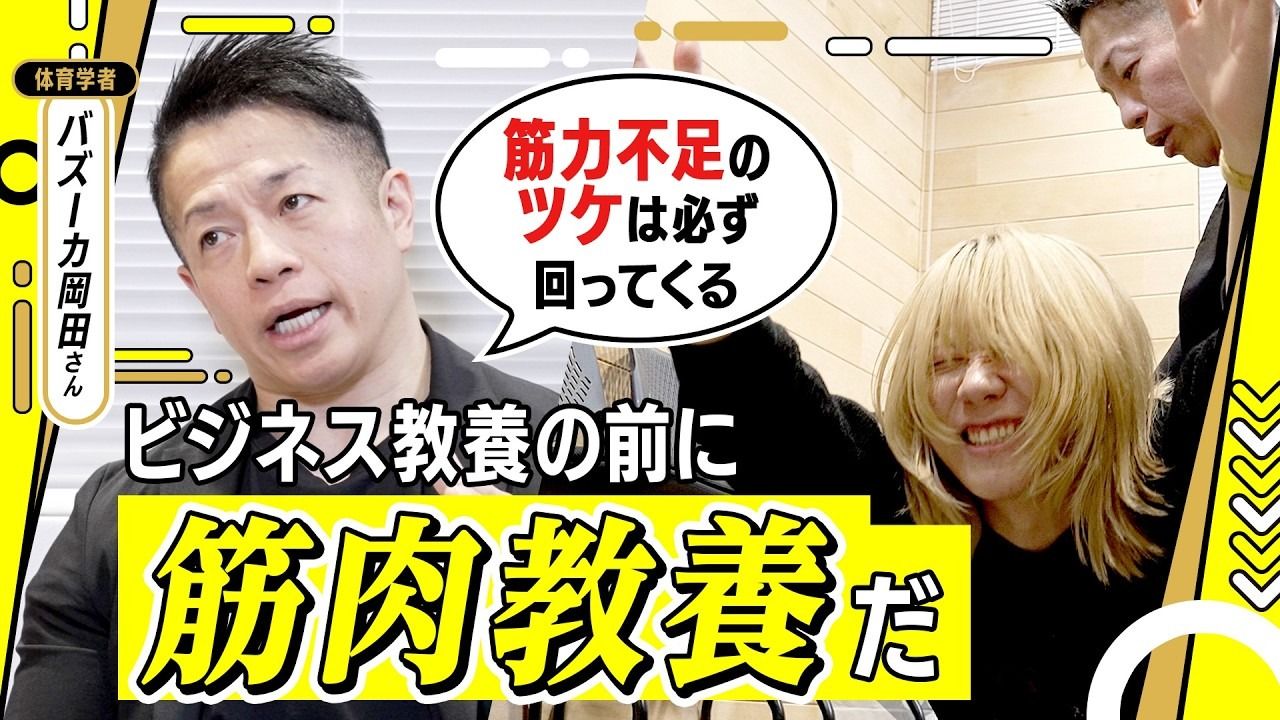
「ツケは必ず回ってくる」バズーカ岡田さんが岸谷蘭丸に説いた、「忙しいから」を理由に筋トレを一切しないことのリスク
新R25編集部
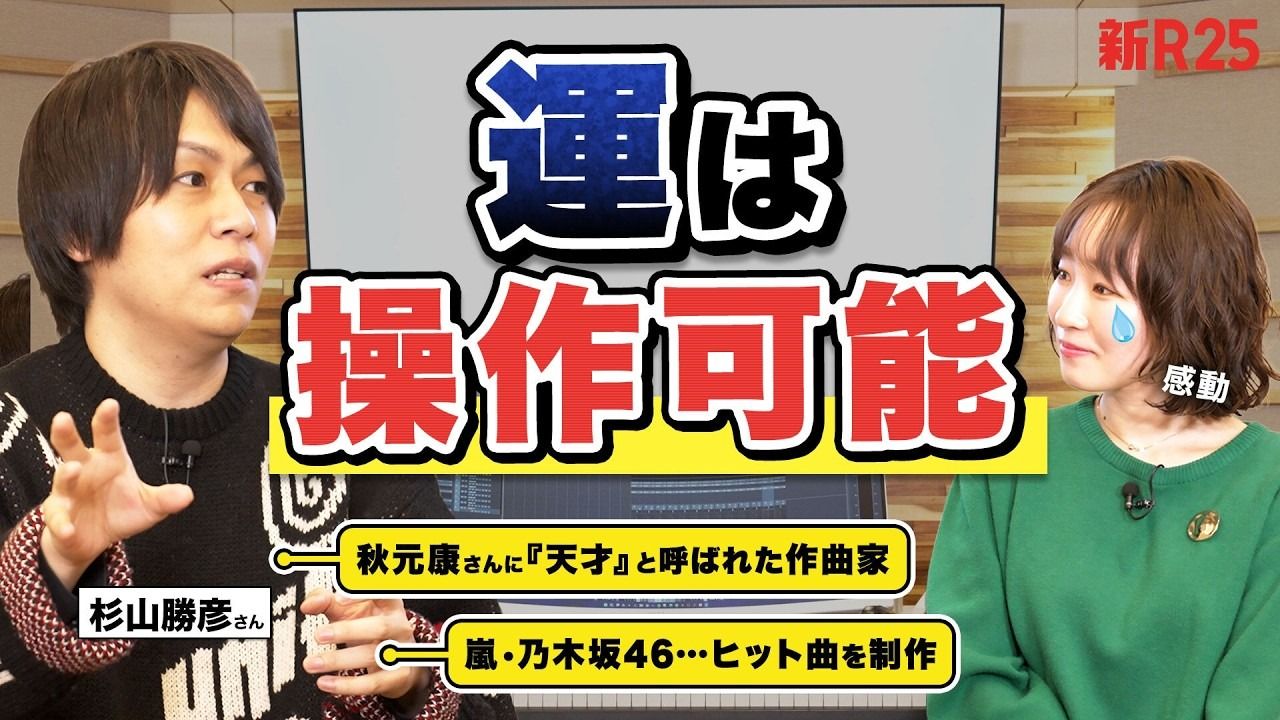
「実力はあるのに選ばれない人」の特徴は?秋元康さんに"天才"と呼ばれる作曲家の納得回答
新R25編集部








