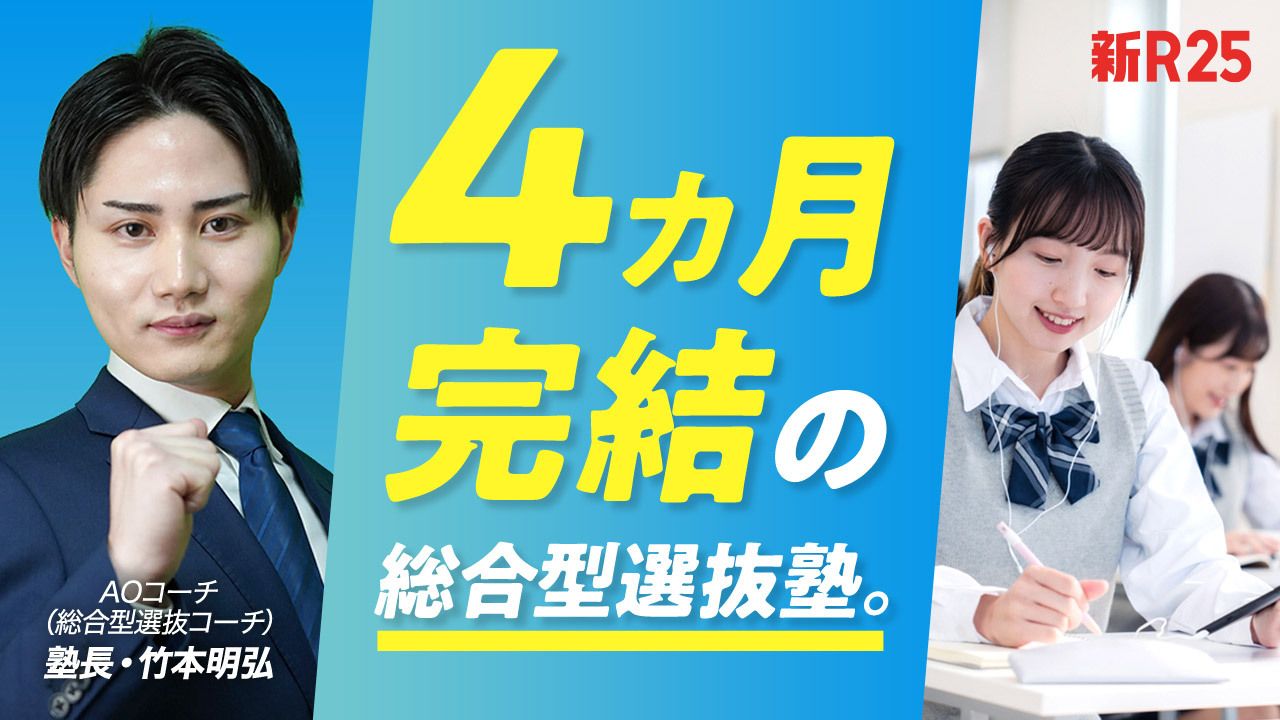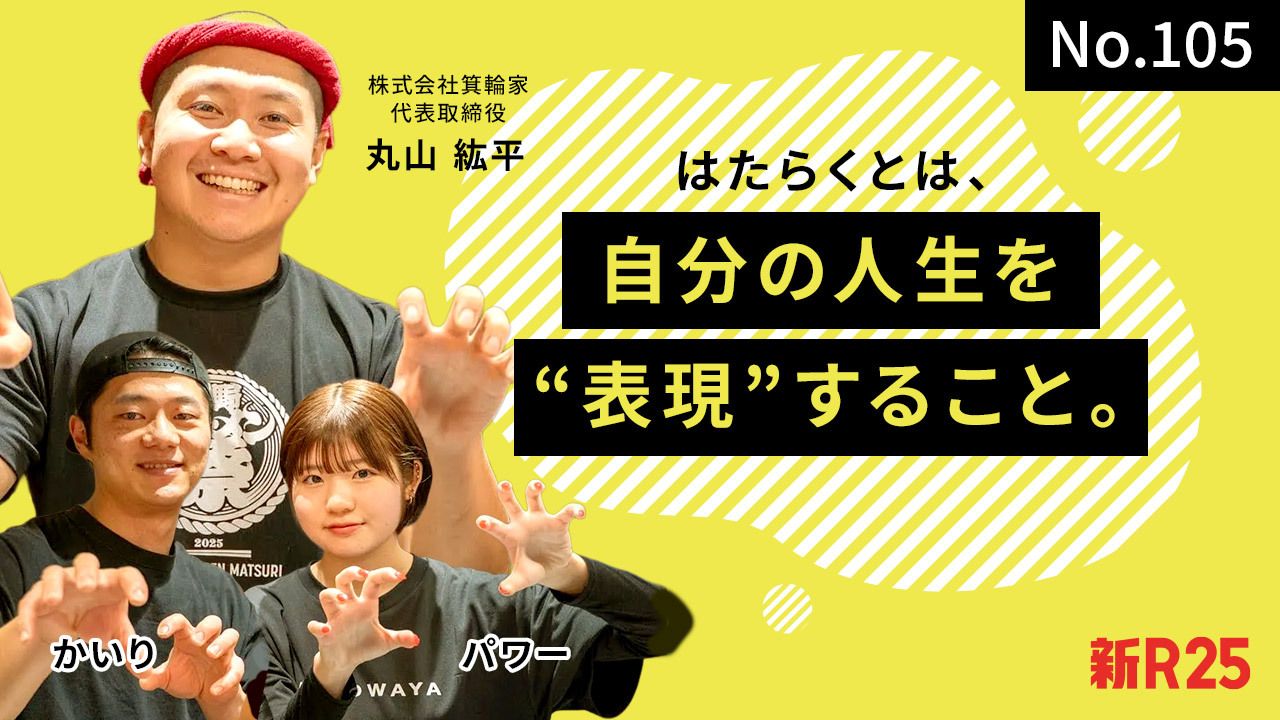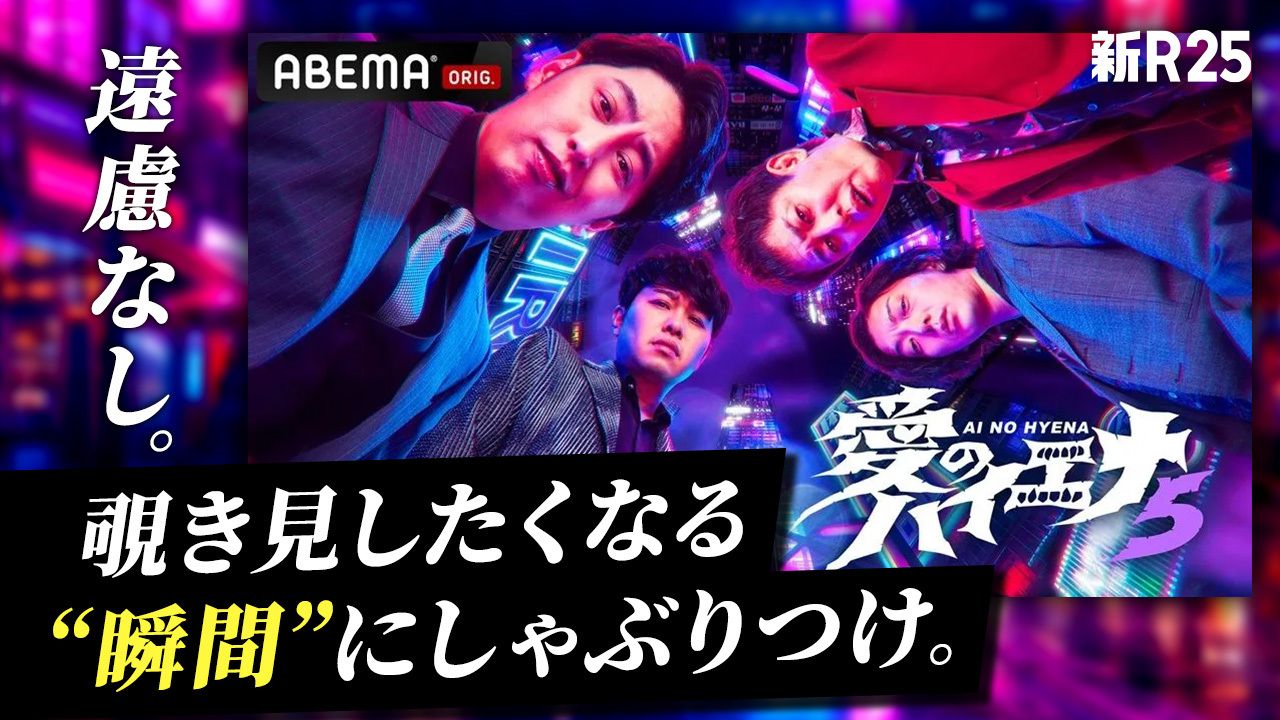企業インタビュー
企業インタビュー
「得意なこと」で社会に貢献。まごころサポートが実現する“はたらくWell-being”
連載「“はたらくWell-being”を考えよう」
新R25編集部
リモートワークの浸透などと相まって、「はたらき方改革」が世間の潮流となって久しい昨今。
現場ではたらくビジネスパーソンのなかには、「本気で仕事に打ち込もうと思ったらはたらき方改革なんて無理」「自分らしいはたらき方なんて難しい」と感じている人もいるはず。
そこで、パーソルグループとのコラボでお送りする本連載「“はたらくWell-being”を考えよう」ではモヤモヤを感じているあなたへ「令和の新しいはたらき方」を提案していきます。

本連載では、学校法人角川ドワンゴ学園が運営するN高グループ生徒会のN/S高新聞実行委員に参加してもらい、「N/S高生“はたらくWell-being”を考える」と題した新企画として、N/S高生が“はたらくWell-being”を体現している人や応援している人、あるいは組織を取材し、高校生の視点からこれからの「幸せ」について考えます。
今回ご紹介するのは、「シニアの毎日に豊かさを」というビジョンのもと、高齢者支援事業を行うMIKAWAYA21の代表取締役社長・青木慶哉(あおきよしや)さんです。
MIKAWAYA21のまごころサポート事業は、シニアの困りごとを解決するだけでなく、孤独や不安を解消する心の豊かさを大切にしています。また、地域住民による「有償ボランティア」という新しいはたらき方を開発し、現在3,000人以上のコンシェルジュが全国で活躍しています。
「シニアが豊かに生きることが、若者の希望につながる」という想いを胸に挑戦を続ける青木さんに、現役N/S高生の笹岡が、ビジネスと社会貢献を融合させたWell-beingなはたらき方について伺いました。
1976年大阪府枚方市生まれ。23歳で、読売新聞販売会社の代表に就任。2012年に15年間経営した新聞販売会社を売却し、MIKAWAYA21を創業。これまでの調達額は10億円を超える。シニア世代のお困りごとをワンストップで解決する「まごころサポート」事業のフランチャイズを展開し、2025年3月現在、加盟店は230社にのぼる。2023年には国土交通省のモデル事業に採択されたシニアの住環境整備事業「まごころアパート」を立ち上げ、今後ジーバーFOODとのコラボ事業として連携していく。またインパクトスタートアップ協会会員も務めている
\ ガイアの夜明けで放映!/
— MIKAWAYA21株式会社 (@MIKAWAYA21_PR) March 21, 2025
「ジーバーFOOD」、働く!じいちゃん ばあちゃん。
超高齢社会の課題を、"シニアの力を活用して解決する"
労働条件は60歳以上!
ユーモアあふれる仕組みで、地域のシニアが笑顔で元気に活躍できる場を提供しています。
TVerで見逃し配信開始!https://t.co/0R0hQdTd65
地域を支える“おしゃべりの価値”

笹岡
まずは、青木さんが代表をされているMIKAWAYA21の「まごころサポート」事業について教えてください。

青木さん
MIKAWAYA21のビジョンは、「シニアの毎日に豊かさを」と掲げてます。僕たちがやっているまごころサポート事業は、簡単にいうとシニアの方のお困りごとを解決する事業です。だから、よく「便利屋さんや家事代行みたいだ」と言われるのですが、決して作業をするだけではないんです。
昨今、高齢社会を取り巻く課題ってたくさんありますよね。たとえばオレオレ詐欺は、毎年警察が注意喚起していますが、件数も被害金額も依然として増え続けています。また、新聞には載っていませんが、詐欺にあった後に自ら命を絶ってしまう高齢者がかなりの数いるそうです。人生の最後に貯めてきたお金をとられてしまい、そして子どもたちから責められ、自分の不甲斐なさに本当に苦しんで、命を絶ってしまうケースが多いそうです。
ほかにも、うつ病患者の約40%は高齢者だと言われていますし、日本の自殺者も40%近くを高齢者が占めているんです。その自殺の理由は、たとえば、身体的に病気になったからだけでなく、病気になり「家族に迷惑をかけるから死にたい」というものなんです。
日本は豊かだったはずなのに、高度成長期を一生懸命に生きてきたシニア世代がこのような状況になっています。日本の家計金融資産は6割超を60代以上の人が保有していると言われていますが、60代以上といえば、不動産をたくさん持っている人もいるし、年金をいっぱいもらってる人もいるし、退職金もマックスの世代です。でも、みんなが豊かではないんです。
つまり重要視すべきは、金銭的な豊かさではなく、ハートを豊かにすることだと思っていて。だから僕たちがやっている「まごころサポート」というシニア向けのサービスで、人間関係の希薄さにともなう寂しさや孤独をなくして、シニアの方の毎日を豊かにしたいんです。


青木さん
これから超高齢社会になっていくのにもかかわらず、今の日本では何十年も頑張ってきたシニア世代が豊かに楽しそうに生きていない。そんな日本では、若い人たちは希望を持てないと思うんです。
僕はとくにおじいちゃん子やおばあちゃん子だったわけではないんですが、今の若い子たちのために、シニアがとにかく豊かでいてほしいという思いを込めて頑張っています。

笹岡
日本の社会課題に真っ向から向き合っているんですね。具体的に「まごころサポート」はどのようなことをしているんですか?

青木さん
ビジネスとして継続するために試行錯誤を繰り返した結果、地域の方たちが地域の高齢者を支える「有償ボランティア」という今のかたちに辿り着きました。このボランティアの方々を、僕たちは「コンシェルジュ」と呼んでいます。
一般的なボランティアは無償ですが、「まごころサポート」では、シニアの方から1時間3,000円のサポート費をいただきます。そのうちの65%である1,950円をコンシェルジュにお支払いする、時給1,950円の有償ボランティアです。


青木さん
1時間1,950円ってなかなか割のいいバイトだと思うかもしれませんが、実際、作業を1時間行い、そこから利用者さんと30分ほどゆっくり座っておしゃべりしてもらっています。
この「作業+おしゃべり」で初めて、シニアにとって付加価値の高い「まごころサポート」が完成します。
実はこのおしゃべりの時間をとても楽しみにしてくださって、86%の方がリピートしてくださいます。だから、おしゃべりの時間も含めると実質的な平均時給は1,000円ちょっとくらいです。決して高いアルバイトではないため、有償ボランティアの方たちは、お金が目的ではなく、地域に貢献したい、誰かの役に立ちたいという方が多いです。
地域で活躍して、ありがとうって言われてうれしい。それに、きちんとお金もついてくるというはたらき方ですね。

笹岡
それこそWell-beingなはたらき方ですね!

青木さん
「まごころサポート」のコンシェルジュさんたちは、特別なスキルとか能力がなくても、地域で普通のお手伝いをして、しっかり貢献しながら稼げます。このコンシェルジュさんたちは、決して作業員ではありません。シニアの良き隣人です。だから、おじいちゃんおばあちゃんたちに寄り添いながら、困ったことを一つひとつ丁寧に解決し、おしゃべり相手にもなっています。
このはたらき方をする人たちが、今3,000人を超えてきていて、今年中には一桁上げたいねと話をしています。まさに地域を支える新しいはたらき方をつくりだしながら、みんなWell-beingに生きていますね。
あと、コンシェルジュさんたちのための「まちなか大学」をつくり、さまざまな技術やスキルを勉強してもらっています。コンシェルジュはパートナー加盟店と業務委託契約を結んでいますから、みんな個人事業主なんです。だから、個人として活躍できる幅を広げることによって、「まごころサポート」でできることもどんどん増やしてもらっています。


笹岡
まちなか大学で、コンシェルジュさんにとくに伝えていることはありますか?

青木さん
「まごころサポート」では、作業だけではなくおしゃべりも重要視しているため、必ず4つの大切なことをコンシェルジュさんに覚えてもらっています。
それは、「観察・洞察・質問・相づち」です。これがおしゃべりをとっても有意義な時間にするんです。
サポートに行った際に、お家のなかを観察してしっかり洞察力をはたらかせると、生活が見えてきます。たとえば、キッチンにレトルト食品やカップラーメンがいっぱい並んでいるのであれば、「お料理つくるのめんどくさくなったりしてない?」って聞いてみます。すると、「誰も家にいないからつくる気が起きなくて、カップラーメンばかりなの。」などと教えてくれます。そうやって会話をしていくと、利用者の方が困っている本質がだんだんと見えてくるんです。
ですからこの「観察・洞察・質問・相づち」の技術を身につけて、本当に意味のあるおしゃべりができる魅力的なコンシェルジュさんをどんどん育てていきたいなと考えています。

コンシェルジュの役割とはたらき方

笹岡
「まごころサポート」は日本全国に展開されていますが、各地域にMIKAWAYA21の支社があるんですか?

青木さん
いえ、フランチャイズのかたちで「まごころサポート」を広めています。
現在は全国で、230社以上の企業から「まごころサポート」をやりたいとお問い合わせをいただいてます。
お問い合わせいただいた地域の企業が私たちのところに加盟してくださって、ノウハウを学んで、そしてコンシェルジュを地元で組織していくというビジネスモデルです。

笹岡
なるほど! 加盟した後はどうやって地域に展開するのですか?

青木さん
加盟した企業には、まずコミュニティマネージャーを1名置いてもらいます。そのコミュニティマネージャーに、一緒に地域を支えてくれるコンシェルジュの募集をしてもらい、「まごころサポート」を立ち上げていきます。
立ち上げてすぐは、経済的にも余裕を持ってお仕事できる方たちに集まっていただいて、その地域のコンシェルジュのコミュニティをつくっています。そして必ず月1回、コンシェルジュたちとランチミーティングをしながら情報を共有しています。
あとは、コンシェルジュだけが入れるSNSもクローズドで運用していて、リアルでもオンラインでもコミュニティでつながっていることをすごく大事にしています。


笹岡
地域内外に仲間がいるのはとても安心しますね。
ほかにも、コンシェルジュさんたちがWell-beingにはたらけるための工夫は何かされていますか?

青木さん
コンシェルジュを始める前の面談では、やりたいことや得意なことだけでなく、逆にやりたくないことも必ず聞きます。そして、やりたくないことは絶対に頼まないようにしています。やりたいこと得意なことで、自分の空いてる時間を使って、地域を支えていきましょうという新しいはたらき方をつくっています。
また、マナーの良くない利用者のもとには、次回から行かなくてもいいというルールになっています。「本当に支えてあげたいと思う人に対して、自分のできることで支えていきましょう」というスタンスで、継続的にシニアの方もコンシェルジュの心も満たされていくことを意識しています。

笹岡
やりたいことで人を支えられるなんて素敵なはたらき方ですね!
福祉と聞くとやっぱり行政や施設をイメージしますが、「まごころサポート」のような仕組みをなぜ思いついたんですか?

青木さん
セーフティーネットとして公的な介護があることはすごく理解しています。けれども、僕たちは介護が必要になる状態を予防することも大切だと思っています。
今は、介護が必要になる前に足腰を鍛えようと頑張って歩いても、鍛えた後の目的や楽しみがない状態なんです。学生の方も、「勉強しましょう」と言われてやる気は出なくても、「将来や夢のために」と考えると頑張りたいと思えますよね。おじいちゃんおばあちゃんたちの頑張りも、「テストでいい点を取るために勉強しなさいと言われたときの虚しさ」と似ています。やっぱりシニア自身が希望を感じられる目的を持てないと、予防をしたいとは思わないんです。
介護の世界は、法律で「これやっちゃいけません」「あれやっちゃいけません」といろいろ縛られます。でも、僕たちは税金ももらっていない民間の事業者なので縛られることがなく、シニアの方が希望を持って生活するためには何ができるかをずっと考えながら、こうやって新しいサービスをどんどん開発しています。

事業をスタートした経緯は?

笹岡
MIKAWAYA21や「まごころサポート」が発足されたときのことを教えてください。

青木さん
僕は、最初は奈良県で新聞販売会社の社長をしていました。新聞を売るためにはたらいていたのですが、時代の流れもあり、シニア世代も「新聞はもう取りません」「新聞はインターネットで見ます」という方がどんどん増えていきました。
そんななかで「それでも新聞をとってくれ」と言っても、スタッフも町の方も誰も幸せにならないなと気づいたんです。そして、新聞のおもな読者層であったシニア層に、新聞販売以外で貢献できることがないか、と考えたんです。
そこで、「日本一じいちゃんとばあちゃんに尽くす会社になります」と宣言し、社名も変えて再出発しました。そうして一人一人のおじいちゃんおばあちゃんを大切にしていると、結果、新聞だけでなく、電化製品やiPhone、リフォームまでいろんなものが売れました。いろんなものを買ってもらった代わりに今度は、「困っている」と聞いたら、どんな些細なことでも喜んで飛んでいきました。
会社の業務にとらわれず、「関わってくれているシニアたちを大切にする」という考えに変えたことで、自分たち自身が「まごころサポート」の価値に気づいていきました。
そうやってできたのが、今の高齢化にともなう社会課題に真正面から取り組むMIKAWAYA21です。一つひとつシニアの方のご要望にお答えしながら「まごころサポート」をやってきましたが、マンパワーのみでは対応が難しくなったため、エイジテック事業も拡大してきました。
これらのアイデアはすべて、シニアの方の本音に一つひとつ耳を傾けて答えたものです。サービスによって集めたビッグデータをシステムに登録して、「シニアの方の悩みを分析してはサービスをつくる」ということを繰り返しています。


笹岡
「まず幸せにする」という“GIVE”の考え方が素敵ですね!
ほかにも、青木さんが仕事で大切にしている価値観はありますか?

青木さん
僕は「起こることすべて自己責任」という言葉がすごく好きなんです。
生まれる環境などの話ではなくて、「商売人として責任を持つ」という考え方です。その責任に対して向き合って、初めて乗り越えていくべき課題と真正面で向き合えるんだと思います。
僕の場合は、新聞が売れない時代になったとき、「時代のせいにしなかった」ことが考えを変えるきっかけになった気がします。

笹岡
なるほど。でも「起こることすべて自己責任」という考え方は、悲観的になってしまわないんですか?

青木さん
やっぱり商売をやっていると、うまくいかないこともたくさんあります。そのたびに最初のビジョンに立ち戻り、「僕が本当にやりたいことはなんだろう?」と自分に投げかけます。
そして「シニアの方の毎日を豊かにして、若い人たちがシニアに憧れる社会をつくること」が僕の目標だと振り返ると、小さな失敗やちっぽけなプライドはポイッと捨ててしまったほうがいい、となる。
ビジョンや志が本当にあれば、傷ついたり挫折している暇はないと思っています。僕もぐったり疲れて、「もうすべて投げ出したいな」っていうときもあります。でも、朝起きるとやっぱり「何のためにこの会社をつくって、何のために自分の命を使うって決めたんだろう?」と自問して、答えに向き合うと、逃げられないなと思ってワクワクするんです。

笹岡
自己責任と考えていくと、逆にワクワクしていくんですね。なんというか…かっこいいです!


笹岡
最後に、青木さんが考える「これからのはたらき方」を教えてください。

青木さん
僕は新聞販売会社をしているときから、スタッフに50冊以上プレゼントしてきた本があります。それは、セス・ゴーディンさんが書かれた『新しい働き方ができる人の時代』(三笠書房)という本です。
この本は、「すべての人は労働者ではなく、アーティストのように生きるべきだ」ということを教えています。つまり、「自分の能力を何のために使いたいか」「自分は仕事を通じてどういう作品をつくりたいか」というように、自分の思いに正直にお仕事をしていきなさいということが書いてあるのです。「まごころサポート」のコンシェルジュさんたちは、まさにこのはたらき方ができる人たちだと思っています。
「まごころサポート」では、コンシェルジュさんたちにやりたくないことを絶対に頼まないようにしていて、本当にしたいことだけをやっていただき、結果としてお金がついてくるという仕組みになっています。この仕組みで日本のシニア世代を支えてもらっています。
僕にとって一番の幸せは、コンシェルジュさんたちがどんどん活躍していくことですね。
<取材・執筆=笹岡 穂乃花>
新着
Interview

自分の力を発揮できるのはどんな局面? 得意×フェーズで実現する “はたらくWell-being”
NEW
新R25編集部

カフェラウンジ&バーを併設した“新時代のメンズ美容室”「The Hair Lounge」が東京・日本橋に誕生
新R25編集部

顧客獲得、まだ苦戦してる…? 効率的にマッチングができる、ビジネスコミュニティ「COB」
新R25編集部
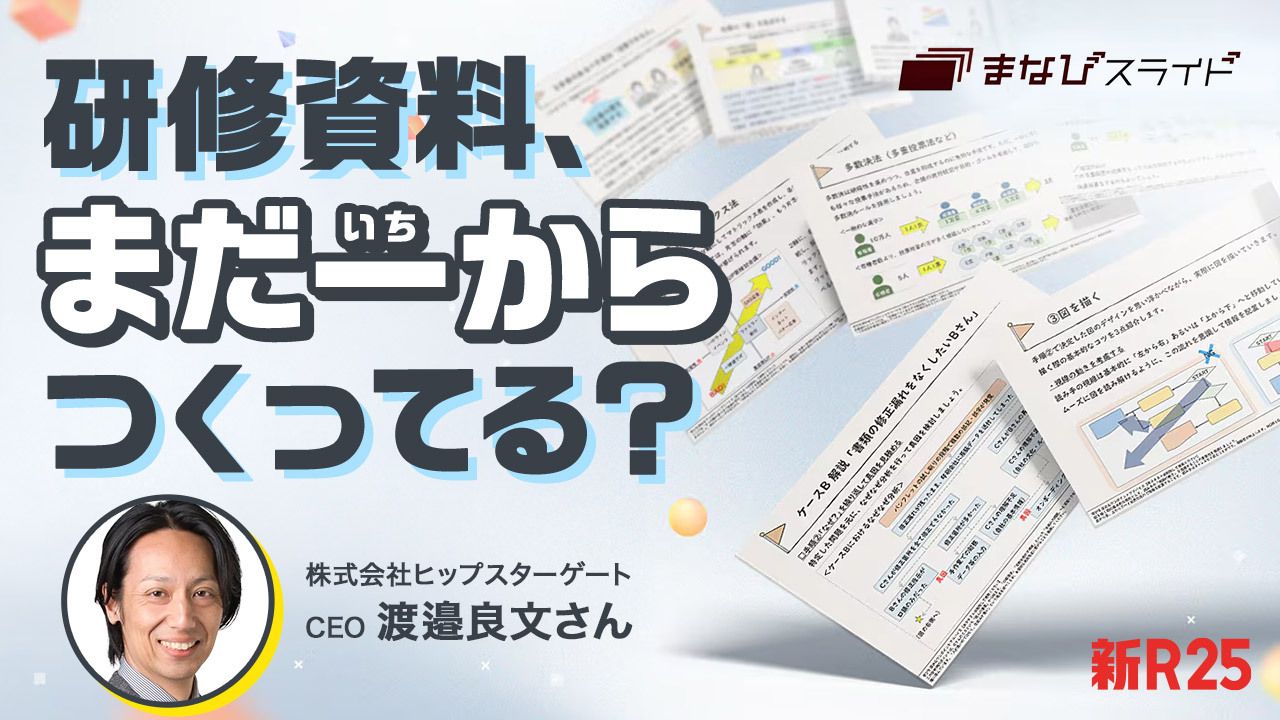
研修資料は“つくる”から“買う”へ。自社仕様にカスタマイズ可能なスライドDLサービス「まなびスライド」
新R25編集部

広告も、映像も、ブランド体験も。「DO/AI」が提案する“企業のAIクリエイティブ活用”
新R25編集部

正解がない“子育てのいま”をリアルに映し出す…ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』始動
新R25編集部