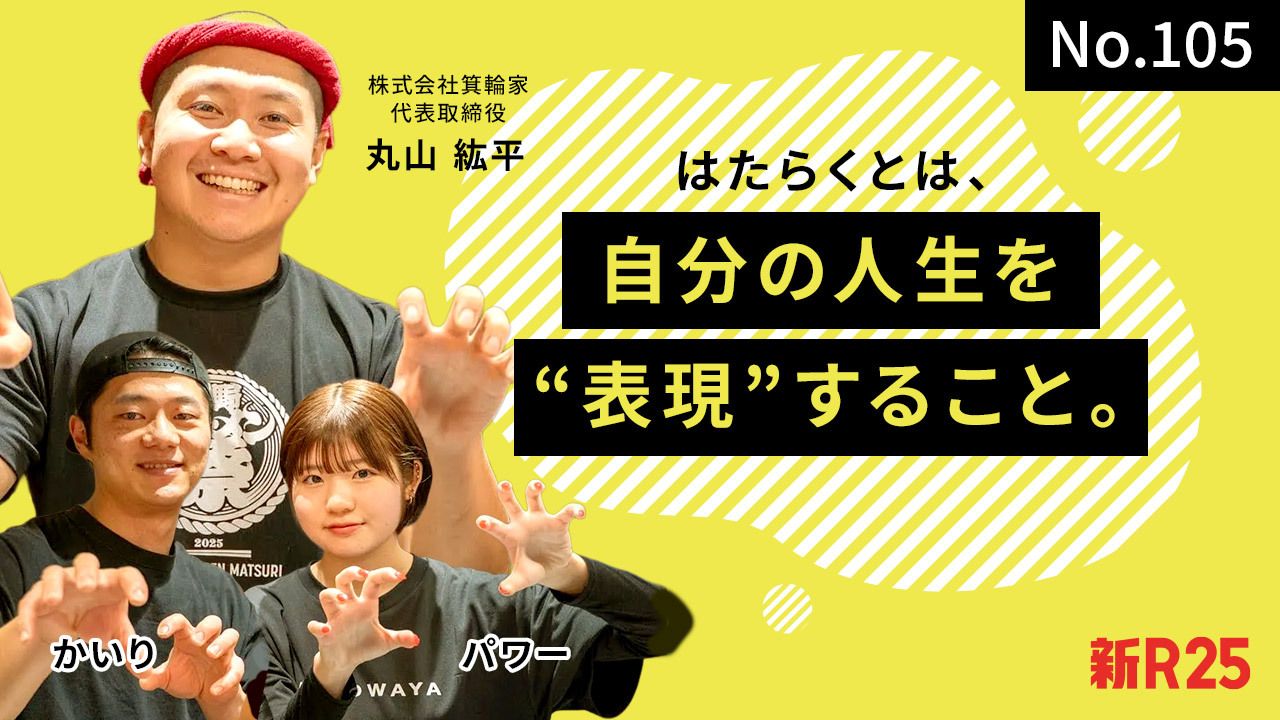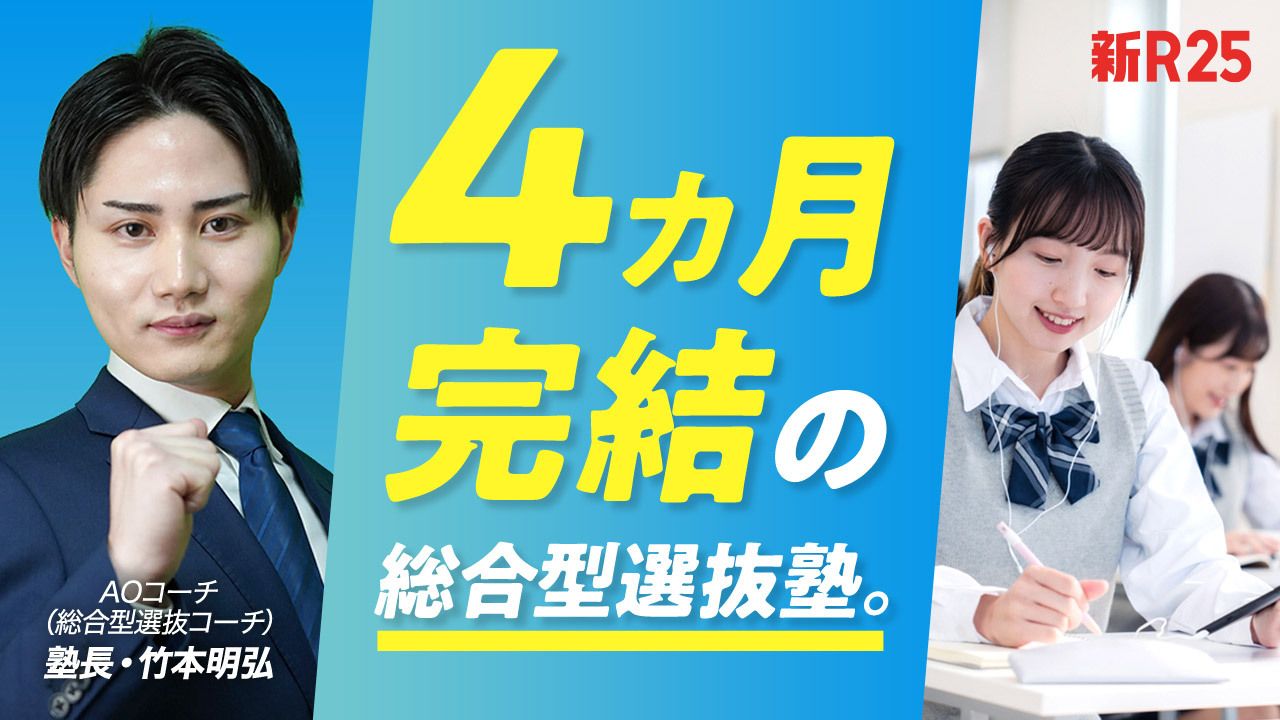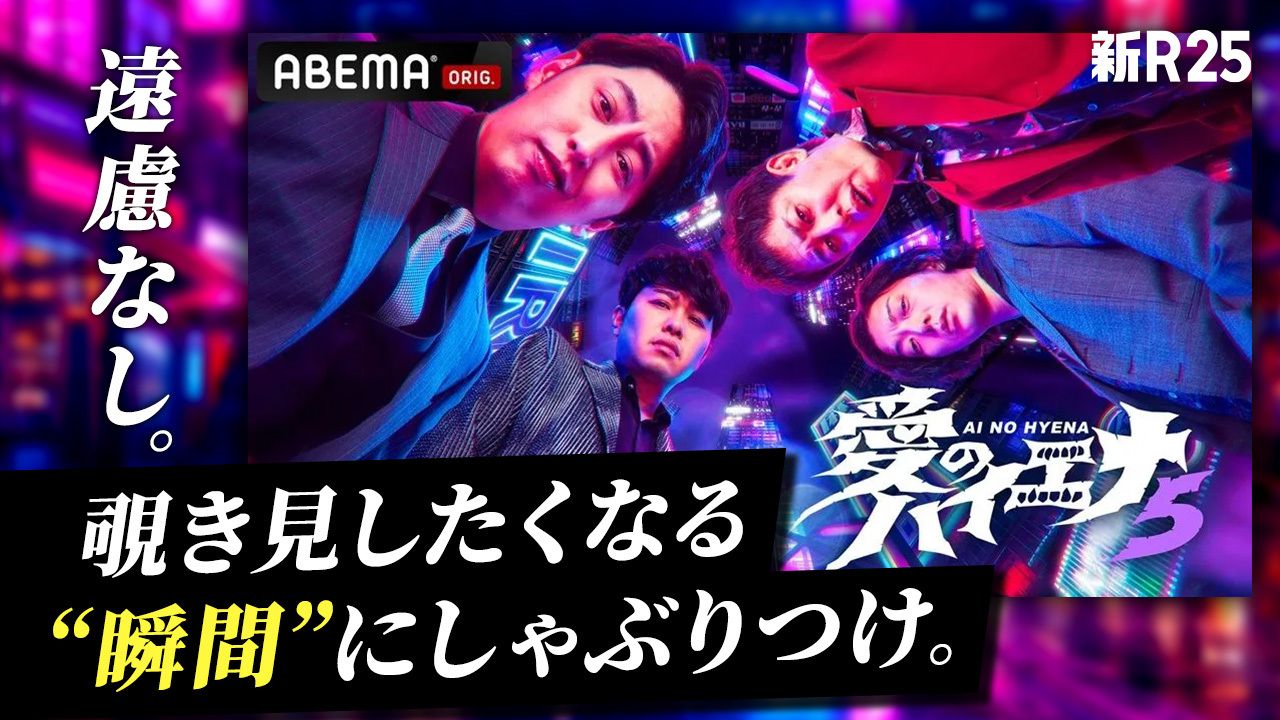企業インタビュー
企業インタビュー
職人気質のお店が「危機感はあった」。データで“無駄のない仕入れ”を実現した「DXツール」導入事例
「具体的な“お客さま像”を描けるようになった」
新R25編集部

店舗業務の煩わしい作業をすべて自動化してくれる経営支援ツール「TOUCH POINT BI」。
自家製麺の店を展開する「味一番フード」では、「TOUCH POINT BI」を使った業務効率化で利益を拡大中です!
味一番フードの代表取締役専務・村上良一さんいわく「データのおかげで、“お客さま像”を思い描きながら販売戦略を練れるようになった」とのこと。
村上さんと「TOUCH POINT BI」を開発した株式会社EBILAB・常盤木龍治さんに、店舗経営にデータを活かすコツをお聞きしました。
〈聞き手=山田三奈(新R25編集部)〉
「職人の感覚」から「データ分析」へと変化

村上さん
「味一番フード」は、石川・富山県内で自家製麺の店「めん房本陣」を7店舗、「そば処花凛」を2店舗展開しています。
何年経ってもまた食べたくなる、飽きのこないベーシックなおいしさが自慢です。

山田
御社が「TOUCH POINT BI」を導入する前は、どのような課題がありましたか?

村上さん
根っからの職人気質なもので…数値ではなく、感覚で仕事をしていましたね。
感覚頼りだから、ある程度のキャリアがなければ店舗の中心的な仕事ができませんでした。

山田
導入のきっかけは何だったんでしょう?

村上さん
石川県が開催した「デジタル化実践道場」がきっかけでしたね。

常盤木さん
「デジタル化実践道場」は、AIやIoTなどのデジタル技術を活用できる人材を育成するために、石川県が2018年から行っている事業です。
2022年の開催時に、企業の現況に対して「データ活用でどのようなことができるのか」を考察するべく「TOUCH POINT BI」をモデル的に導入いただいたんです。

山田
なるほど。それが「TOUCH POINT BI」に触れる機会になったと。

村上さん
ちょうど「感覚ではなくて数値データを裏付けとした精度の高い経営をしていきたい」と考えていたところでした。
半年間テストで「TOUCH POINT BI」を使わせていただくなかで課題を克服できる手応えを感じたので、本格的な導入を決めたんです。
感覚的ではない需要予測や、より深いデータ分析ができる点に魅力を感じています。
集客の予測・無駄のない発注・効率的なシフト組み…すべてデータで

山田
「TOUCH POINT BI」は、どのようなことに役立っていますか?

村上さん
日々データを見て、いろんな販売戦略を立てています。
経営側がデータを見ながら、いろんな販売戦略を立てるだけでなく、現場でも予測のデータを仕入れの発注などに役立てています。
他にも、現場では各スタッフのシフトを効率的に組んだりすることも可能になりました。

山田
販売戦略はどのように変わりましたか?

村上さん
各店舗の時間ごとの客数やよく使用されているテーブルのデータ、平日や週末など様々なデータから各店舗の”お客様像”を描けるようになったことで、精度の高い販売戦略を練られるようになりました。
以前にも販売管理ソフトは使っていたんですけど…そのときのデータは“結果論”という感じで、ここまで業務に活かせる相対的なデータの取得はできていなかったと思います。

常盤木さん
村上さんは、経営とデータをしっかり結びつけて利用していただいてる印象ですね。

常盤木さん
「経営において何のためにデータを使うのか」をヒト・モノ・カネやマーケットを見据えて考えているのは村上さんだけだったと思います。
普通は「デジタル化したい」という理念が先行しがちなんです。その結果、残念ながら”ただのIT導入”になっているケースが多い。
村上さんには考え方自体の中に解決したい課題が明確にあって、そこに僕らをあてがっている状態なので、最初から成功するイメージはありましたね。

村上さん
私がデータを大いに活用しているのはもちろんですが…現場で働くスタッフにとっても「TOUCH POINT BI」が心強い存在になっていると思います。
じつは今度、お店の運営にプラスして「物販の販売」の分野も開拓しようと思っているんです。
「TOUCH POINT BI」を活用して、物販を購入しそうな客層や、ほかにどのような商品がほしいかを分析できる手応えを感じています。
データシステムを拡大してさらなる効率化を狙う

山田
「味一番フード」には店舗がいくつかあると思いますが、今後さらに「TOUCH POINT BI」を導入していく予定はありますか?

村上さん
はい。もともと2店舗で導入していたんですが、今年度の石川県のデジタル補助金を使って、5店舗まで導入を広げました。
今後はさらに多くの店舗に導入して効率化アップを狙っていきます。
それにプラスして、セントラルキッチンで「食材の発注テスト」を始めたんですよ。

山田
セントラルキッチン…?

村上さん
飲食店のメニューの製造や加工を一カ所に集中させる拠点のことです。
「TOUCH POINT BI」を導入した5店舗で「どれくらい食材が減っているか」 「どれくらいの食材が必要か」という需要のデータを取って、食材の発注が多すぎたり少なすぎたりしないように調整しようと思って。
2カ月くらいテストしているんです。

常盤木さん
村上さんは、こんな感じで走りながらつねに挑戦しているところが素晴らしいと思っています。
ただでさえ新しいツールの導入に抵抗を感じる方が多いなかで、「TOUCH POINT BI」の“データ”“分析”とかを苦手とする方は本当に多いので...。

村上さん
もともと「感覚に頼ってパワフルに頑張るだけではダメだ」 「デジタルを導入しなきゃいけない」という強い危機感があったので。その危機感が行動になっているんだと思います。
でもそれだけではなくて、そこで働く人とお客さんとの接点など、店員さんの方の「やっててよかった」みたいな報われ感なども大切にしないといけない。
例えばお客さんがご飯を食べてる瞬間を少なからずちゃんと見れる余裕のあるスタッフを作っていく。
そのための設備としてDXをしていこうという思いはありますね。
データを活用することで、無駄なコスト削減や利益の拡大につなげる「TOUCH POINT BI」。
ITツールをただ導入するだけでなく、「経営のどこに効かせるためのデータなのか」を考え続けることが、利益拡大において大事なのかもしれません。
店舗経営をしている方は、「TOUCH POINT BI」の導入を検討してみては?
新着
Interview

自分の力を発揮できるのはどんな局面? 得意×フェーズで実現する “はたらくWell-being”
新R25編集部

カフェラウンジ&バーを併設した“新時代のメンズ美容室”「The Hair Lounge」が東京・日本橋に誕生
新R25編集部

顧客獲得、まだ苦戦してる…? 効率的にマッチングができる、ビジネスコミュニティ「COB」
新R25編集部
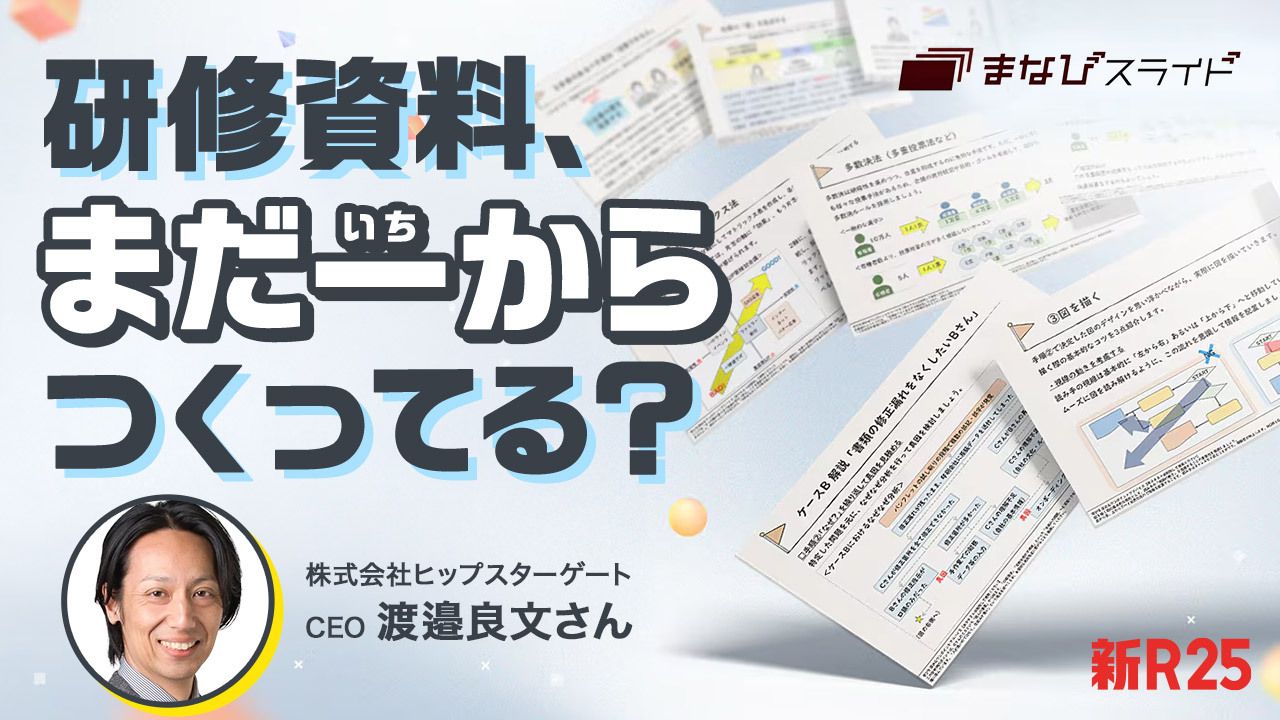
研修資料は“つくる”から“買う”へ。自社仕様にカスタマイズ可能なスライドDLサービス「まなびスライド」
新R25編集部

広告も、映像も、ブランド体験も。「DO/AI」が提案する“企業のAIクリエイティブ活用”
新R25編集部

正解がない“子育てのいま”をリアルに映し出す…ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』始動
新R25編集部