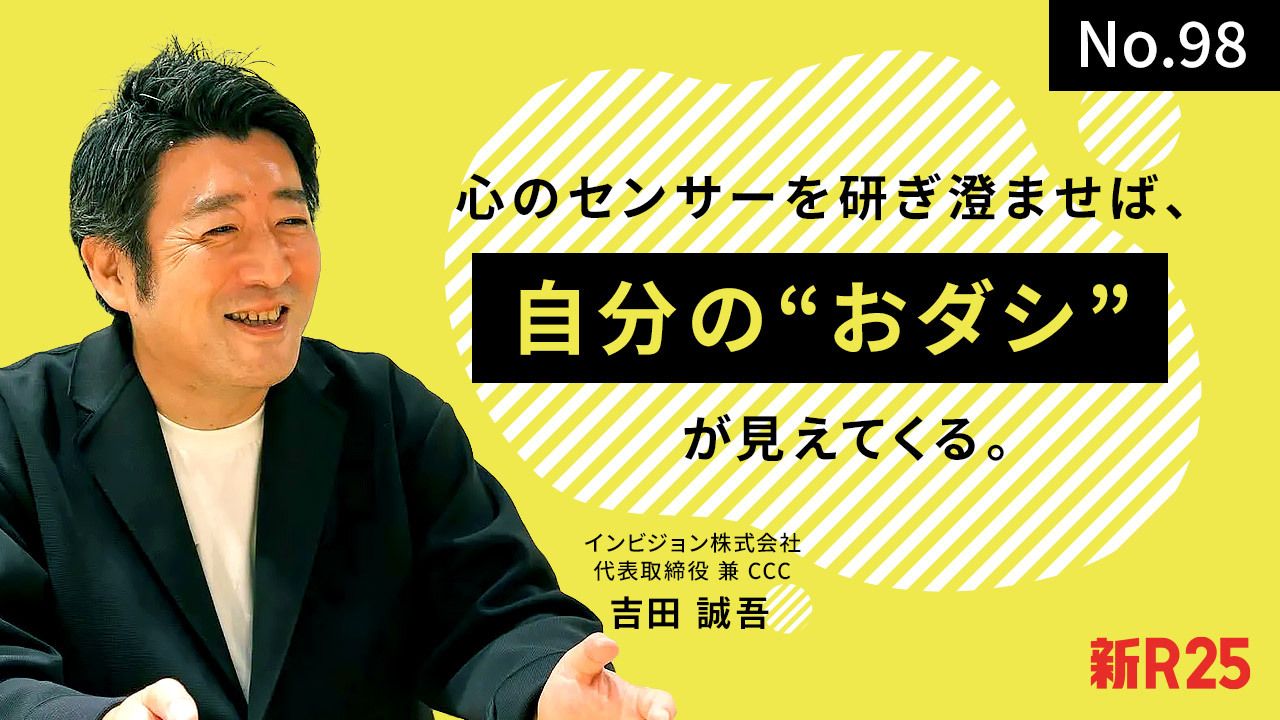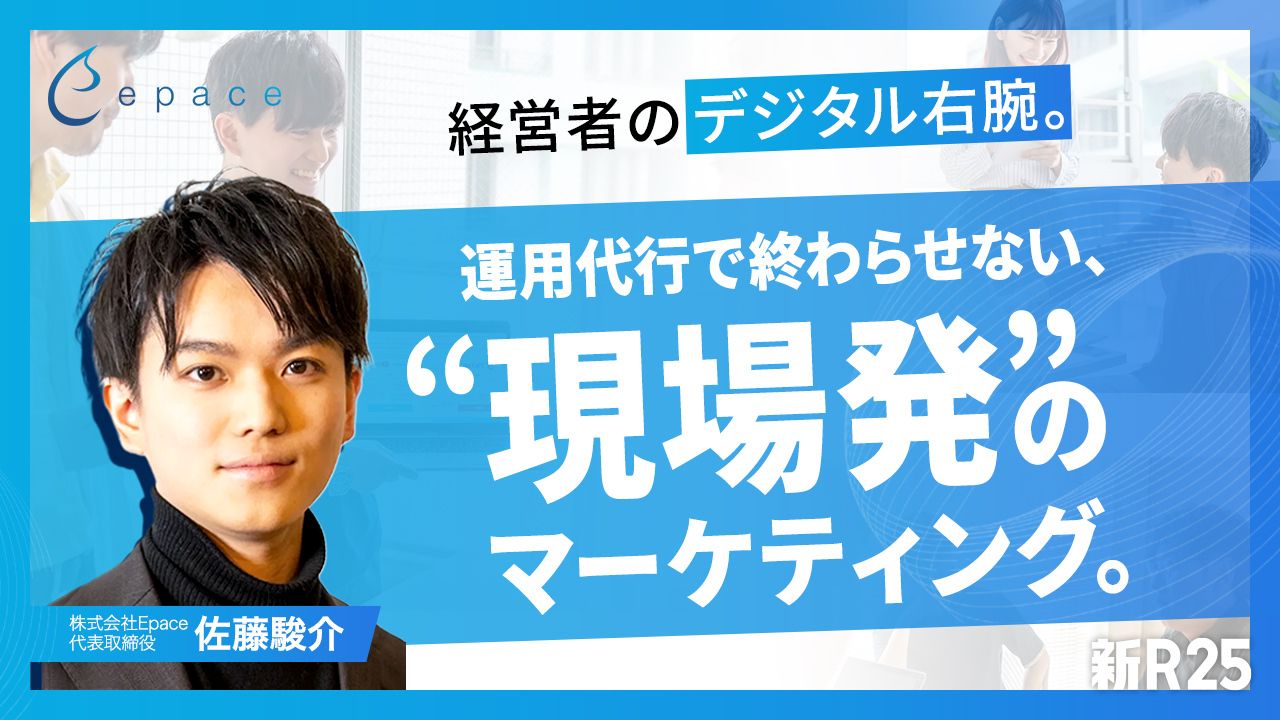企業インタビュー
企業インタビュー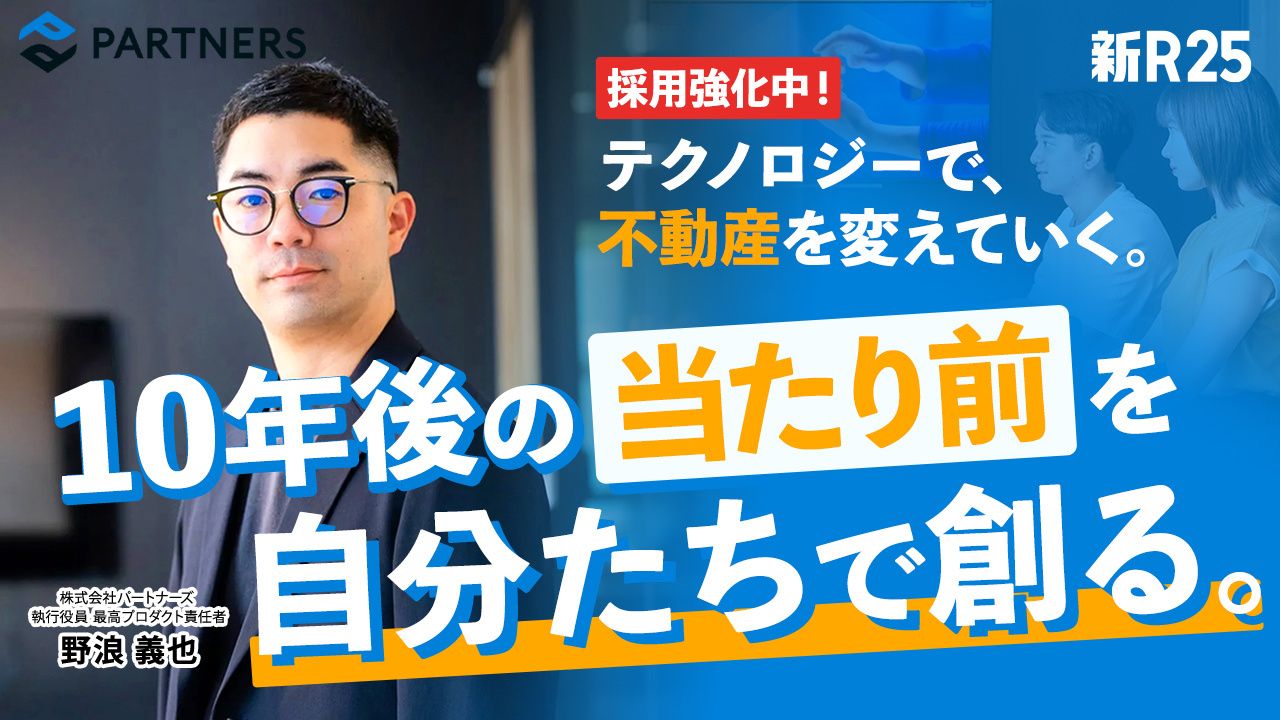
「変わる仕組みを自らの手で創る」株式会社パートナーズが挑戦する不動産市場の改革とは
CPOが語る「まだ何者でもない僕らが、“社会の当たり前”に挑む理由」
新R25編集部
「社会を変えるような仕事がしたい」
そんな希望を抱く就活生にとって、不動産というフィールドは、もしかしたら“想像以上の可能性”を秘めた選択肢かもしれません。
株式会社パートナーズは、不動産売却という人生において数少ない意思決定の場面を、「もっと納得して選べる体験」に変えようとしています。業界ではまだ珍しい“オンライン完結”の売却プロダクトを開発し、「仕組みごと変える」ことに挑んでいるのだとか。
話を聞いたのは、同社でCPO(Chief Product Officer)を務める野浪義也さん。
UX・テクノロジー・現場の知見を掛け合わせて、不動産という巨大市場の構造を見直す──そんな野浪さんの言葉の一つひとつが、「社会の前提を変える」ことの本質を突いているようでした。
アジェンダ
・“変えがいのある産業”としての不動産
・「“納得して選ぶ”とは何か?」を、構造から設計する
・テクノロジーは、人が“本当にやるべきこと”のためにある
・パートナーズというチームだからこそ、“仕組みから変える”挑戦ができる
・社会の当たり前を、あなた自身が変えていく
“変えがいのある産業”としての不動産

野浪さん
不動産投資マーケットは日本国内で約65兆円という、GDPの1割以上を占める巨大な市場なんです。
しかもその多くが、まだアナログな仕組みのまま動いている。FAXが当たり前に使われていたり、契約のたびに何度も対面で書類のやり取りをしたり。
テック業界にいる人からすれば信じられないかもしれませんが、2025年にもなって、紙と電話が主流の業務が多いんです。
ーー(編集部)たしかに、お部屋探しや賃貸契約でも「書類が多くてよくわからなかった」って話をよく聞きます。

野浪さん
そうですよね。たとえば初めてひとり暮らしで賃貸契約をしたとき、
「この契約って本当に大丈夫?」
「この費用、何に使われてるの?」
「どうしてこんな手続きが必要なんだろう?」
と戸惑った経験がある方も多いはずです。
それが“自分の不動産を売却する”立場になったら、もっと複雑で高額な話になります。専門用語や判断ポイントも増えて、不安や不透明さは何倍にもなる。
でも、そうした不便さに対して、多くの人が「不動産ってそういうものだから…」と、流してしまっているのが現実なんです。
ーー(編集部)テクノロジーで変化を起こす余地が、まだ大きく残っているんですね。

野浪さん
はい。投資用不動産の売却にしても、「売るか、持ち続けるか」といった意思決定が人生に大きく関わるのに、情報が不透明で、判断材料も不足していて、最終的にはすべて理解しきれないまま売却してしまっているケースも少なくありません。
私たちのプロダクトがその構造を変え、誰もが自分の意思で納得して選べるようになれば、それだけで資産形成のあり方が変わりますし、日本の資産流動性にも影響が及びます。
ーー(編集部)たしかに、不動産の売買が変われば、人の暮らしや経済の在り方も変わっていきますね。

野浪さん
不動産は「変わらない産業」ではなく、「変えたときの影響が最大級の産業」です。
だからこそ僕たちは、テック・UX・リアルの力を融合しながら、泥臭く仕組みをアップデートしていくことに、本気で取り組んでいます。
「“納得して選ぶ”とは何か?」を、構造から設計する
ーー(編集部)「テクノロジーで不動産を変える」と聞くと、便利なUIをつくることや、手続きをデジタルに置き換えることをイメージしますが…

野浪さん
もちろんそういった部分も重要ですが、それはあくまで“手段”です。
僕たちが本当にやりたいのは、お客さまが「納得できる意思決定」を実現すること。
不動産って、一生のうちに何度も経験することではないのに、売却後、多くの人が心残りがあると感じているんですね。
ーー(編集部)具体的に、どんな課題があるのでしょうか?

野浪さん
実際にあったケースを例に挙げると、「この価格で売っていいのか?」「今、売るべきなのか?」といった判断が求められる状況なのに、判断材料が手元に揃っていない場合。
「プロが言うなら...」と決めてしまい、あとで「本当にこれで良かったんだっけ?」とモヤモヤが残ったということが多いんです。
実際、弊社が行った売却経験者へのアンケートでも、約8割の方が「何かしらの心残りがある」と答えています。
納得って、「自分でちゃんと理解して、自分で選んだ」と思えることから生まれます。だからこそ、僕たちは単に利便性を上げるのではなく、“納得の設計”をプロダクトに落とし込もうとしています。
ーー(編集部)どうやって「納得」をプロダクトに落とし込んでいるのですか?

野浪さん
たとえば、ユーザーがどこで迷っているかを可視化し、次のアクションの選択肢を直感的に示すUIを設計したり、価格シミュレーションや市場データをリアルタイムでわかりやすく提示することで、感覚ではなく、根拠をもって判断できる状態をつくっています。
プロに頼らなくても、自分で納得して意思決定できる。そういう状態を、構造ごとプロダクトで支えるんです。
ーー(編集部)なんとなく選ぶ、ではなく、納得して選ぶ。それが可能な設計にしていると。

野浪さん
はい。不動産のように高額で責任の重い取引だからこそ、その意思決定の体験を根本から変えることには、大きな社会的意味があります。
そしてそれは、UXデザインの積み重ねや、ユーザー行動の分析、リアルな顧客対応の知見が融合しないとできません。
僕たちがやっているのは、ただの“売却ツール”の開発ではなく、「人が自分の未来を自分で決められる構造をどうつくるか?」という問いに向き合う仕事なんです。
パートナーズは、そういう軸を持って動いていることが売却後に喜びの声をいただく結果につながっているのだと思います。
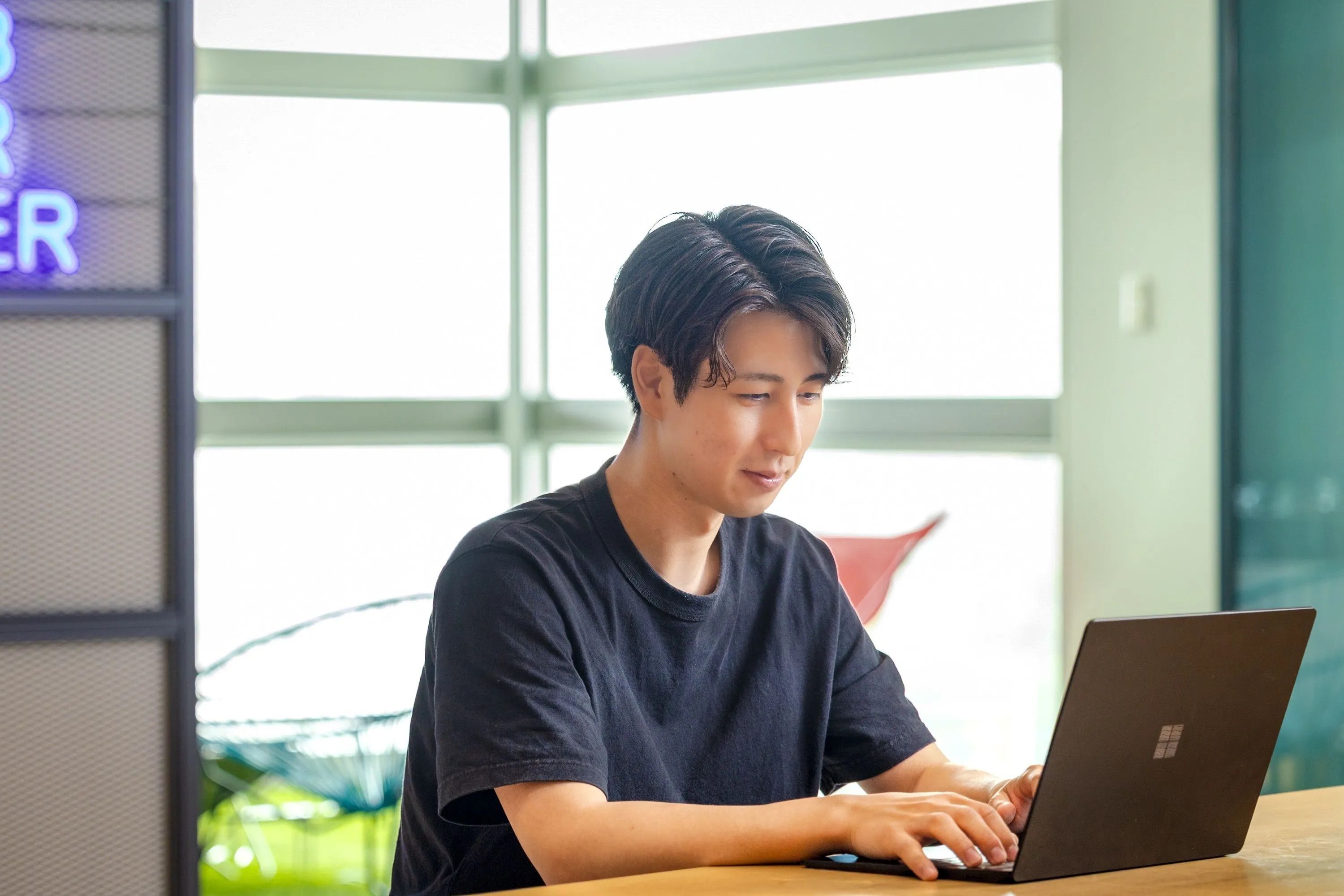
テクノロジーは、人が“本当にやるべきこと”のためにある
ーー(編集部)不動産×テクノロジーというと、顧客側の利便性ばかりに注目が集まりがちですが、パートナーズでは社内の在り方にも変革が起きているそうですね。

野浪さん
はい。僕たちが変えたいのは、「ユーザーインターフェースのような接点」だけではなく、「産業の深部にある構造」です。「社内の人が、本質的な価値を発揮できる仕組み」をつくることもその変革のカギになります。
テクノロジーを活用する目的は、単なる効率化ではありません。もっと根源的に、“人がやるべきことに集中できる状態”を創造することにあります。
不動産業界の現場には今もなお、紙での契約、手作業でのスケジューリング、電話での確認作業など、旧態依然とした業務が根強く残っています。こうしたアナログな構造を、僕たちはテクノロジーの力で一つひとつ丁寧に解きほぐしている最中です。
ーー(編集部)効率化だけを見据えるのではなく、もっと広く業界全体の変革のためにテクノロジーを活用していく、ということですね。

野浪さん
たとえば営業においては、お客さまの意思決定に伴走する存在であるべきで、そのためには背景理解や対話にこそ時間を割く必要があります。
「人にしかできない仕事」の比重を最大化すること。その対話や理解の時間を守るために、テクノロジーがある。
僕たちはそう信じて、現場の“仕組み”そのものをアップデートし続けています。
そして社内フローの自動化、営業活動の一元管理、顧客接点の情報共有など一見“裏方の改善”に見える取り組みの先には、「この人になら相談したい」「この仕組みなら自分で決められる」と思える信頼体験が生まれます。
僕たちが向き合っているのは、不動産業界に長く根付いた“非効率を前提とする構造”そのもの。それを変えることで、セールスにとっても、顧客にとっても、もっと価値のある、唯一無二の体験にしていきたいと思っているんです。
ーー(編集部)テクノロジーを、冷たい最適化ではなく「人の力が活きる土台」として使うと。

野浪さん
テクノロジーに任せられることは任せて、人は「向き合うべき仕事」にしっかり向き合える状態をつくる。
そうした仕事のあり方が、現場にも顧客にも誠実な選択肢を増やしていくと信じています。
「人が力を発揮できる構造をつくること」。それが、僕たちがテクノロジーに託している役割であり、パートナーズらしさだと考えています。

パートナーズというチームだからこそ、“仕組みから変える”挑戦ができる
ーー(編集部)ここまでお話を聞いて、「テクノロジーを使って構造から変えていく」姿勢に強いこだわりを感じました。そうした取り組みが、なぜパートナーズで実現できているのでしょうか?

野浪さん
パートナーズは、仕組みを変えることに本気で取り組める“土壌”があるチームなんです。
僕らはGAテクノロジーズグループの中で、不動産売却領域を担っていますが、同時に「イノベーションの起点」としてグループ全体を牽引しているポジションにあります。
ーー(編集部)具体的には、どんなところにパートナーズならではの特性があるのでしょう?

野浪さん
まず1つは、現場とプロダクトが密接につながっていることです。営業やカスタマーサクセスが日々感じている課題感やお客さまの声が、すぐにプロダクト開発に反映される仕組みがあります。
「こんなことで迷っていた」「こうしたらもっと良くなるかも」──そういったリアルな気づきが、どんどん設計に活かされていく。しかもそれが「トップダウンでやらされる」んじゃなくて、一人ひとりが“自分ごと”として関わっているのが特徴です。
僕たちは、まだ正解が決まっていない領域に、自分たちで仕組みや枠組みをつくっていく仕事をしています。だからこそ、「まずはやってみる」「うまくいかなくても、そこから学ぶ」という姿勢が当たり前になっている。
パートナーズには、役職や年次に関係なく、現場から生まれた問いや仮説をすぐにプロダクトに反映できるスピード感と裁量があります。
大きな仕組みを動かすには、理想を掲げるだけじゃなく、現実に向き合い、地に足をつけて積み上げていく覚悟が必要です。その両方を大切にできるのは、「業界を本気で変えたい」と信じて動く仲間がいるからこそです。
ーー(編集部)だから、単なるプロダクト開発や事業推進ではなく、“業界変革”の一歩につながっているんですね。

野浪さん
しかも僕たちは今、“スケールアップ企業”として、次のフェーズに挑戦している真っ最中。これが2つ目の特性です。
不動産テック領域のなかでも業界最大級の基盤を持ち、着実な実績を築いてきた一方で、業界全体にはまだ紙・FAX・対面が根強く残るなど、アップデートの余地が山ほどある。
つまり、プロダクトは育ちつつある。でも、業界はまだ変えきれていない──そこに、リアルで手応えのある挑戦が眠っているんです。
組織としてもまだ200人規模で、整えきれていない部分もある。けれどだからこそ、意志ある一人ひとりの動きが、会社を、事業を、社会を前に進めていく原動力になる。その実感を、日々味わえるのが今のパートナーズです。
挑戦のスケールも、裁量も、これからの伸びしろも、全部そろっている。だから僕は、「裁量を持って社会を変える仕事がしたい」という人には、今のこのフェーズのパートナーズを心からおすすめしたいと思っています。

社会の当たり前を、あなた自身が変えていく
ーー(編集部)パートナーズで働く魅力を教えてください。

野浪さん
パートナーズで働く最大の魅力は、「10年後の“当たり前”を、自分たちで創っていける」ことだと思っています。
世の中で今当たり前に使われているものの多くは、かつて「そんなの無理だ」と言われていたことばかりです。
でも、それを信じて動いた人たちがいたから、今の社会がある。僕たちも、不動産という大きな産業で、まさにそれと同じようなことに挑んでいます。
不動産業界は、オンライン取引の割合がいまだ1%という、いわば“変えがい”しかない産業です。契約は紙とFAX、情報はブラックボックス化し、初めての人ほど置いていかれてしまう。
でも私たちは、そうした“仕組みの当たり前”を見直し、「誰もが自分で納得して選べる社会」を目指して、仕組みそのものをアップデートしています。
ーー(編集部)とはいえ、それをゼロからつくるのは、かなり大変な仕事では?

野浪さん
はい。でも、だからこそ面白いんです。
パートナーズは、すでに市場に受け入れられつつあるプロダクトと、お客さまから選ばれ続け、創業以来ずっと増収増益をし続けてきた実績があります。
一方で業界全体を見れば、まだ“仕組みとして変わりきれていない”ところが山ほどある。
いわば今は、会社としての「第二創業期」。まだ整っていない部分も多いけれど、その分、自分の挑戦がダイレクトに社会や組織を動かせる。
ーー(編集部)それが「スケールアップ企業」ならではの面白さなのですね。

野浪さん
ベンチャーのゼロイチの熱量も持ちながら、社会に出せる成果・信用もある。
その両方を併せ持つ今だからこそ、「これからの社会にとって必要なスタンダードとは?」という問いに、真っ向から取り組めるフェーズにいます。
制度も、カルチャーも、プロダクトも、まだまだこれから。「正解がないからこそ、自分が動く意味がある」と思える人にとっては、これ以上ない環境だと思います。
ーー(編集部)最後に、学生の皆さんへメッセージをお願いします。

野浪さん
変化を待つんじゃなく、自分が変化の起点になる。それってすごく勇気がいることですが、誰かがやらなきゃ社会は変わらない。
でもそれを「自分がやるんだ」と思った人が、時代を動かしてきたんだと思います。
今世界のトップに君臨している企業も、最初は“無謀”とすら言われたところから始まっている。その火種になったのは、たった数人の「やってみよう」という意志です。
パートナーズも、そんな挑戦ができる場所です。ただの“仕事”ではなく、「社会の仕組みそのものに問いを立てていく仕事」がしたい人には、きっとすごくフィットすると思います。
まだ何者でもない自分が、社会の“当たり前”を変えていく。そんな経験を、本気でしてみたい人を、僕たちは待っています。
新着
Interview

クラファンでも大反響。注目したい、次世代“エイジングケア”サプリ
NEW
新R25編集部
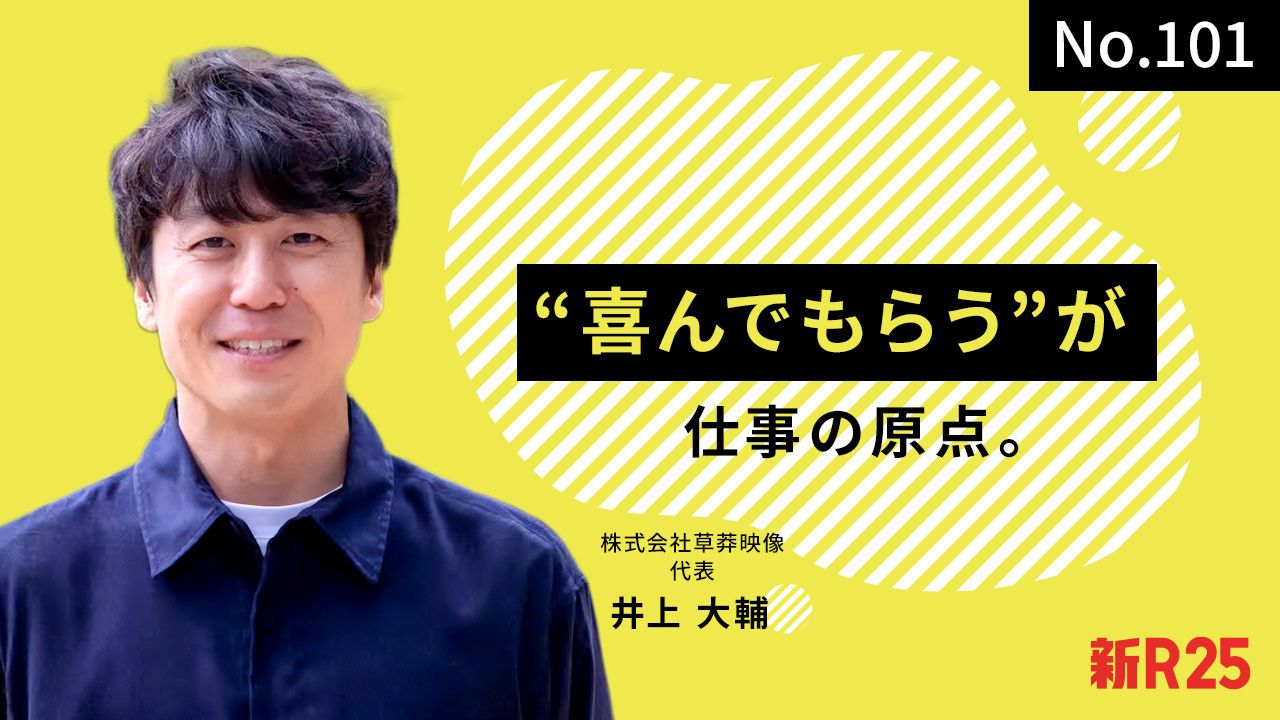
会社の名前じゃなく、自分の名前で仕事をする——元NHKディレクターが独立してつかんだ“はたらくWell-being”
NEW
新R25編集部

ケムリ「かなり不安です!」くっきー・ザコシと“MADな芸人”によるルール無用の番組が新春スタート
新R25編集部
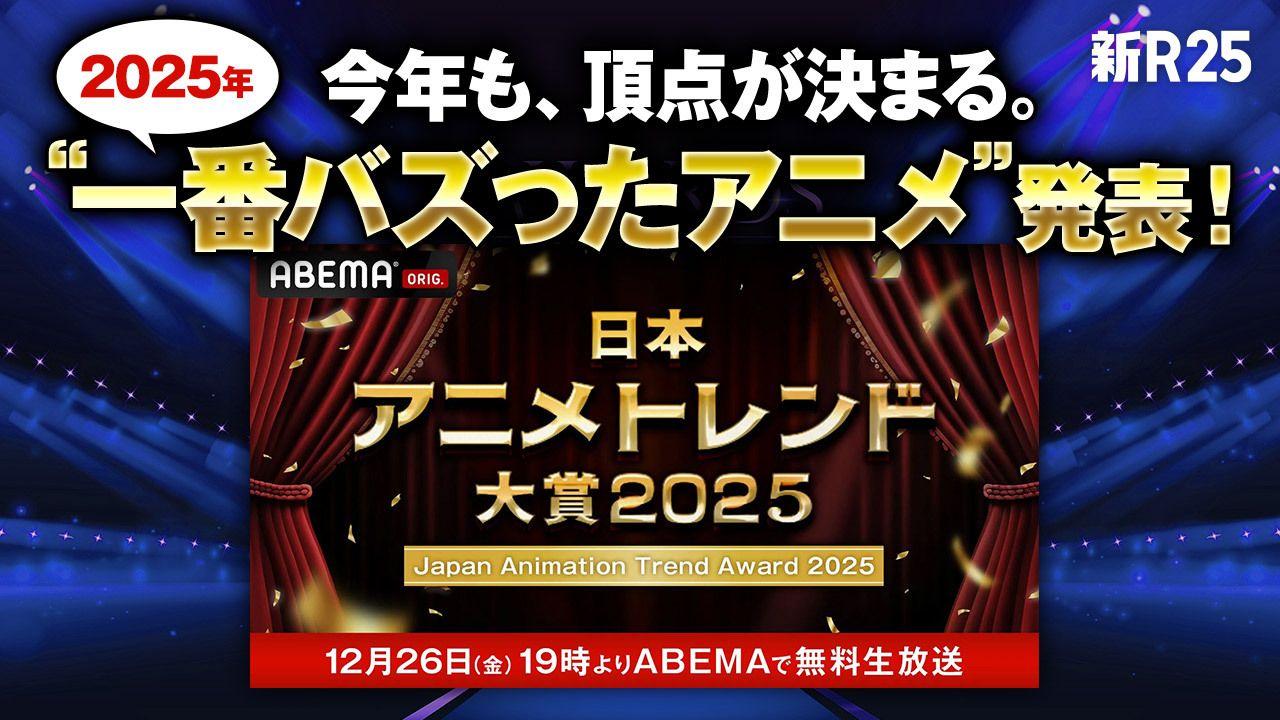
アニソンライブも無料生配信!“No.1バズアニメ”を決めるABEMAのアニメアワードが今年も開催
新R25編集部

たった“20分”でSEO記事が完成。月1,000万MAUのノウハウをAIで再現した「AI編集長」が革命的
新R25編集部
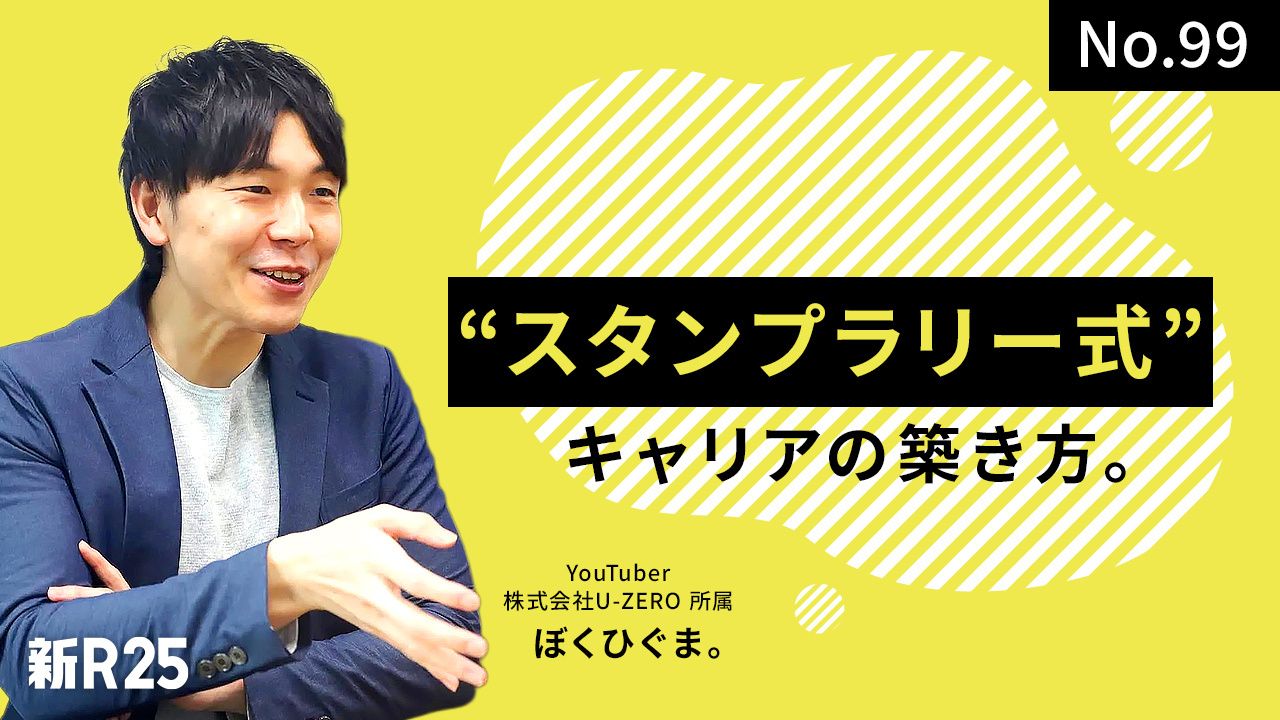
職務経歴書、華やかにしてる? 元銀行員YouTuber・ぼくひぐまが見つけた“はたらくWell-being”
新R25編集部